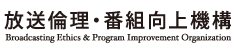「娘を暴行被害者と誤認報道」母親からの苦情
「強盗傷害事件の被告に対する論告求刑(懲役12年)を伝えたニュースの中で、自分の娘が暴行事件の被害者であるかのように放送された。このような報道で、また、娘や家族が大きなショックを受けている」との苦情。
当該放送局は訂正放送を実施したが、母親の了解を得られず話し合いが続けられた。2002年6月になって、今後、被害者の立場、気持ちに最大限配慮した報道をすることを約束する合意書を交わし解決した。(山梨)
(2001.11.08 放送、2002.06.05 解決)
バラエティー番組出演者から 放送中止の訴え
「美容整形をテーマにしたバラエティー番組に、パニック症候群で通院している娘が出演することになったが、番組の予告を見て娘の病気への影響が心配になった。放送を中止してほしい」という両親からの訴えがあった。番組責任者と本人、両親が話し合った結果、放送局側が、本人や家族の気持ちを配慮して出演部分を全面的にカットすることを決め、解決した。(東京)
(2002.06.28 放送予定、06.26 解決)
「約束無視の放送」と情報番組に苦情
営業担当の会社員から「仕事を終えてからゲームセンターで遊んでいるところを撮影され、『顔は出さない』との約束を無視して放送された。自分は放送を見ていないが、得意先などで『放送に出ていた』などと言われ、仕事をサボって遊んでいるかのように受け取られ迷惑している」との苦情があった。本人が放送テープを確認したところ、本人が考えていたほどの明確な映像でなかったこと、局側が改めて迷惑をかけたことを謝罪する文書を出すことで解決した。(大阪)
(2002.04.26 放送、07.05 解決)
「不登校児ドキュメント」保護者からの苦情
「不登校になった小学校5年の娘が通っているフリースクールを取材したドキュメンタリー番組が放送された。スクール側は生徒の実名、顔などは出さないよう要求したが、放送では自分の娘だけが何の映像処理もされずに、悪いイメージで放送された。このため放送後、子供は登校しなくなってしまった」との苦情が保護者からあった。保護者と放送局の責任者が会い、局側が家族を傷つけたことを謝罪、今後、不登校問題を番組で継続的に取り上げて行くことを約束し解決した。(大阪)
(2002.05.31 放送、07.12 解決)
「レズビアンは怖い」発言でトーク番組に苦情
「男女のタレントが司会するトーク番組で、女性が”最近、私にレズ説があるの。女の子に誘われて行ったら、大変怖い思いをした”と発言、それを受けて男性が”怖いなー、そんな人おるで、この頃。ちょっと隠さなあかんのとちゃうの、あんなん”とレズを冒涜する発言をした」との苦情があった。当該局に連絡し対応を要請した結果、1月10日に当該局から、「性的マイノリティーの人権、心情に配慮が足りなかったことを認め、再放送に当たっては不適切な部分を削除することを約束し解決した」との報告があった。(大阪)
(2002.12.20 放送、2003.01.10 解決)
「バラエティー番組でプライバシーの侵害」との苦情
「6~7年前に19歳の息子が交通事故で死亡した。死んだ息子の恋人が、バラエティー番組の霊能企画に出演し、息子の写真、墓などの映像を映しながら、息子との関係、現在の気持ちなどを話した。この中で霊能者が『交通事故で死亡したのは親の愛情が足りなかったからだ』などと無責任なことを話した。この放送に妻が怒り、テレビ局に抗議した。放送に当たって放送局から何の連絡もなく家族のプライバシーが侵害された」との苦情があった。当該局に連絡し対応を要請した結果、2月5日に当該局から、「1月に同じ番組で謝罪放送を行い解決した」との連絡があった。
(2002.11.27 放送、2003.02.05 解決)
「トークバラエティー番組で名誉毀損」との苦情
「番組で作家募集をしていたので応募した。オーディションを受けて、自宅などを撮影された上で、11月28日に放送された。この放送はひどいもので、私の顔と部屋が映し出される中(3分)で、応募した短編の説明をしだすと、司会者らが”おたくだ””危ない”などと連呼し、自分を笑いものにした。当該テレビ局の担当者に会って抗議したが、司会者らの謝罪には応じられないということだった。作品を読んだ感想もなく、番組の中でただ袋叩きにされたようなもので、これは個人に対する中傷、侮辱であり人権侵害である」との苦情があった。
当該局に連絡し対応を要請、当事者間の話し合いが行われた結果、2月初めに当該局から「謝罪放送を実施し解決した」との連絡があった。(札幌)
(2002.11.27 放送、2003.02.05 解決)
「無断撮影・放送で名誉毀損」の苦情
昨年8月24日に放送された在阪テレビ局のバラエティー番組に対する大阪の主婦からの抗議は、今年3月に当該局が謝罪放送を実施し解決しました。
抗議の内容は「スーパーで買い物をして出てきたところを、女性アナウンサーに声をかけられたが、急いでいたので断った。このとき撮られた映像が、断りもなくバラエティー番組で放送され、『大阪のおばちゃんはこんなに怒っている』という音声とともに、アップにした顔に”怒りマーク”が付けられていた。放送局に抗議したところ、局は今年1月の検証番組で一方的に謝罪放送を行ったが、自分としては同じ番組での謝罪を要求しており納得できない」というものでした。
事務局から当該局に苦情の趣旨を伝え対応を要請した結果、この3月に当該番組で謝罪放送が行われ解決しました。今年度8件目の斡旋解決事案になりました。
(2002.08.24 放送、2003.03.25 解決)