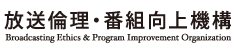第26号 喫茶店廃業報道
【委員会決定を受けての毎日放送の対応】
2005年10月に当該事案について委員会決定を受けた毎日放送は、3か月後の2006年1月16日にBRC宛に、「委員会決定後の当社の取り組みについて」という文書を提出した。
これは、NHKと日本民間放送連
盟が、BPOの発足にあたり基本合意書において「3委員会から指摘された放送倫理上の問題点については、当該放送局が改善策を含めた取組状況を報告し、放送倫理の向上を図る」と申し合わせたことに基づくもので、06年1
月17日の第108回BRCでこの毎日放送からの報告文書について意見を交わした。
委員からは、「このところ当該局の対応の仕方はよくなっている」「毎日放送も、かなり前向きに対応している」との意見が出ていた。
毎日放送の報告文書は以下の通り
2006年1月16日
放送と人権等権利に関する委員会
委員長 飽戸弘 殿
毎日放送
「喫茶店廃業報道」事案
委員会決定後の当社の取り組みについて
毎日放送では、2005年5月9日にニュース番組・VOICEの特集において、「憤懣本舗/嫌がらせの屋台、無神経な役所」を放送しました。この放送についてBRCでは「喫茶店廃業報道」事案として審理され、10月18日に委員会決定を
だされました。決定を受けた後の当社の対応や取り組みについて、ご報告いたします。
(1)委員会決定後の当社の対応について
◆申立て人に対しての謝罪
- 10月20日、申立人に謝罪文を郵送
◆委員会決定の主旨の放送
- 10月18日(火)「イブニング・ニュース」 <17:50~18:16放送 TBS発 全国ネット>内で44秒間、決定の主旨を放送
- 10月18日(火)「VOICE」<18:16~18:55放送 MBSローカル>内で1分13秒間、決定の主旨を放送
- 11月5日(土)「MBSマンスリーリポート」<05:30~05:45放送 MBSローカル>内で4分28秒間、決定の主旨を放送
◆委員会決定を受けて、当社のコメントを公表
- 委員会決定の内容を公表する記者会見の席で、出席した記者に当社のコメントを配布
◆視聴者など社外への告知
- 当社ホームページ「ちゃやまち広報室」に委員会決定の内容や社としての対応を掲載
◆番組審議会への報告
- 10月25日開催の第503回番組審議会において、広報室長、報道局長から委員会決定について報告
◆社内への告知
- 10月19日開催の全社局長会<当社の全常勤取締役、全常勤監査役、全ライン局長出席>において、広報室長から委員会決定へ至る経過と決定内容について報告
- 当社社報12月号<12月1日発行>に決定内容と対応を掲載
◆社長の訓示
- 1月4日の当社年賀式および当社社報1月号<1月1日発行>において、VOICEにおける報道がBRCに放送倫理違反と判断がなされたことに関し、社長から全社員に向け訓示
(2)再発防止のための取り組みについて
◆決定内容を報道局員に周知徹底
10月20日に緊急の報道局会を開催し、局員に対し委員会決定の内容を説明しました。指摘を受けた点を重く受け止め、報道の正確性を期するために、取材対象者に報道の意図を明示して、その弁明を聞くという報道の基本原則を
再確認すること、ならびに、いわゆる隠し撮りという取材手法が許されるのは、その目的が公共性・公益性を有するとともに、そうした取材が不可欠の場合に限定されるということをあらためて報道局員全員に周知徹底しました。
また、今後の報道活動において民放連の放送基準、報道指針を遵守することなど、放送倫理のいっそうの向上に努めるよう指示しました。
◆デスクによるチェック体制の強化
報道局内の部長、デスクが協議を重ね、10月31日のデスク会で、再発防止のために次の2点を確認し、チェック体制を強化することにしました。
- 今回の決定をふまえ、特集に限らずニュース番組の制作にあたっては、十分な取材がなされているか、また取材手法が妥当かなどを、毎夜、開催している取材予定会議の場でデスクが協議し、厳しくチェックすること
- なかでも今回の決定で指摘を受けた、いわゆる“隠し撮り”取材については、事前にその目的や内容の妥当性を複数のデスクが判断すること、また、取材後の編集や放送にあたっても同様に複数のデスクがチェックし、厳格に
判断すること
◆研修会の開催
12月16日、毎日放送本社に上智大学・田島泰彦教授を講師に招いて報道研修会を開催しました。
研修会には報道局員ら50余名が出席し、放送に求められる倫理とは何か、特に、いわゆる隠し撮り取材(無断録音・無
断撮影)という取材手法が報道倫理上、どのように位置づけられているかについて、英国BBCの倫理ガイドラインやわが国での過去の事例などをもとに講演をしていただき、報道局員らの認識を高めました。
今後も報道倫理に
関わるさまざまなテーマで適宜、報道研修会を開催し、取材、放送に関わるスタッフの人権や放送倫理に対する意識の向上を図っていきます。
2005年度 第27号 放送局対応
第27号 新ビジネス“うなずき屋”報道
【委員会決定を受けてのテレビ東京の対応】
2006年1月17日に委員会決定を受けたテレビ東京は、放送と人権等権利に関する委員会(BRC)宛に、3月20日「改善策と取り組み」などをまとめた文書を提出した。
これは、NHKと日本民間放送連盟が、BPOの発足にあたり基本合意書において「BPOの三委員会から指摘された放送倫理上の問題については、当該放送局が改善策を含めた取組状況を委員会に報告し、放送倫理の向上を図る」と申し合わせたことに基づくもので、4月の委員会でこの報告について意見を交わした。
この中で、テレビ東京が委員会決定で指摘された内容を、関係部局に周知徹底して伝えたこと、報道現場をはじめ、外部プロダクションを含む各セクションで研修会、勉強会を行って放送倫理の確立を改めて認識しあったことなどに対し、委員各位からその取り組みを評価し、この教訓を今後に是非生かして欲しいとの要望が出された。
テレビ東京の報告は以下の通り。
2006年3月20日
放送と人権等権利に関する委員会(BRC)
委員長 飽戸 弘 殿
「新ビジネス“うなずき屋”報道」BRC決定後の改善策の取り組み等について
2006年3月20日
株式会社 テレビ東京
「新ビジネス“うなずき屋”報道」事案について、2006年1月17日に貴委員会から審理結果の通知を受け、テレビ東京は、「決定で指摘された点を真摯に受け止め、今後より一層放送倫理を遵守した報道に努めて参ります。」とのコメントを発表し、ホームページ上にも掲載しました。
その後当社では下記の通り、放送での対応・改善策の取り組み等を実施致しましたのでご報告申し上げます。
記
I.BRC決定通知後の決定主旨等の放送
- 1月17日(火)17時~『速ホゥ!』で放送
- 1月17日(火)22時~『ガイアの夜明け』で放送
- 1月17日(火)23時~『ワールドビジネスサテライト』で放送
- 1月22日(日)6時20分~『みんなとてれと』で放送
- 2月19日(日)6時20分~『みんなとてれと』で、2月開催の放送番組審議会報告において、社内委員会「人権・放送倫理委員会」での模様等を紹介した。
II.決定文配布等社内周知
- 1月17日(火)決定文社内配布
- 1月24日(火)役員局長会報告
社長以下全役員、全局長が出席する会議において、決定内容を報告した。 - 1月26日(木)考査事例研修会報告
社内の制作・報道セクションを中心に、「考査事例」を教材にして放送倫理問題を研修する会において決定内容を周知した。 - 2月9日(木)人権・放送倫理委員会報告
放送倫理問題を中心に議論し、幅広く社内周知を図るために設置されている委員会。
制作・報道・スポーツをはじめ管理部門の委員も参加し、決定文を基にした意見交換 を行った。 - 社内報(2006年2月21日発行の2月号)に決定内容を掲載した。
III.2月13日(月)開催の第305回放送番組審議会で報告
IV.報道局における改善策の取り組み(局員・制作担当者への周知・徹底等)
- 『ガイアの夜明け』制作スタッフ(テレビ東京社員)に周知・徹底
1月19日に制作スタッフを招集し、報道局長より委員会決定の内容を説明するとともに、今後の取材および制作活動において、放送倫理の一層の向上に努めるように指示した。 - 報道局員に周知・徹底
2月10日に報道局員を招集し、委員会決定の内容を説明するとともに「テレビ東京報道倫理ガイドライン」の遵守を徹底した。また今後の取材および制作活動において、放送倫理の一層の向上に努めるように指示した。約70名の報道局員が出席し、「取材対象との関わり方」等について議論を深めた。 - 『ガイアの夜明け』外部制作プロダクションに周知・徹底
2月14日に、番組制作に携わる外部プロダクション20社33名のプロデューサー、ディレクターを招集し、委員会決定の内容を説明するとともに、今後の取材および制作活動において、放送倫理の一層の向上に努めるように指示した。また制作過程において、局のプロデューサーとプロダクションのプロデューサー・ディレクターとのコミュニケーションを緊密にし、再発防止に努めることを確認した。「番組構成上の問題」や「取材対象者の人権への配慮」などが 議論された。 - 勉強会の開催
BRCの右崎正博委員(独協大学法科大学院教授)を招き、委員会決定の内容と「放送と人権」についての報道勉強会を3月8日に開催した。当日は、報道局員にとどまらず編成・制作・制作会社など約70名が参加、質疑応答・意見交換が活発に行われた。
以上
2005年度 第28号 放送局対応
第28号 バラエティー番組における人格権侵害の訴え
【委員会決定を受けての関西テレビの対応】
2006年3月28日に委員会決定を受けた関西テレビは、BRC宛に06年6月13日に「決定後の対応と取り組み状況」をまとめた文書を提出した。
これは、NHKと日本民間放送連盟が、BPOの発足にあたり
基本合意書において「3委員会から指摘された放送倫理上の問題点については、当該放送局が改善策を含めた取り組み状況を報告し、放送倫理の向上を図る」と申し合わせたことに基づくもので、06年6月20日の第113回委
員会では、この関西テレビからの報告文書について意見を交わした。
各委員からは、BRCの委員会決定を受けた放送局に対する最近の総務省の動きを懸念する意見が相次いだ。
関西テレビの報告は以下の通り
2006年6月13日
放送と人権等権利に関する委員会
委員長 竹田 稔 様
関西テレビ放送株式会社
委員会決定後の対応と取組みについて
平成18年3月28日のBRC(放送と人権等権利に関する委員会)の勧告を受け、当社は下記の通りの対応と再発防止の取組みを行いましたので、ご報告します。
(A)勧告後の当社の対応について
1.申立人への謝罪
- 4月4日、申立人に制作局長と番組プロデューサー連名の謝罪文を郵送
2.視聴者等への告知
- 3月28日、委員会決定直後に当社ホームページにて、これまでの経緯と委員会決定の内容、今後は一層送倫理遵守に努める方針を掲載
- 3月28日、委員会決定後から視聴者情報部が窓口となり、視聴者からの電話やメールに対応(3月28日~4月6日:この件に関する電話7件、メール28件で内訳は苦情69%、激励その他31%)
- 3月28日、委員会決定後に夕方の全国ニュース(40秒)、ローカルニュース(1分20秒)で決定内容を放送
- 4月1日の当該番組「たかじん胸いっぱい」の中で番組の最後にテロップ画面でアナウンスコメントのお詫びを30秒間放送
- 4月30日、月1回放送の検証番組「月刊カンテレ批評」の冒頭で5分間の特集を放送。その中で制作局長が出演し、経緯及び今後の方針を説明
3.他のマスコミ各社への対応
- 3月28日、委員会決定直後のBRC委員長らの記者会見の席で、出席したマスコミ各社に当社のコメントを配布
- 3月28日、委員会決定後から総務部が窓口となり、マスコミ各社の問合せに対応
4.社内への告知
- 3月28日、委員会決定直後に緊急管理部長会を開き、総務局長から委員会決定について報告。全社員への周知徹底を図る
- 4月4日、5日に全社の部長会、局長会でも今回の経緯並びに決定内容が報告される
5.総務省近畿総合通信局への報告
- 3月28日、当社技術業務部長から委員会決定について報告。4月12日、技術業務部長と総務部長がこれまでの経緯を事情説明
6.番組審議会への報告
- 4月13日開催の第475回番組審議会において、制作局長、考査部長から委員会決定について報告
(B)再発防止に対する取組み
1.緊急制作局会、プロデューサー会議の開催
- 3月28日に緊急制作局会、プロデューサー会議を開き委員会決定の内容を説明し、今後は企画・編集段階から見直しを図り、再発防止に努めるよう指示
- 4月7日、制作局長が当該番組の制作プロダクション幹部に委員会決定の内容とともに再発防止への協力を要請
2.企画・編集のチェック体制の強化
- 3月29日より、制作部長と副部長が分担して企画書や収録番組の編集テープを取寄せ、番組のチェックをすることを決定
3.各種研修会の開催
- 4月12日、新入社員の研修会にて考査部長がこれまでの経緯とBRC決定のポイントを解説
- 5月18日、若手カメラマンと外部プロダクションの編集スタッフを対象に研修会を開催。今回の問題点を取り上げて、人権に配慮した番組作りを心掛けることを確認
- 6月2日、関西テレビの本社で上智大学の田島泰彦教授を講師に招いて、「放送と人権」をテーマに研修会を開催。外部プロダクションのスタッフや社員80人が参加。田島教授はBRCの設立時の背景や放送倫理と人権について
講演。講演後、バラエティ番組と人権に関するテーマで活発な議論が交わされた
4.制作マニュアルの作成
- 番組制作に携わる者が放送倫理を守り、他人の名誉やプライバシーに配慮した番組作りに努める心得を書いた小冊子を作成
以上
2006年度 第29号 放送局対応
若手政治家志望者からの訴え
委員会決定 第29号 – 2006年7月26日 放送局:日本テレビ
若手政治家志望者3人が、日本テレビが2005年11月に放送した報道番組について「我々が作った政党と個人の活動について誤解を与える表現と作為的な編集、演出が行われ、名誉が傷つけられた」と申し立てた事案。
2006年7月26日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第29号
申立人 小笠原 賢二 中野 壽人 近藤 勇次郎 3氏
被申立人 日本テレビ
「先端研」は、日本テレビの説明によると、ニュース離れが進む若年層をターゲットに、気になる「先端的なテーマ」を取り上げた報道局制作の深夜番組であり、05年4月から12月まで週に1回関東ローカル枠で放送された。
「政治家を志す若者たち」というテーマで放送された本件番組は、主に以下の4つのパートから成り立っている。
•元フリーターから当選した(東京の)中野区議
•自分たちで政党をつくった「日本公進党」の党首ら
•早稲田大学雄弁会の学生たち
•松下政経塾の塾生たち
今回申立てを行ったのは、04年10月に「日本公進党」を立ち上げたいずれも20歳代の党首・小笠原賢二、幹事長・中野壽人、幹事・近藤勇次郎の3氏で、「当該放送は、当方の活動について誤解を与える表現を使い、また作為的な編集や演出が行われた結果、我々の名誉が傷つけられた」としている。
申立人らは、当初05年12月に日本テレビ報道局長宛に公開質問状を送るなどして局側の説明を求めていたが、06年2月に担当プロデューサーと電話で話しあった後、書面による回答を求めていた。
被申立人の日本テレビは、06年4月に報道局担当プロデューサー名で「当該番組は取材で浮かび上がった事実をありのままに伝えたもので、事実を歪曲して編集していない。したがって、取材方法や編集作業において謝罪や訂正すべき点があるとは考えていない」と回答した。
申立人らは、この回答を不満として同年4月9日付けで「申立書」を本委員会に提出した。
目次
- Ⅰ. 申立てに至る経緯
- Ⅱ. 申立人の申立ての要旨
- Ⅲ. 被申立人の答弁の要旨
- IV. 委員会の判断
2006年10月13日 【委員会決定を受けての日本テレビの対応】
2008年度 第36号 放送局対応
第36号 高裁判決報道の公平・公正問題
【委員会決定を受けてのNHKの対応】
標記事案の委員会決定(6月10日)を受けて、NHKは9月3日放送人権委員会宛に「委員会決定に対するNHKの対応について」という文書を提出した。
NHKの報告は以下の通り
平成20年9月3日
BPO・放送と人権等権利に関する委員会御中
日本放送協会
「公平・公正に係る申し立てについての委員会決定」に対するNHKの対応について
平成20年6月10日、貴委員会は、平成19年1月29日の「ニュースウオッチ9」でのETV番組をめぐる控訴審判決報道について、「公平・公正を欠き、放送倫理違反があった」との判断を示しました。この決定に対するNHKの対応などに
ついて報告します。
NHKは、審理の中で「公平か公平でないかの判断は微妙な問題であり、より慎重に行われるべきだ」と繰り返し主張してきました。その理由は、決定で、公平・公正な裁判報道はこうあるべきだとの
一般的な枠組みが万一示された場合、今後の報道への影響が大きいとの危惧からです。
その点、今回の放送倫理違反という結論は、報道一般に適用されるものではなく、報道機関自身が当事者となっている民事事件に関する
裁判報道という非常に特殊なケースに限定したものとなっています。NHKとしては、この決定を真摯に受け止めています。
(1)勧告後のNHKの対応
NHKでは、決定を受け、「今回の決定を真摯に受け止めて、さら
に放送倫理の向上に努め、公共放送に対する期待に応えていきます」とのコメントを発表しました。
また当日午後7時からの「ニュース7」と9時からの「ニュースウオッチ9」で決定内容を放送し、その中で、申立人の記者会
見についても紹介しました。またラジオ第一放送でも、午後7時からの「NHKきょうのニュース」と午後10時からの「NHKジャーナル」で決定を伝えました。
なお、2日後の6月12日に出された最高裁判決の報道にあた
っては、公平・公正に十分に配慮しました。また一般の裁判報道の際にも、決定の趣旨をいかしていくよう対応しています。
(2)社内周知のための対応
放送現場への周知については、翌日の6月11日に、全国の
報道現場に、決定内容を記した報道局長名の文書を配布し、決定趣旨を周知するとともに、日々の取材・報道に際して、改めて公平・公正の原則を再確認するよう指示しました。
さらに放送関係の部局長で作る放送倫理委員
会(6月23日)、及び現場の担当者で作る放送倫理連絡会(6月27日)で、今回の決定について説明し、報道以外の関係者にも周知を図りました。
今後、職員の研修などの場でも今回の決定の趣旨を徹底していきたいと考えて
います。
以上報告します。
以上
2008年度 第37号 放送局対応
第37号 群馬・行政書士会幹部不起訴報道
【委員会決定を受けてのエフエム群馬の対応】
エフエム群馬の報告は以下の通り
平成20年9月25日
放送と人権等権利に関する委員会
委員長 竹田 稔 殿
株式会社エフエム群馬
代表取締役社長 小林洋右
「委員会決定」の取組状況について(ご報告)
拝啓 貴委員会のご清栄を衷心よりお慶び申し上げます。
弊社の「群馬・行政書士会幹部不起訴報道」の審理に際して、貴委員会には多大なご面倒をおかけし、改めてお詫び申し上げます。
弊社は、貴委員会
決定「放送倫理違反」見解を真摯に受け止め、全社をあげて改善策を推進しております。今回のご報告は、既にご報告した委員会決定直後の措置を含め、弊社のこれまでの改善策全体についてまとめたものです。
弊社
の改善策は、(1)「放送倫理違反」見解を受けたことの公開、(2)申立人との関係改善、(3)社内統制と社員教育の改善、の三点について行いました。
このうち、(3)社員教育改善のため、弊社の「報道・編集ハンドブック」を
策定しましたので、添付させていただきました。
このハンドブックについて、9月中に全社員と番組出演者等を対象にした研修会を開き、日常業務の改善に役立てる所存です。なお、本報告書は、委員会決定があった平成20年
7月1日を起点に時系列でまとめさせていただきました。
ご査収いただき、行き届かない事柄についてご指導をいただければ幸甚です。
敬具
■7/1(火)
放送と人権等委員会が委員会決定 「放送倫理違反」見解を公表
17:00~30 地元記者会見で発表 於:県政記者クラブ
小林社長・大崎報道渉外担当部長が説明
18:03~04 夕方番組、ニュースコー
ナーで報道
委員会決定の概略
19:55~20:00 通常番組を休止し、特別枠で報道
委員会決定の詳細
弊社が真摯に受け止める旨のコメント
申立人のコメント
20:55~21:00 通常番組を
休止し、特別枠で報道
内容は上記と同じ
■7/2(水)
9:10~50 社内説明会実施
社長より在局社員に「放送倫理違反」の説明
不在者に説明骨子をメールで配信
午前~午後 関係各所へ報告
広告代理店へ説明文書を発送
JFN、エフエ
ム東京へ電話とメールで報告
ホームページ「お知らせ欄」に掲載、以後1週間
委員会決定の全文書(個人名をカット)
当社が真摯に受け止める旨のコメント
申立人のコメント
申立人に挨拶訪問
社長と報道渉外担当部長が挨拶に訪問、懇談
申立人は友好的に応対してくれた
■7/7(月)
午後 申立人と県行政書士会幹部4人が弊社に挨拶訪問
会長、常務理事、事務局長、申立人
■7/8(火)
放送番組審議会に報告
顧問弁護士に委員会決定内容を説明.
■7/15(火)
社長が上京、BPO事務局を訪問、経過を報告
■7/28(月)
「報道・編集ハンドブック」作成を開始
社長指導で報道部が作業
■7/29(火)
関係者3名の社内処分「文書による厳重注意」
■9/5(金)
人事異動内示 9月22日発令予定
■9/8(月)
「報道・編集ハンドブック」完成
常務会で決定、社内LANで掲示
■9/11(木)
代理店会議開催
「放送倫理違反」の概略説明
本報告書を作成
■9/16(火)
総務部長がBPO事務局を訪問
本報告書を提出
■9/19(金)
9月定例取締役会開催
「放送倫理違反」の概略説明
■9/24(水)
「報道・編集ハンドブック」の全社研修会を実施
社員・番組出演者・業務委託者、計36名参加
以上
2008年度 第39号 放送局対応
第39号 徳島・土地改良区横領事件報道
【委員会決定を受けてのテレビ朝日の対応】
テレビ朝日の報告は以下の通り
2009年6月29日
放送倫理・番組向上機構 御中
株式会社 テレビ朝日
委員会決定後の対応と取り組みについて
当社番組「報道ステーション」の「徳島・土地改良区横領事件報道」事案について、2009年3月30日の放送倫理・番組向上機構 放送と人権等権利に関する委員会による委員会決定を受けて、当社は以下の対応と取り組みを行って
おりますので、ご報告いたします。
- 委員会決定後の対応について
3月30日の委員会決定を受けて、当社広報部は当日「委員会の勧告を真摯に受けとめ、放送倫理や人権に十分配慮をしてまいります」というコメントを発表しました。委員会決定の内容については、当社のコメントも交えて、当日夕方の「スーパーJチャンネル」と、委員会決定の当該番組である「報道ステーション」および翌日朝の「やじうまプラス」内「ANNニュース」で全国向けに放送したほか、4月5日の番組「はい
!テレビ朝日です」の中で放送しました。社内においては、委員会決定の当日以降、局長会をはじめ社内常設の番組審査や放送倫理にかかわる会議などで委員会決定の内容を報告しました。また、報道局においては局内の会議で詳
細な報告を行いました。4月14日には、顧問弁護士も交えて委員会決定について詳細に分析・検討する会議を開き、対応策の策定などの方針を確認しました。申立人には、4月16日に報道担当取締役が面会し、委員会決定の趣旨に沿
って、今後番組を編集・放送していく方針を説明したところ、申立人はそれを了承されました。社員の処分は4月21日付で行い、「裏づけ取材など不十分なまま放送にいたり、結果、放送倫理違反があったとしてBPOから勧告を受け
たことに対して」として、報道ステーション担当部長ら番組の担当者5名を減給1カ月、また「その管理監督責任を問う」として、報道局長と報道局ニュース情報センター長を譴責としました。当社放送番組審議会においては、4月17
日の第499回審議会で社長が委員会決定について報告しました。5月15日の第500回審議会では「報道情報系番組の『取材』のあり方、『情報』の取り扱いと放送倫理、人権の問題について」というテーマで審議が行われました。この
中では、委員から「ぜひ取材に関してはしっかりとやってもらいたい」「情報という危険なものの扱い方の伝承がなされているか。デスククラスが心をひきしめていかないといけない事態だ」などの意見が出されました。
さらに、6月4日の第76回テレビ朝日系列24社放送番組審議会委員代表者会議(大阪市で開催)においても前述のテーマで議論が行われました。出席委員からは「番組制作の現場で、経験の少ないスタッフによる放送倫理観が欠落して
いたことや、それを監督する立場の責任者のチェック機能が十分でなかったのが取材不足の原因ではないか」「ジャーナリストとして勉強する機会がどこまで保証されているのだろうか。余裕がない現場が危ない状況を生んでいると
思う」「テレビの映像と音声は一瞬にして消えるが、影響力が大きいだけに間違いを起こさないように謙虚であるべき」「取材を慎重に行い、事実の確認をきちんと行うことが重要だ。さらに事実を報道したとしても、視聴者がど
のような印象を持ったかが重要となる」などの意見が出されました。
- 再発防止に向けた取り組みについて
「報道ステーション」では、番組の責任者が全スタッフを集めて、委員会決定の内容と、取材の経緯や表現方法などを説明しました。委員会決定で指摘された問題点を重く受け止めて、検証報道に必要な十分な裏付け取材を今後も怠ることなく徹底的に実施するよう注意喚起を促すとともに、様々な意見交換を実施しました。また、幹部デスクとも委員会決定後に協議を重ね、放送人権委員会で審理されることに
なった問題点を再度整理し、今後は放送項目についてチームリーダーを決め、素材の確認をはじめナレーション原稿や表現方法など全体的な点検作業を徹底的に実施していく方針を確認しました。
報道局に、放送倫理の一層の徹底および危機管理情報の共有を図り、問題発生の事前防止に向けた施策を機動的に立案し、実施するための会議「報道局・危機管理プロジェクト」を設置しました。この会議では、まず「徳島・土地改良区横領事件報道」につ
いて、このような放送に至った原因の究明や、再発防止に向けた業務の改善方法などについて検討を行いました。
5月14日には当社に、放送人権委員会委員長代行で今回の委員会決定のとりまとめを担当した三宅弘弁護士を招いて、委員会決定の内容や問題点等について2時間以上にわたって説明を受ける研修会を実施しました。社員・社外スタッフなど約80人が参加し、番組スタッフなどから出された質問や疑問について三宅委員長代行から回答をいた
だき、委員会決定についての理解を深めるとともに、問題意識を持つことの重要性を再認識しました。
- 番組における具体的な改善策
1)検証報道を実施する際の裏付け取材の徹底。
検証報道に限らず、ニュース報道の根幹は十分な裏付け取材が必要なことは言うまでもありません。確認作業は一人では行わず、必ず複数人で一つ一つ疑問点を解消していきながら、十分な裏付け取材ができているか、最終的な確認作業をデスクと必ず行うことを徹底します。
2)安易で短絡的・拙速な報道の防止。
十分な裏付け取材ができなかった場合や、コンセプトが明確になっていない場合などは、拙速な報道を避けて当日の放送を見送るという決断をするよう努めます。
3)チームリーダーを決め確認作業を実施。
現在のニュース編成は、一つの項目に対して複数のディレクターが取材や原稿、編集などを分担して作業を実施するため、全体を統括する責任者はいるものの、細部まで完璧に把握できていないこともありました。これを改めて、チームリーダーを項目ごとに配置して責任体制
を明確にし、取材や編集などすべての過程において確認作業に当たらせることにします。
4)チェック体制の強化と節目ごとに確認作業を実施。
チームリーダーは1次的な確認作業を行いますが、進捗状況も含めて担当のデスクやプロデューサーがチームリーダーとともに節目節目で取材や編集など進捗状況をチェックして確認作業を行います。また、ナレーションでの表現方法なども含めて、適切かどうか確認を進めることとします。
5)定期的な勉強会と研修を実施し、再発防止を推進。
他番組や他局で起きたことも含めて、当該報道に関連した講師や人物を招いて勉強会や研修会を開催し、スタッフの意識を常に高めるように努めます。
以上、放送と人権等権利に関する委員会による委員会決定についての当社の対応と取り組みをご報告申し上げました。
以上
2009年度 第40号 放送局対応
第40号 保育園イモ畑の行政代執行をめぐる訴え
【委員会決定を受けてのTBSテレビの対応】
TBSテレビの報告は以下の通り
平成21年11月6日
BPO・放送と人権等権利に関する委員会 御中
(株)TBSテレビ
「保育園イモ畑の行政代執行を巡る訴えに関する委員会決定」に対する対応と取り組み
この度、当社番組「サンデージャポン」の「保育園イモ畑の行政代執行を巡る訴え」事案について、「放送倫理・番組向上機構(BPO)放送と人権等権利に関する委員会」による2009年8月7日の委員会決定を受けて、当社は以下の対応と取り組みを行っておりますので、ご報告いたします。
- 委員会決定後の対応
弊社では貴委員会の決定を受けて、「委員会の勧告の内容を真摯に受け止め、今後の番組作りに生かしてまいります」というコメントを公表しました。
また、決定内容については通知当日の『総力報道!THE NEWS』の中で全国向けに放送をしたほか、8月9日に当該番組である『サンデージャポン』の中でも放送しました。 - 社内での報告と周知
貴委員会による「決定」通知以降、社内では局長会をはじめ、放送倫理委員会(9月4日開催)などで内容を報告し、全社的に周知徹底を図るように確認しました。さらに第521回番組審議会(9月14日開催)、当社の放送及び当社が放送責任を負う番組の制作や取材過程等における人権侵害等について審議する第52回放送と人権特別委員会(9月25日開催)においても内容を報告し、委員の皆様からご意見を頂きました。 - 再発防止に向けた取り組みについて
(1) 『サンデージャポン』が所属する情報制作局では、現在の情報番組が直面する様々なテーマを盛り込んだ、情報番組に携わるスタッフ専用版の「情報番組ガイドライン」を作成しました。ガイドラインの中に今回の『サンデージャポン』の事例を掲載し、「情報バラエティ番組は、手法はバラエティでも伝える内容は事実であり、且つ正確に伝える番組でなければならない」旨を再確認しました。
このガイドラインをもとに8月末から9月初めにかけて勉強会を計4回にわたって実施し、情報制作局の社員・社外スタッフ約460人が参加しました。今回の事例を改めて振り返ると共に名誉毀損や人権問題に関する昨今の事例研究、取材や放送における社内でのチェック体制についての確認、加えて貴委員会からご指摘をいただいた「訂正放送」についても検証しました。(2) 『サンデージャポン』のスタッフ向けには個別勉強会を3ヶ月に1回実施します(既に1回実施)。社内外の問題事例を詳しく検証するほか、取材やVTR編集時などにおける問題点を研修したり、講師を招いて勉強会を開催することで、スタッフの意識を常に高めるように努めてまいります。
(3) 情報番組においては政治・経済・事件などを扱うことが多いことから、報道局との連携を一層強める体制を作りました。『サンデージャポン』では報道局で記者経験のあるプロデューサーが、取り上げる項目の選定から取材、編集に至る過程で入念なチェックを行うことに加え、報道局各部のデスクによる原稿チェックや弁護士によるVTR内容のリーガルチェックなどを実施しております。
そうすることでVTRにおける事実誤認をなくし、VTRを見た出演者が誤解を生じないように、また誤解に伴う発言をしないように配慮しております。(4) 出演者に対しては内容面の説明を手厚くするなど事前打ち合わせの時間を長めに取っておりますが、万が一出演者に不適切な発言が出た場合に備えて、サブで制作プロデューサー、番組プロデューサーと番組デスクが共同でチェックを行う体制を整えました。必要と判断すれば、番組内で速やかに訂正や補足説明を行うようにしております。
今回の「決定」を受けて、当社は放送局として今後も視聴者の皆様の信頼を損なわないように取材や制作を適正に行うため、情報制作局のみならず報道局などの制作現場と編成やコンプライアンス室などが連携していく所存です。
以上、貴委員会による委員会決定についての当社の対応と取り組みについて報告させていただきました。
以上
2009年度 第41号 放送局対応
割り箸事故・医療裁判判決報道
委員会決定 第43号 – 2009年10月30日 放送局:TBS
2008年2月、TBS『みのもんたの朝ズバ!』は、1999年に男児が割り箸を喉に刺して死亡したいわゆる「割り箸事故」の民事裁判判決を取り上げた。その内容について、男児の治療を担当した勤務医とその家族が、事実誤認と捏造ともいえる放送により医師の名誉が毀損され家族も精神的苦痛を受けたと申し立てた事案。
2009年10月30日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第41号
申 立 人 根本英樹、根本良美、根本美知子、根本晋一、根本美香穂
被申立人 株式会社 TBSテレビ
苦情の対象となった番組
『みのもんたの朝ズバッ!』における「8時またぎ」のコーナー
放送日時
2008年2月13日(水)午前7時30分過ぎ~
VTR部分 8分20秒
スタジオトーク部分 6分50秒
本決定の概要
本件申立ては、2008年2月13日放送の『みのもんたの朝ズバッ!』(以下「本
件放送」という)において、男児が綿菓子の割り箸を口にくわえたまま転倒し、のど
を貫いた割り箸の先端部分が脳にまで達した結果死亡した、いわゆる「割り箸事故」
で、その治療に関与した医師の責任の有無をめぐる民事裁判の判決内容の報道ならび
に論評が行われたが、その内容が当該医師の名誉と信用を毀損し、その家族に精神的
被害をもたらしたとしてTBSに対して謝罪放送等を求めたものである。
当委員会は、審理の結果、本件放送は、当該医師の名誉を毀損するものではなく、
また申立人ら家族の精神的圧迫感もその侵害が社会通念上許された限度を超えるとは
認められないが、放送内容及びその前提となる放送態勢において、民間放送連盟とN
HKが制定した『放送倫理基本綱領』における「報道は、事実を客観的かつ正確、公
平に伝え、真実に迫るために最善の努力を傾けなければならない」との定めに反する
など重大な放送倫理違反があると判断し、TBSに対してしかるべき措置をとること
を勧告する。
(決定の構成)
委員会決定は以下の構成をとっている。
Ⅰ.事案の内容と経緯
- 1.申立てに至る経緯
- 2.放送内容と問題点
- 3.申立人の申立ての要旨
- 4.被申立人(放送局)の答弁
Ⅱ.委員会の判断
- 1.事実の認定と判断
- 2.放送倫理上の問題および権利侵害の有無
Ⅲ 結論と措置
Ⅳ.審理経過
2010年1月12日 委員会決定を受けてのTBSの取組み
1998年度 第5号 放送局対応
第5号 其枝幼稚園報道
【委員会決定を受けてのNHKの対応】
被申立人のNHKは、「今回の決定では、『放送は取材した事実に基づいたもので、訂正放送の必要性までは認められない』としており、NHKの立場が基本的には受け入れられたものと認識している。しかし、取材の相手方に対して、より細やかな配慮を求められたことについては、その趣旨を真摯に受け止め、今後も放送倫理の徹底に努めていく考えです」とのコメントを出し、以下の番組で委員会決定の主旨を放送した。
10月26日 「ニュース7」で放送(全国)
ラジオニュース(全国)
11月 1日 「あなたの声に答えます」で放送(全国)
以上
2010年度 第46号
「大学病院教授からの訴え」事案
委員会決定 第46号 – 2011年2月8日 放送局:テレビ朝日・朝日放送
見解:放送倫理上問題あり
テレビ朝日・朝日放送の報道番組『サンデープロジェクト』で2010年2月に放送した「密着5年 隠蔽体質を変える~大学病院医師の孤独な闘い~」の特集に対して、大学病院教授が、自分が直接当事者ではなかった過去の出来事に関連して、事前の同意を得ることなく取材を強行されたことや番組で実名や取材映像を使用されたのは人格権の侵害だと訴えた事案。
2011年2月8日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第46号
- 申立人
- A
- 被申立人
- 株式会社テレビ朝日・朝日放送株式会社
- 苦情の対象となった番組
- 『サンデープロジェクト』
(毎週日曜日 午前10時~11時45分、2010年3月終了) - 放送日時
- 2010年2月28日(日)(番組の後半の特集 約34分)
「密着5年 隠蔽体質を変える~大学病院医師の孤独な闘い~」
本決定の概要
本件は、報道番組『サンデープロジェクト』の中の「密着5年 隠蔽体質を変える~大学病院医師の孤独な闘い~」と題する特集コーナーの後半部分で、1998年に金沢大学附属病院で起きた「患者の同意なき臨床試験」をめぐる裁判と大学病院側の対応等を取り上げたこと、および事前の同意を得ることなく「直撃取材」を行ったことに対して、この取材を受け、また番組で実名および取材映像を使用された金沢大学附属病院産婦人科学講座の教授である申立人が、人格権侵害等の違法と放送倫理違反を申し立てたものである。
放送と人権等権利に関する委員会(以下「委員会」という)は、結論として、本件取材には人格権侵害の違法性は認められないが、放送内容には、企画意図は理解できるものの、放送倫理上の問題および表現上の問題があると判断した。とりわけ問題となるのは、番組のインタビュー部分における申立人の扱いと、「患者の同意なき臨床試験」をめぐる裁判の紹介の仕方である。本件放送における申立人インタビュー部分の取り上げ方は、真実性の追求や反論の機会の確保とはほど遠いものであり、また、「患者の同意なき臨床試験」をめぐる裁判結果の紹介は、上訴審以降の経過を捨象し、その結果を誤り伝えたため、裁判所も患者が実験目的を主とした臨床試験の対象にされたと認定したかのような不正確なものになっているとの批判を免れない。これらについて委員会は、放送倫理上の問題があると判断した。
(決定の構成)
委員会決定は以下の構成をとっている。
I.事案の内容と経緯
- 1.申立てに至る経緯
- 2.放送内容の概要
- 3.申立人の申立ての要旨
- 4.被申立人(放送局)の答弁の要旨
II.委員会の判断
- 1.審理の対象
- 2.実名・映像の使用による人格権侵害
- 3.取材上の問題点
- 4.放送内容の問題点
III.結論と措置
IV.審理経過
2011年6月20日【委員会決定を受けてのテレビ朝日・朝日放送の取組み】
2011年7月4日【「委員会決定を受けての取り組み」に対する意見】
2010年度 第45号
「機能訓練士からの訴え」 事案
委員会決定 第45号 – 2010年9月16日 放送局:TBSテレビ
見解:問題なし
TBSの報道番組『報道特集NEXT』が2009年4月と11月に放送した車イスの少女の普通中学校入学をめぐる問題を扱った特集について、映像に登場した少女の機能訓練士が無断で訓練の映像を使用されたとして肖像権や名誉、財産権等の侵害を訴えた事案。
2010年9月16日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第45号
- 申立人
- (有)A
B
C - 被申立人
- 株式会社TBSテレビ
- 苦情の対象となった番組
- 『報道特集NEXT』
(毎週土曜日午後5時30分~6時50分) - 放送日時
- 2010年2月28日(日)(番組の後半の特集 約34分)
(1) 2009年4月11日
特集「車イスの少女が入学できない訳」19分20秒
(2) 2009年11月7日
特集「Dさん入学・・・豊かな教育」24分10秒
本決定の概要
TBSテレビ(以下「被申立人」という)は、報道番組『報道特集NEXT』において、2009年4月11日に特集「車イスの少女が入学できない訳」を、2009年11月7日に特集「Dさん入学・・・豊かな教育」を放送した。これらの番組は、普通小学校に通うことができた少女がなぜ普通中学校に通うことができないのかという企画意図に基づくものであったが、番組中、(有)A(以下「A」という)の代表者であるB氏、同社員であるC氏(以下三者をあわせて「申立人ら」という)が少女に機能訓練を行う映像が放送された。この映像は少女の両親が撮影したものであった。
申立人らは、4月11日の放送については、事前にB氏C氏両名の肖像を使用することについて被申立人が了解を得ておらず肖像権侵害にあたるとしたほか、申立人らの名誉、財産権(特許技術)、著作権、営業権を侵害したものと主張した。11月7日の放送については、放送前に被申立人から連絡があり一応の許諾を与えたものの、その後許諾を与えた前提に反する対応があったことから、結局、B氏C氏両名の肖像権、申立人らの名誉、財産権(特許技術)、著作権、営業権を侵害したものであり、いずれの放送も申立人らの活動を曲解させ、または、不法な説明があり、申立人らの活動を阻害するもので、申立人らの被申立人に対する善意を踏みにじるものであるとして、申立てに及んだ。
放送と人権等権利に関する委員会(以下「委員会」という)は審理の結果、以下の理由により、本件放送内容については名誉、肖像権等の権利侵害はなく、また、放送倫理違反にあたる点も認められないと判断した。
まず、B氏C氏両名の肖像の使用については、4月11日の放送については事後の承諾が与えられており、11月7日の放送については事前の承諾が与えられているので、いずれも肖像権の侵害があったとはいえない。また、放送において視聴者に申立人らの活動を曲解させるような内容や不法な説明があり、そのことによって申立人らの活動を阻害した事実は認められず、そのほか、申立人らとの対応のうえで、被申立人において申立人らの善意を踏みにじる行為があったとする点もこれを認めることができなかった。
ただし、被申立人においては肖像にかかわる権利処理について軽率なところがあり、その点において報道される側に対する配慮に欠けた部分があったと考えるので、この点については、今後の放送の糧として欲しい。
なお、財産権(特許技術)、営業権に関わる部分については、委員会の審理の対象とはならないので判断しない。
(決定の構成)
委員会決定は以下の構成をとっている。
I.事案の内容と経緯
- 1.申立てに至る経緯
- 2.放送内容の概要
- 3.申立人の申立ての要旨
- 4.被申立人(放送局)の答弁の要旨
II.委員会の判断
- 1.申立ての要旨(1)について
- 2.申立ての要旨(2)について
- 3.申立ての要旨(3)について
- 4.申立ての要旨(4)について
III.結論
IV.審理経過
2010年度 第44号
「上田・隣人トラブル殺人事件報道」
委員会決定 第44号 – 2010年8月5日 放送局:テレビ朝日
見解:放送倫理上問題あり(意見付記)
テレビ朝日は、2008年12月の『報道ステーション』において、長野県上田市で夫婦が殺害され隣家の男が逮捕された事件を特集で取り上げた。この放送について、遺族が、夫婦が長年にわたって加害者やその親族に嫌がらせをしてきたことが、殺害の動機を形成したかのような事実に反する内容だったとして、名誉毀損などを訴えた事案。
2010年8月5日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第44号
- 申立人
- A
- 被申立人
- 株式会社 テレビ朝日
- 苦情の対象となった番組
- 『報道ステーション』
(月~金 午後9時54分~11時10分)
特集「身近に潜む境界トラブルの悲劇 住宅地の惨劇はなぜ起きた」 - 放送日時
- 2008年12月23日(火)午後10時48分過ぎから約15分間
本決定の概要
テレビ朝日は、2008年12月23日放送の『報道ステーション』において、同年11月に長野県上田市で夫婦が殺害され、隣家の男が逮捕された事件を取り上げ、特集「身近に潜む境界トラブルの悲劇 住宅地の惨劇はなぜ起きた」(以下「本件放送」という)を放送した。
これに対して、申立人は、(1)本件放送において、申立人の両親である被害者夫妻が長年にわたって加害者やその親族に対して嫌がらせをしてきたことが加害者の殺害の動機を形成したかの真実に反する内容が放送されたことによって、被害者夫妻およびその子供である申立人自身の名誉が毀損され、あるいは申立人の被害者夫妻に対する敬愛追慕の情が侵害された、また、(2)本件放送が近隣住民から聴取した内容の真実性等に十分配慮することなくそのまま放送したことは、事実を正確に、かつ公平に報道すべきであるという放送倫理に違反すると主張して、放送内容の訂正と謝罪を求めて本件申立てを行った。
審理の結果、被害者夫妻が、自分の土地に加害者の車が入ることを嫌がって、加害者自宅から公道へ出るために通過する路地の屈曲箇所付近に障害物を置いて通行を妨害しようとした事実、また、事件当日、障害物を置いた上で、被害者(妻)が加害者の様子をうかがい、加害者を写真撮影しようとしていた事実が認められた。また、こうした被害者夫妻の行為が加害者による本件犯行の動機形成に影響したことは、加害者に対する刑事事件判決においても指摘されているところである。こうした認定に基づき、委員会は、これらの点に関する本件放送の報道内容は、主要な部分において真実であり、または真実と信じるにつき相当の理由があったといえ、申立人に対する名誉毀損に当たらず、その他の違法もないと判断する。したがって、訂正放送、謝罪放送はいずれも必要がない。
他方、委員会は、とりわけ本件放送が一般的な隣人トラブルにとどまらず殺人事件という深刻な犯罪を取り扱うものであったことを考慮すれば、(1)取材段階においては、少なくとも申立人ら遺族など被害者関係者と接触を試み、その言い分も聴取するなどの被害者保護の観点からの積極的姿勢が求められる場合であったにもかかわらず、そうした努力をしていなかった点において被害者に対する配慮に欠けるところがあり、また、(2)編集・放送段階においては、被害者夫妻が非常識であったといったイメージを与えかねない放送をする一方で、加害者の側の問題点には一切触れなかったため、被害者側への配慮に乏しく、公平性を欠く内容になっていることが否定できないものと認めた。
このように、本件放送は、取材や編集・放送の各段階において被害者夫妻および申立人ら遺族に対する配慮に欠ける点があったものと認められ、「放送倫理基本綱領」が「報道は、事実を客観的かつ正確、公平に伝え、真実に迫るために最善の努力を傾けなければならない」とし、民放連の報道指針が「事件の被害者に対し、節度をもった姿勢で接する」としていることに照らして、放送倫理上問題があると判断する。 したがって、委員会は、被申立人に対し、本決定の趣旨を放送するとともに、今後は、報道においてより正確性、公平性を確保するよう留意して真実を追求し、かつ被害者等の名誉と生活の平穏のいずれをも害することのないよう公平な取材・報道をするよう十分配慮することを要望する。
(決定の構成)
委員会決定は以下の構成をとっている。
I.事案の内容と経緯
- 1.申立てに至る経緯
- 2.放送内容の概要
- 3.申立人の申立ての要旨
- 4.被申立人の答弁の要旨
II.委員会の判断
- 1 苦情申立てが期限内に行われなかったことについて
- 2 申立人が名誉毀損等にあたると主張する事実
- 3 これらの事実についての検討
- 4 名誉毀損等の成否
- 5 放送倫理上の問題
- 6 小括
III.結論と措置
IV.審理経過
2010年11月4日【委員会決定を受けてのテレビ朝日の取組み】
2009年度 第43号
「拉致被害者家族からの訴え」事案
委員会決定 第43号 – 2010年3月10日 放送局:テレビ朝日
見解:放送倫理上問題あり(補足意見付記)
2009年4月放送のテレビ朝日『朝まで生テレビ!』において拉致問題に触れた番組司会者の発言をめぐって、「北朝鮮による拉致被害者家族連絡会」が「人の生死に関する安易な発言は名誉毀損やプライバシーの侵害以上に最も重大な人権侵害である」として申し立てた事案。
2010年3月10日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第44号
- 申立人
- 北朝鮮による拉致被害者家族連絡会(代表 飯塚繁雄)
- 被申立人
- 株式会社テレビ朝日
- 苦情の対象となった番組
- 『朝まで生テレビ!』
(毎月最終金曜日25時25分~28時25分) - 放送日時
- (1)2009年4月24日27時15分頃から約5分間
(2)2009年5月29日25時29分頃から約2分間
本決定の概要
テレビ朝日(以下「局」または「被申立人」という)の制作によるニュース討論番組『朝まで生テレビ!』は、2009年4月24日深夜、「激論 日本の安全保障と外交」とのテーマで、北朝鮮ミサイル問題を入り口に日本の安全保障や外交について各界専門家による約3時間にわたる議論を放送した。この中で司会者のジャーナリスト田原総一朗氏は拉致問題に触れ、横田めぐみさんと有本恵子さんの名前を挙げて「外務省も生きていないことは分かっている」と発言するとともに、拉致問題に関する言論が拉致被害者の生死に触れることをタブー視する閉塞状態に陥っていることを指摘し、そのような見方にとらわれた政府の方針を批判する趣旨の意見を展開した。「北朝鮮による拉致被害者家族連絡会」(以下、「家族会」という)は、田原氏のこのような発言は人の生死にかかわる安易な発言であって、家族の心情を傷つけ、名誉毀損やプライバシー侵害以上の最も重大な人権侵害であるとともに、政府の基本方針を批判し、誤まったメッセージを発したことによって救出運動を妨害し、ひいては拉致被害者の人命にもかかわる最も重大な人権侵害である等として、局に対し、田原氏の発言の撤回と謝罪、田原氏の司会者としての起用の見直しなどを求め、放送と人権等権利に関する委員会(以下「委員会」という)に救済を申し立てた。
委員会は、田原氏の発言について以下の通り判断した。番組中で田原氏が、生死の確証のない2人の拉致被害者について、実体的根拠を示すことなく「生きていない」と断定的に述べたことは、家族にとって耐え難い苦痛である。田原氏の発言が家族の心情を深く害し、強い不快の念を抱かせたものであることは疑いがない。拉致被害者の救出に全力で取り組んでいる家族の心情に対しあまりに配慮に欠ける表現であった点において不適切であった。
しかし、田原氏の発言全体について見れば、拉致問題についての言論が閉塞状況にあり、そのことが拉致問題の解決を妨げているとの認識のもとに、そのような状況を打開するためあえて批判と苦言を呈したという発言意図に照らせば、その発言が家族の心情を深く害し、強い不快の念を抱かせたものであったとしても、論評全体としては、言論の自由の範囲内にあるものとして許容されるべきである。異論が提起されることによって自らの立場が否定されたとの不快の念を抱く場合があったとしても、メディアの世界における自由な言論は保障されなければならない。田原氏の発言に関する局の責任としては、名前を特定した2人の拉致被害者について、根拠を示すことなく「生きていない」と断定し、被害者家族の心情を無視した不適切な発言に対する対応のあり方の問題に限られる。
局は番組終了後、田原氏からの事情聴取や局としての独自の取材によって上記のような事実が確認できなかったことを認め、二度にわたって謝罪しているから一応必要な措置を講じていると認められる。しかし、問題の深刻さを考えれば謝罪に関してはより迅速かつ適切な方法をとるべきであった。この点において放送倫理上の問題があったと判断し、報道に対する信頼が確保されるよう一層の努力を求めることとした。
(決定の構成)
委員会決定は以下の構成をとっている。
Ⅰ.事案の内容と経緯
- 1.申立てに至る経緯
- 2.放送内容の概要
- 3.申立人の申立ての要旨
- 4.被申立人の答弁の要旨
Ⅱ.委員会の判断
- 1.田原発言に対する評価
- 2.田原発言に対する局の対応と責任
Ⅲ 結論と措置
Ⅳ.審理経過
2010年6月9日【委員会決定を受けてのテレビ朝日の取組み】
2009年度 第42号
「派遣法・登録型導入報道」事案
委員会決定 第42号 – 2009年11月9日 放送局:テレビ朝日・朝日放送
見解:構成・表現に関し配慮を求む
テレビ朝日・朝日放送の共同制作による『サンデープロジェクト』は、2009年2月に2回にわたり特集「派遣法誕生」を放送した。この番組について、インタビュー取材を受けた元労働次官と経済学者らが、「質問と答えを勝手に切り貼りされ、局の都合の良い内容に捏造された」などとして名誉侵害を訴えた事案。
2009年11月9日 委員会決定
- 申立人
- 高梨 昌・関 英夫・木村 大樹
- 被申立人
- 株式会社テレビ朝日・朝日放送株式会社
- 苦情の対象となった番組
- 『サンデープロジェクト』
(毎週日曜日 午前10時~11時45分) - 放送日時
- 第1回 2009年2月1日(日)(番組後半の特集 約30分)
「派遣法誕生(前編)~“雇用破壊”の原点はこう作られた~」
第2回 2009年2月8日(日)(番組後半の特集 約31分)
「派遣法誕生(後編)~“生みの親”キーマン二人の証言~」
本決定の概要
テレビ朝日・朝日放送(以下「局」もしくは「被申立人」という)の共同制作による『サンデープロジェクト』は、2009年2月1日および8日の2回にわたり、特集「派遣法誕生」(以下「本件放送」という)を放送した。番組は、2008年秋以降の派遣切り・雇用不安の拡大を受け、いわゆる「労働者派遣法」の問題点、特に「登録型」に焦点を当て、その成立の過程を追った調査報道である。
この中で「労働者派遣法に登録型を導入するにあたり大きな力を発揮したのが、元労働次官と経済学者の2人であることが分かった」と、多くの関係者や本人のインタビューを積み重ねて伝えた。
この番組について元労働次官と経済学者ら(以下「申立人ら」という)が、「インタビューの質問と答えを勝手に切り貼りされ、局の都合の良い内容に捏造された。また、労働者派遣法に『登録型をひっそりと盛り込んだ』などの表現を多用し、2人が派遣切りなどの雇用不安を生みだした犯人だと攻撃された。これにより名誉を侵害されたので、局に対し訂正と謝罪の放送を求める」と、放送と人権等権利に関する委員会(以下「当委員会」という)に申し立てたものである。
この申立てを受け当委員会で審理した結果、本件放送には一部に申立人の社会的評価に影響をもたらす表現が含まれているが、申立人らが公人として労働者派遣法の制定に関わっていた以上、論評を受忍すべき範囲は一般人よりも広く認められるし、そもそも放送内容自体にはその重要な部分において事実に反するところがなく、現在の雇用不安に至る原因を探るという公共性の高い性格を有していることから、名誉毀損などの違法性はないとの見解に至った。
また、この調査報道番組を制作するに当たって、インタビュー証言の編集や放送表現に関し、なお配慮すべき点が幾つかあるものの、放送倫理上問題ありとまではいえないとの結論で当委員会は一致をみた。
(決定の構成)
委員会決定は以下の構成をとっている。
Ⅰ.事案の内容と経緯
- 1.申立てに至る経緯
- 2.放送内容の概要
- 3.申立人の申立ての要旨
- 4.被申立人の答弁の要旨
Ⅱ.委員会の判断
- 1.派遣法成立の経過と報道のあり方
- 2.事実の認定と判断
- 3.放送内容についての評価
Ⅲ 結論と措置
Ⅳ.審理経過
2009年度 第41号
割り箸事故・医療裁判判決報道
委員会決定 第41号 – 2009年10月30日 放送局:TBS
勧告:重大な放送倫理違反
2008年2月、TBS『みのもんたの朝ズバ!』は、1999年に男児が割り箸を喉に刺して死亡したいわゆる「割り箸事故」の民事裁判判決を取り上げた。その内容について、男児の治療を担当した勤務医とその家族が、事実誤認と捏造ともいえる放送により医師の名誉が毀損され家族も精神的苦痛を受けたと申し立てた事案。
2009年10月30日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第41号
- 申立人
- A、B、C、D、E
- 被申立人
- 株式会社 TBSテレビ
- 苦情の対象となった番組
- 『みのもんたの朝ズバッ!』における「8時またぎ」のコーナー
- 放送日時
- 2008年2月13日(水)午前7時30分過ぎ~
VTR部分 8分20秒
スタジオトーク部分 6分50秒
本決定の概要
本件申立ては、2008年2月13日放送の『みのもんたの朝ズバッ!』(以下「本件放送」という)において、男児が綿菓子の割り箸を口にくわえたまま転倒し、のどを貫いた割り箸の先端部分が脳にまで達した結果死亡した、いわゆる「割り箸事故」で、その治療に関与した医師の責任の有無をめぐる民事裁判の判決内容の報道ならびに論評が行われたが、その内容が当該医師の名誉と信用を毀損し、その家族に精神的被害をもたらしたとしてTBSに対して謝罪放送等を求めたものである。
当委員会は、審理の結果、本件放送は、当該医師の名誉を毀損するものではなく、また申立人ら家族の精神的圧迫感もその侵害が社会通念上許された限度を超えるとは認められないが、放送内容及びその前提となる放送態勢において、民間放送連盟とNHKが制定した『放送倫理基本綱領』における「報道は、事実を客観的かつ正確、公平に伝え、真実に迫るために最善の努力を傾けなければならない」との定めに反するなど重大な放送倫理違反があると判断し、TBSに対してしかるべき措置をとることを勧告する。
(決定の構成)
委員会決定は以下の構成をとっている。
Ⅰ.事案の内容と経緯
- 1.申立てに至る経緯
- 2.放送内容と問題点
- 3.申立人の申立ての要旨
- 4.被申立人(放送局)の答弁
Ⅱ.委員会の判断
- 1.事実の認定と判断
- 2.放送倫理上の問題および権利侵害の有無
Ⅲ 結論と措置
Ⅳ.審理経過
2010年1月12日【委員会決定を受けてのTBSの取組み】
2009年度 第40号
保育園イモ畑の行政代執行をめぐる訴え
委員会決定 第40号 – 2009年8月7日 放送局:TBSテレビ
勧告:重大な放送倫理違反(意見付記)
TBSの情報バラエティー番組『サンデージャポン』は2008年10月、大阪の保育園の野菜畑が道路建設のため行政代執行される様子を伝えた。この放送について、保育園理事が、あたかも保育園が代執行の当日に園児たちを現場に動員して並ばせたかのような事実に反する放送内容で名誉を毀損され、その後の訂正放送も不十分だったと申し立てた事案。
2009年8月7日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第40号
- 申立人
- A
- 被申立人
- 株式会社 TBSテレビ
- 苦情の対象となった番組
- 『サンデージャポン』
- 放送日時
- 2008年10月19日(日)=本放送
午前10時~11時24分(当該項目 計 約4分50秒)
同 年 11月2日(日)=訂正放送
午前10時~11時24分(終了間際の約37秒)
本決定の概要
本件申立ては、情報バラエティー番組『サンデージャポン』において、大阪府が高速道路建設のため、保育園用地に対して行った行政代執行の様子を報じた内容に事実と異なる点があり、またそれを前提としたスタジオトークによっても申立人の名誉が毀損されたとして、TBSテレビ(以下「TBS」という)に対し謝罪と訂正を求めるものである。申立人はあわせて、その後の訂正放送においても適切な訂正とお詫びがなされておらず、二度にわたって人権侵害を受けたとしている。
放送内容の誤りについては、大筋においてTBSも認めるところであるが、問題は、それがどのような経過と原因から生じたか、放送によって申立人の名誉その他の権利が侵害されたのか、また訂正放送が適切に行われたかどうかにあった。
放送と人権等権利に関する委員会(以下「当委員会」という)は、結論として、放送において使用したVTRは、故意に事実をねじ曲げたり虚偽の内容を報道したとまではいえないものの、編集上配慮されるべきことが守られず、明らかに視聴者を誤解させる構成があったほか、出演者がVTRの内容によって形成された誤った認識に基づく発言を行ったのを看過して、放送中、または放送直後に訂正する措置がまったくとられなかったことにより、申立人に対する社会的評価を低下させ、その名誉を毀損した疑いが強く、少なくとも申立人の名誉感情を侵害したものと認めた。TBS自身も、放送内容の問題性を認識し、後日訂正放送を行ったが、その訂正放送も不十分であり、申立人の意向に沿うものになっているとはいいがたい。本決定は、本件の放送内容及び放送態勢において「事実を報ずる」という点において重大な放送倫理違反があったとするものであり、当委員会としてはTBSがしかるべき措置をとることを求めるものである。
Ⅰ.事案の内容と経緯
- 1.申立てに至る経緯
- 2.放送内容の概要
- 3.申立人の申立ての要旨
- 4.被申立人(TBS)の答弁と実施措置
Ⅱ.委員会の判断
- 1.事実の認定
- 2.放送内容と放送態勢に対する評価
- 3.訂正放送の在り方
Ⅲ 結論
Ⅳ 審理経過
2009年11月6日【委員会決定を受けてのTBSテレビの取組み】
2008年度 第39号
徳島・土地改良区横領事件報道
委員会決定 第39号 – 2009年3月30日 放送局:テレビ朝日
勧告:重大な放送倫理違反(補足意見・少数意見付記)
徳島県で起きた土地改良区の横領事件を伝えた2007年7月のテレビ朝日『報道ステーション』をめぐって、全国土地改良事業団体連合会会長の野中広務氏が作為的な構成の報道内容により、名誉と信用を毀損されたとして訴えた事案。
2009年3月30日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第39号
- 申立人
- 野中 広務
- 被申立人
- 株式会社 テレビ朝日
- 対象番組
- 『報道ステーション』
「『土地改良区と補助金』6億円着服・・・60歳女の裏側」 - 放送日時
- 2008年7月23日(水)
午後9時54分~11時10分内 約7分
Ⅰ 申立てに至る経緯
- 1 苦情の対象となった番組
- 2 申立ての経緯
Ⅱ 申立人の申立ての要旨
- 1 名誉・信用の侵害
- 2 肖像権の侵害
- 3 放送局に要求すること
Ⅲ 被申立人の答弁の要旨
- 1 名誉・信用の侵害について
- 2 肖像権について
- 3 放送局への要求について
Ⅳ 委員会の判断
- 1 名誉権の侵害について
- 2 信用の毀損について
- 3 肖像権の侵害について
- 4 放送倫理違反について
- 5 結論と措置
2009年6月29日【委員会決定を受けてのテレビ朝日の取組み】
2008年度 第38号
広島県知事選裏金疑惑報道
委員会決定 第38号 – 2008年12月3日 放送局:中国放送
見解:ホームページでの当該報道の文字情報は放送と同視せず(意見付記)
1997年の広島県知事選挙において当時の知事の後援会組織等から裏金を受け取ったとの疑いを持たれ、中国放送のニュース番組で実名を報道された元県議会議員3名が、「事実無根の報道により大きな被害を受けた」として名誉権の侵害を訴えた事案。
2008年12月3日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第38号
- 申立人
- A
B
C - 被申立人
- 株式会社中国放送(RCC)
- 対象番組
- 『イブニングニュース広島』内
「特集 藤田県政の闇 知事選裏金疑惑」 - 放送日時
- ① 2006年11月30日放送 標題「メモの現職県議8人が判明」
② 2007年 2月20日放送 標題「メモの現職県議、残る2人も判明」
③ 2007年 2月28日放送 標題「藤田知事の元秘書が供述『宮本県
議に30万円渡した』~疑惑の現職県議は11人」
④ 2007年 4月10日放送 標題「県議会選挙ドキュメント~あの人
たちは何を語った?~」
Ⅰ.申立てに至る経緯
- (1)苦情の対象となった番組
- (2)申立ての経緯
Ⅱ.申立人の申立ての要旨
- (1)名誉権の侵害について
- (2)被った不利益
- (3)放送局への要求
Ⅲ.被申立人の答弁の要旨
- (1)名誉権の侵害について
- (2)交渉の経過について
- (3)インターネットでの報道について
Ⅳ.委員会の判断
- (1)第1の申立てについて
- (2)第2の申立てについて
- (3)結論
2008年度 第37号
群馬・行政書士会幹部不起訴報道
委員会決定 第37号 – 2008年7月1日 放送局:エフエム群馬
見解:放送倫理違反
申立人は2006年7月に暴行容疑で書類送検されたが、その後不起訴処分になった。エフエム群馬は2007年12月に県議会で取り上げられたこの問題を伝えたが、申立人は「何の取材も受けないまま真実でない放送をされ、名誉を傷つけられた」と申し立てた。
2008年7月1日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第37号
- 申立人
- A
- 被申立人
- エフエム群馬
- 対象番組
- エフエム群馬 夕方のニュース
- 放送日時
- 2007年12月12日
午後6時07分頃
1分10秒
申立てに至る経緯
民放ラジオ局であるエフエム群馬は、夕方の定時ニュースの一項目として、「群馬県行政書士会の総務部長が会員に暴行を加えてケガを負わせたとして、傷害の疑いで前橋地方検察庁に書類送検されていたことが分かりました」で始まり、同行政書士会の会員が県議会に総務部長らの処分を行うように陳情し、放送当日の県議会総務常任委員会で取りあげられたこと、総務部長は書類送検されて不起訴処分となっていること、また県では検察で不起訴処分になっていることから処分は行わないとしたことなどを伝えた(以下、「本件放送」という)。
本件放送に対し、申立人である総務部長は、事実関係が異なるうえ、自分になんらの取材をしないまま一方的な報道をされ、名誉を傷つけられたとして、2008年1月、エフエム群馬に対し、放送法4条に基づく訂正放送と謝罪を求めた。
これに対し、エフエム群馬は、本件放送は県議会での質疑応答の過程において明らかになった内容を伝えたものであって、重要事項についての事実確認を行った上で報道しており、真実でない事項の放送はしておらず、訂正放送などに応じることはできないと反論した。その後、双方の直接の交渉はなされないまま、2008年2月、申立人から当委員会に対し「申立書」が提出され、3月の委員会で審理入りを決定した。
目次
- Ⅰ. 申立てに至る経緯
- Ⅱ. 申立人の申立ての要旨
- Ⅲ. 被申立人の答弁の要旨
- IV. 委員会の判断
2008年9月25日【委員会決定を受けてのエフエム群馬の対応】
2008年度 第36号
高裁判決報道の公平・公正問題
委員会決定 第36号 – 2008年6月10日 放送局:NHK
見解:放送倫理違反
「戦争と女性への暴力」日本ネットワークが申し立てた事案。NHKは2007年1月の『ニュースウオッチ9』において、申立人らとNHKが争ったETV2001シリーズ『戦争をどう裁くか』に関する高裁判決を伝えたが、申立人は「当事者としてのNHKの言い分」と「報道機関としての報道」を峻別せずに報道したことは公平原則に照らして到底許されるものではない、また公平原則を逸脱した部分は正確な報道を行うという放送倫理に違反すると申し立てた。
2008年6月10日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第36号
- 申立人
- 「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク
- 被申立人
- NHK
- 対象番組
- NHK制作の報道番組「ニュースウオッチ9」
- 放送日時
- 2007年1月29日
NHK総合テレビ 午後9時00分~
申立てに至る経緯
2001年にNHKが、教育テレビで放送した「戦争をどう裁くか」というシリーズの番組をめぐって、取材を受けた民間の団体「戦争と女性への暴力」日本ネットワークが「事前の説明と異なる不本意な番組を放送された」として訴えていた裁判で、NHKは、2007年1月29日、東京高等裁判所でなされた判決について、その概要やこれに関連する事項について、次のとおり放送した。
「東京高等裁判所の南敏文裁判長は『番組編集の自由は、憲法上、尊重すべき権利で、不当に制限されてはならないが、今回の番組は、取材を受けた団体への事前の説明とかけ離れたものになって、期待と信頼に反した。放送前に十分な説明もしていなかった』と指摘しました。そして『NHKの当時の幹部が、国会議員から一般論として公正・中立にと言われたことなどを、必要以上に重く受け止め、その考えを推し量って、番組を編集し直すよう指示したもので、編集権を乱用した責任は重い』と判断し、NHKに200万円の賠償を命じました。」と判決内容を紹介したあと、「判決についてNHKは『不当な判決であり、直ちに上告した。判決は、番組編集の自由を極度に制約するもので、到底受け入れられない』としています。」と被申立人自身の見解を紹介し、「今日の判決の中で、東京高等裁判所は、この番組をめぐって、朝日新聞が政治家の圧力で改変されたと報道したことについて、『国会議員が具体的に番組に介入したとは認められない』と述べました。」とのコメントの後に、朝日新聞で被申立人に圧力をかけたと指摘された本人である安倍晋三内閣総理大臣と中川昭一政務調査会長(いずれも本件放送当時。以下同じ。)の、政治的圧力をかけた事実はなかったことがはっきりした旨のコメントを放送した。
この放送に対して、申立人らは、「上記ニュース内容は『当事者としてのNHKの言い分』と『報道機関としての報道』を峻別せずに報道している。このことは、公平原則に照らして到底許されるものではない。また、公平原則を逸脱した部分は、正確な報道を行うという放送倫理にも違反している」として2007年4月、被申立人に対して抗議・要求書を送付し訂正放送と謝罪を求めた。
これに対し被申立人は、「この報道は、前半部分で、当日の判決の内容とNHKのコメントを伝えた上で、後半部分で、この判決に関連して一昨年1月の朝日新聞の記事をめぐる朝日新聞社と自民党との問題について、安倍氏と中川氏のコメントを交えて伝えたもので、何ら問題はないと考える」と反論し、訂正放送・謝罪には応じられない旨回答した。
その後、双方の直接の交渉はなされないまま、2008年1月、申立人らから本委員会に対して「申立書」が提出され、本委員会は、2月の委員会で審理入りを決定した。
なお、政治家の介入があったか否かの点に関する高裁判決の内容は、次のとおりである。
「一審原告らは、政治家等が本件番組に対して直接指示をし介入したと主張するが、上記面談の際、政治家が一般論として述べた以上に本件番組に関して具体的な話や示唆をしたことまでは、証人松尾及び証人野島の各証言によってもこれを認めるに足りず、他に認めるに足りる証拠はない。」
(注:証人松尾・・・NHK 放送総局長 松尾 武 氏)
(注:証人野島・・・NHK 総合企画室担当局長 野島直樹 氏)
(いずれも2001年当時)
目次
- Ⅰ. 申立てに至る経緯
- Ⅱ. 申立人らの申立ての要旨
- Ⅲ. 被申立人の答弁の要旨
- IV. 委員会の判断
2008年9月3日【委員会決定を受けてのNHKの対応】
2007年度 第35号
“グリーンピア南紀”再生事業の報道
委員会決定 第35号 – 2007年12月4日 放送局:読売テレビ
見解:問題なし
和歌山県にある大規模保養施設の再生事業を請け負った人物が、読売テレビの報道番組『ウェークアップ!プラス』(2007年5月と6月放送)で事実と異なる報道がされ、名誉が著しく傷つけられ、取材・放送によりプライバシーが侵害されたと申し立てた事案。
2007年12月4日 委員会決定
- 申立人
- A
- 被申立人
- 読売テレビ
- 対象番組
- 読売テレビ 報道番組「ウェークアップ!ぷらす」
- 放送日時
- 2007年5月26日 午前8時から午前9時25分内
2007年6月2日 午前8時から午前9時25分内
申立てに至る経緯
本件放送は、旧年金福祉事業団が設置した大規模年金保養施設「グリーンピア南紀」の払い下げを受けた和歌山県那智勝浦町と、その跡地の再開発事業を請け負ったBという会社の契約を巡る不明瞭且つ不透明な経緯を指摘し、問題提起する内容となっている。
被申立人読売テレビは、毎週土曜日の「ウェークアップ!ぷらす」で、4月21日、5月26日、6月2日の3回にわたり、このグリーンピア南紀再生事業に関する追跡報道を行った。
Bのオーナーである申立人A氏は、これら番組のうち、上記 I の(1)、(2)についてプライバシーの侵害、名誉毀損があったと訴え、被申立人に謝罪・訂正を求め、話し合ったが決着がつかず、BRCに対し権利侵害を申立てた。
目次
- Ⅰ. 申立てに至る経緯
- Ⅱ. 申立人らの申立ての要旨
- Ⅲ. 被申立人の答弁の要旨
- IV. 委員会の判断
2007年度 第34号
部落解放同盟大阪府連幹部からの訴え
委員会決定 第34号 – 2007年11月12日 放送局:毎日放送
見解:表現のあり方等について要望
毎日放送の報道番組『VOICE』は2006年11月、大阪市の“ヤミ補助金問題”を取り上げた。申立人は、報道内容に行き過ぎた演出があり名誉を毀損されたとして申し立てた。
2007年11月12日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第34号
- 申立人
- A、B
- 被申立人
- 毎日放送
- 対象番組
- 毎日放送の報道番組「VOICE」
- 放送日時
- 2006年11月20日午後6時36分から4分40秒間
申立てに至る経緯
毎日放送は、2006年11月20日の報道番組「VOICE」(関西ローカル)の中で、「大阪市の民間社会福祉施設等に対する償還金補助」を取り上げ、「予算計上しないまま支給しているのは“ヤミ補助金”の疑いがある」と伝え、また、番組内では、当該補助金の支給を受けていた法人は約30あり、この内8法人は部落解放同盟の幹部らが理事を務めていることなどを、該当する2施設の映像などとともに放送した。
この番組に対し、部落解放同盟大阪府連のA書記長らから毎日放送に「抗議する」との申し入れがあり、12月7日A氏らが毎日放送を訪れ、口頭で抗議した。
抗議内容は、「償還金補助は大阪市の制度であり、“ヤミ”補助金ではない」「部落解放同盟関連法人だけが対象ではないのに、意図的に部落解放同盟を叩いている」「年間返済金の『2倍』の補助金が支払われていたというのは事実誤認」など。
これに対し、毎日放送は12月20日付け文書で次のように回答した。
「当該補助金は予算計上されておらず、不透明・不適切であり、“ヤミ補助金”という表現は不適切ではない」「部落解放同盟関連法人だけに限定していないことを表現したつもりだが、誤解を招いたことは本意ではない」「04年度に当該施設に2年分の補助金が入金されたのは事実。そうなったのは市側の事務手続きの遅延で2年分が同一年度に支払われたと説明しており、報道内容は事実誤認ではない」
この後、3月14日付けで部落解放同盟大阪府連のA書記長から毎日放送(山本社長宛)に「06年11月20日放送の『VOICE』についての再質問と要請」という文書が送られ、「部落解放同盟を殊更に強調していないか」「社会福祉法人側や部落解放同盟に問題があったのか」「部落解放同盟の支部長や府連書記長の肩書きを報道する必要があったのか」など8項目について質している。これに対し、毎日放送は4月3日付けでA氏宛に「再回答書」を送り、項目別に答えるとともに、「大阪市の公金支出の問題点を指摘した本件報道は、その目的の公益性からみても正当なものだ」としている。
この毎日放送の「再回答」を受けて、A氏らは「毎日放送に対し謝罪と『VOICE』の報道によって広がった誤ったイメージの是正を求めていたが、その前段階である見解に大きな違いが存在しており、このままでは私達の求めていることが理解されない」として、局側との交渉をやめ、6月11日付けでBRCに申立てた。
目次
- Ⅰ. 申立てに至る経緯
- Ⅱ. 申立ての要旨
- Ⅲ. 答弁の要旨
- IV. 委員会の判断
2007年度 第33号
広島ドッグパーク関連報道
見解:問題なし
大阪の動物愛護団体の代表が、2006年11月から12月にかけて放送された朝日放送の報道番組『ムーヴ!』で、犬たちを救済する活動が、偏見や憶測によってあたかも募金目当てであるかのように放送され、名誉を毀損されたと申し立てた事案。
2007年8月3日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第33号
- 申立人
- A(動物愛護団体B代表)
- 被申立人
- 朝日放送
- 対象番組
- 朝日放送 ニュース情報番組「ムーブ!」(ローカル)
- 放送日時
- 次の(1)から(11)までの日における午後3時49分から午後5時54分内
(1)2006年11月27日
(2)2006年11月28日
(3)2006年11月29日
(4)2006年12月4日
(5)2006年12月6日
(6)2006年12月11日
(7)2006年12月12日
(8)2006年12月18日
(9)2006年12月20日
(10)2006年12月21日
(11)2006年12月28日
申立てに至る経緯
本件番組は、毎週月曜日から金曜日までの午後3時49分から午後5時54分まで放送される、被申立人の報道局ニュース情報センター制作の「ムーブ!」において、上記(1)から(11)までの各時間帯で放送されたものである。
番組内容は、2003年4月に開園した犬のテーマパーク「ひろしまドッグぱーく」が経営不振に陥って2005年6月に閉園したところ、多数の犬が放置されていたので、2006年9月に、申立人が代表である大阪の動物愛護団体Bが放置犬の救助に乗り出したことについての一連の追跡報道である。Bは、ホームページを使って全国に放置犬の引き取り手を探し、寄付を募ったが、このことはマスコミによって全国的に大きく報道された。このため、集まった寄付金の額は、2006年10月25日のホームページ上で5400万円と公表され、また、放置犬の救出のために全国から延べ6000人以上のボランティアが参加した。
しかしその後、参加したボランティアや他の動物愛護団体から「犬の扱い方がおかしい」「寄付されたお金や物資の使い方に疑問がある」などの情報が被申立人の番組である「ムーブ!」宛に寄せられた。
「ムーブ!」では、Bにおいて多額の寄付金が残っているのに「医療費が足らない」と言って支援を呼びかけていたと判断して、申立人に対し、その収支などを明らかにするように取材・放送の過程で求めた。しかし、申立人はその内容を明らかにしないことから、被申立人の番組「ムーブ!」において、申立人が代表であるBの募金と活動実態が整合しているかを検証したものである。
これに対し、申立人は、被申立人の番組「ムーブ!」における上記(1)から(11)までの番組は、いずれも一方的な偏見報道及び憶測放送と恣意的な内容の連続的放送であるとして、2007年1月5日付で「申立書」をBRCに提出した。
これに先立ち、Bは、2006年12月7日付で、被申立人及び朝日放送番組審議会に対し、「番組に対する苦情申立書」を提出し、上記(1)から(5)までの一連の報道は、B及び申立人に対する名誉毀損その他の重大な人権侵害等権利侵害を含む内容であり、今後も同様の姿勢により継続されるならばさらに侵害されるおそれがあるので、今後の放送によりB及び申立人の人権等が侵害されることのないよう、また過去の放送による被害の回復のため謝罪と訂正放送を求めて、苦情申立てを行った。また、Bは、2006年12月11日に、被申立人報道局ニュース情報センター「ムーブ!」広島ドッグパーク問題取材班宛に「朝日放送に対する質問状」を送付し、上記(1)の放送番組に対する10項目の質問をした。
これに対し、被申立人は、上記苦情申立書は、回答を求めるものではなく、番組内容の検証など番組に対する要望であり、この要望については、報道局内で番組を検証することとして放送を続けた。また、上記質問状については、被申立人は、2006年12月15日付でBに対し、回答を送付し、対応に問題はないものと考えていることを伝えた。
目次
- Ⅰ. 申立てに至る経緯
- Ⅱ. 申立ての要旨
- Ⅲ. 答弁の要旨
- IV. 委員会の判断
2007年度 第32号
ラ・テ欄表記等に対する訴え
委員会決定 第32号 – 2007年6月26日 放送局:テレビ朝日
見解:適正なラ・テ欄表記を要望
2007年2月放送のテレビ朝日のバラエティー番組を紹介する新聞のラジオ・テレビ欄の表現について、外国人の女性が、家庭の事情を公表され名誉・プライバシーの侵害を受けたと訴えた事案。
2007年6月26日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第32号
- 申立人
- 北海道在住のセラピスト
- 被申立人
- テレビ朝日
- 対象番組
- テレビ朝日 バラエティー番組『銭形金太郎』
- 放送日時
- 2007年2月7日午後8時~8時54分(テレビ朝日系列で全国放送)
申立てに至る経緯
被申立人であるテレビ朝日は、2月7日放送のバラエティー番組「銭形金太郎」で、申立人であるルーマニア人女性のセラピストが、北海道の自然の中で家族と楽しく暮らしているという生活ぶりを放送した。
この放送に対し、申立人は「新聞のラジオ・テレビ欄(以下「ラ・テ欄」という)に『バツイチ子連れ美女の……』等の表現で家庭の事情を公表され、名誉・プライバシーの侵害を受け、また、放送された内容は、当初の企画意図の説明の趣旨と違っており、放送倫理に違反する」と放送局に苦情を訴えた。
これに対し被申立人は「前夫との離婚について番組で紹介することは、事前に了承を得ている。放送の企画説明と放送内容は違っておらず一貫している」と反論した。
話し合いは数回にわたって行われたが決着がつかず、2月23日申立人から本委員会に申立書が提出された。
目次
- Ⅰ. 申立てに至る経緯
- Ⅱ. 申立人の申立ての要旨
- Ⅲ. 被申立人の答弁の要旨
- IV. 委員会の判断
2007年度 第31号
エステ店医師法違反事件報道
委員会決定 第31号 – 2007年6月26日 放送局:日本テレビ
見解:放送倫理違反
エステ店経営者が医師法違反で書類送検された事件を伝えた2007年2月の日本テレビの報道について、経営者が「盗み撮りした映像が使われ、まるで極悪人のように報道された。名誉も毀損されプライバシーも侵害された」と訴えた事案。
2007年6月26日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第31号
- 申立人
- 東京都町田市在住のエステ店経営者
- 被申立人
- 日本テレビ
- 対象番組
- 日本テレビのニュース番組
- 放送日時
- 2007年2月7日「NNNニュースD」午前11時30分から放送(関東ローカル、45秒)
「NNN Newsリアルタイム」午後4時50分から放送(関東ローカル、2分)
「NEWS ZERO」午後10時54分から放送(全国ネット、3分)
申立てに至る経緯
申立人は、東京都町田市所在のエステ店を経営しているが、2006年10月31日町田警察署から医師法違反容疑で家宅捜索を受け、2007年2月6日同容疑で書類送検された。
日本テレビは、翌2月7日3回にわたってこの事件を「エステ店経営者が医師法違反容疑で書類送検」と放送したが、その放送内容について申立人は「盗み撮りした映像を使ってまるで極悪人のように報道された。名誉も毀損され、プライバシーも侵害された」と日本テレビ側に抗議した。
その後、申立人は「文書での回答要求も断られた。ラチが明かない」として2月15日付でBRCに「申立書」を送付し、謝罪放送、文書での謝罪等を求めている。
これに対し、被申立人の日本テレビは「本件報道は、申立人が医師法違反で摘発され、書類送検された事実を誤りなく伝えたものだ」と主張している。
目次
- Ⅰ. 申立てに至る経緯
- Ⅱ. 申立人の申立ての要旨
- Ⅲ. 被申立人の答弁の要旨
- IV. 委員会の判断
2007年8月28日 【委員会決定を受けての日本テレビの対応】
2006年度 第30号
民主党代表選挙の論評問題
委員会決定 第30号 – 2006年9月13日 放送局:テレビ朝日
見解:問題なし
テレビ朝日の『報道ステーション』は2006年4月に民主党代表選挙に関する報道をした。
これに対して民主党の衆議院議員2人が「政治評論家によって虚偽の事実を摘示され、著しく名誉を毀損された」と申し立てた。
2006年9月13日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第30号
- 申立人
- 衆議院議員 仙谷由人 衆議院議員 枝野幸男
- 被申立人
- テレビ朝日
- 苦情の対象となった番組
- テレビ朝日 報道ニュース番組『報道ステーション』
- 放送日時
- 2006年4月4日 午後9時54分~11時10分
4月5日 午後9時54分~11時10分
申立てに至る経緯
被申立人テレビ朝日は、4月4日、5日の「報道ステーション」で、民主党代表選挙に関して報道したが、放送後に仙谷申立人側から、「政治評論家によって、虚偽の事実を摘示され、著しく名誉を毀損された。訂正放送か書面での謝罪を求める」と電話で抗議があった。その後、被申立人と仙谷申立人の間で3回にわたり話し合いが行われたが決着がつかず、5月23日仙谷申立人と枝野申立人が、連名で放送人権委員会に審理の申立てを行った。
これまでの双方の話し合いでは、申立人らは、「政治的な謀略的筋書きで一方的に放送し、裏づけ取材なく虚偽の報道をした」などと主張したのに対し、被申立人は「真実ないし真実と信じるに足る相当な理由がある事実に基づいて論評を行ったものだ」と反論した。当委員会は、当該番組を視聴した上で、6月の委員会で審理入りを決定した。
目次
- Ⅰ. 申立てに至る経緯
- Ⅱ. 申立人の申立ての要旨
- Ⅲ. 被申立人の答弁の要旨
- IV. 委員会の判断
2006年度 第29号
若手政治家志望者からの訴え
委員会決定 第29号 – 2006年7月26日 放送局:日本テレビ
見解:迅速・丁寧な対応を要望
若手政治家志望者3人が、日本テレビが2005年11月に放送した報道番組について「我々が作った政党と個人の活動について誤解を与える表現と作為的な編集、演出が行われ、名誉が傷つけられた」と申し立てた事案。
2006年7月26日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第29号
- 申立人
- A、B、C
- 被申立人
- 日本テレビ
- 苦情の対象となった番組
- 日本テレビ 報道番組「先端研」
- 放送日時
- 2005年11月22日 午前1時45分から約30分間放送
申立てに至る経緯
「先端研」は、日本テレビの説明によると、ニュース離れが進む若年層をターゲットに、気になる「先端的なテーマ」を取り上げた報道局制作の深夜番組であり、05年4月から12月まで週に1回関東ローカル枠で放送された。
「政治家を志す若者たち」というテーマで放送された本件番組は、主に以下の4つのパートから成り立っている。
•元フリーターから当選した(東京の)中野区議
•自分たちで政党をつくった「日本公進党」の党首ら
•早稲田大学雄弁会の学生たち
•松下政経塾の塾生たち
今回申立てを行ったのは、04年10月に「日本公進党」を立ち上げたいずれも20歳代の党首・A、幹事長・B、幹事・Cの3氏で、「当該放送は、当方の活動について誤解を与える表現を使い、また作為的な編集や演出が行われた結果、我々の名誉が傷つけられた」としている。
申立人らは、当初05年12月に日本テレビ報道局長宛に公開質問状を送るなどして局側の説明を求めていたが、06年2月に担当プロデューサーと電話で話しあった後、書面による回答を求めていた。
被申立人の日本テレビは、06年4月に報道局担当プロデューサー名で「当該番組は取材で浮かび上がった事実をありのままに伝えたもので、事実を歪曲して編集していない。したがって、取材方法や編集作業において謝罪や訂正すべき点があるとは考えていない」と回答した。
申立人らは、この回答を不満として同年4月9日付けで「申立書」を本委員会に提出した。
目次
- Ⅰ. 申立てに至る経緯
- Ⅱ. 申立人の申立ての要旨
- Ⅲ. 被申立人の答弁の要旨
- IV. 委員会の判断
2006年10月13日 【委員会決定を受けての日本テレビの対応】
2005年度 第28号
バラエティー番組における人格権侵害の訴え
委員会決定 第28号 – 2006年3月28日 放送局:関西テレビ
勧告:人権侵害
東京の男性が、2005年6月と7月に関西テレビで放送されたバラエティー番組『たかじん胸いっぱい』における元妻の発言によって、名誉・プライバシーを侵害されたと申し立てた事案。
2006年3月28日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第28号
- 申立人
- A
- 被申立人
- 関西テレビ
- 苦情の対象となった番組
- 関西テレビ トークバラエティー番組「たかじん胸いっぱい」
- 放送日時
- (1) 2005年6月25日 午後0時~午後1時
サブタイトル「知られざる結婚生活5か月に迫る!!」
「検証 B 離婚寸前報道の真実とウソ!!」
(2) 2005年7月9日 午後0時~午後1時
サブタイトル「芸能界サミット」
申立てに至る経緯
本件番組は、タレントのやしきたかじんが司会し、落語家など数名のゲストが出演している昼の時間帯のトークバラエティー番組である。
(1)の6月放送の番組には、申立人の当時の妻のタレントB氏がゲスト出演し、結婚生活等について赤裸々に語った。
(2)の7月放送の番組には、B氏は出演しなかったが、出演者たちが先の番組におけるB氏の発言にもとづいて、トークを繰り広げた。
申立人は、2005年1月にB氏と結婚し同年8月に離婚したが、上記番組によって申立人の名誉及びプライバシーが著しく侵害されたとして、同年9月21日関西テレビに文書で抗議し、取り消しと謝罪放送を求めた。
これに対し、関西テレビは同年10月14日申立人側の要求には一切応じない旨を回答した。
当事者同士の交渉が不調に終わったことを受けて、申立人は同年11月30日付けで「権利侵害申立書」をBRCに提出した。
目次
- I. 申立てに至る経緯
- II. 申立人の申立ての要旨
- III. 被申立人の答弁の要旨
- IV. 委員会の判断
2006年6月13日 【委員会決定を受けての関西テレビの対応】
2005年度 第27号
新ビジネス“うなずき屋”報道
委員会決定 第27号 – 2006年1月7日 放送局:テレビ東京
見解:放送倫理違反
テレビ東京が2005年6月に放送した『ガイアの夜明け~消える高齢者の財産~』というドキュメンタリー番組において、”孤独老人相手の新商売”として紹介された男性が、悪徳業者と受け取られる放送内容だったなどとして、名誉・信用の毀損を申し立てた事案。
2006年1月7日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第27号
- 申立人
- 東京都在住の保育園経営者
- 被申立人
- テレビ東京
- 苦情の対象となった番組
- テレビ東京 ドキュメンタリー番組『ガイアの夜明け~消える高齢者の財産~』
- 放送日時
- 2005年6月14日 午後10時00分~10時54分 (テレビ東京系列各局で放送)
申立てに至る経緯
本件番組は、最近多発し大きな社会問題になっている「悪徳リフォーム」や「振り込め詐欺」など、高齢者の財産を狙う犯罪の手口を取材し、警鐘を鳴らすとともに、その対策を紹介することを目的に制作したものであり、その中で、核家族化が進み孤独な高齢者が増加している状況を背景にして出現した新商売が紹介された。
申立人は、〈消える高齢者の財産〉というタイトルのこのドキュメンタリー番組の中で“孤独老人相手の新商売”を行っている者として紹介されたが、ただうなずくだけで「2時間1万円」をとる、「高齢者の寂しさにつけ込みお金をむしり取る悪徳業者」と視聴者に受けとられる放送内容だったとして、当該局に対し名誉・信用の侵害を主張し、謝罪、訂正放送などを求めた。双方で話し合いが行なわれたが決着がつかず、放送人権委員会に苦情を申立てた。
目次
- Ⅰ. 申立てに至る経緯
- Ⅱ. 申立人の申立ての要旨
- Ⅲ. 被申立人の答弁の要旨
- IV. 委員会の判断
2006年3月20日 【委員会決定を受けてのテレビ東京の対応】
2005年度 第26号
新喫茶店廃業報道
委員会決定 第26号 – 2005年10月18日 放送局:毎日放送
見解:放送倫理違反
たこ焼き屋の店主の申立て。喫茶店の入り口付近で営業していたが、2005年5月の毎日放送のニュース番組『VOICE』の特集について、「隠しマイクの録音、隠しカメラの映像を巧みにつなぎ合わせ、いかにも私が嫌がらせを続けて喫茶店を廃業に追いやったかのように放送された」として、人権侵害などを訴えた。
2005年10月18日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第26号
- 申立人
- 兵庫県在住 元たこ焼き屋台店主
- 被申立人
- 毎日放送
- 苦情の対象となった番組
- 毎日放送 ニュース番組「VOICE」
特集「憤懣本舗:嫌がらせの『屋台』・無神経な『役所』」 - 放送日時
- 2005年5月9日午後6時16分~6時55分内
申立てに至る経緯
放送内容
「兵庫県宝塚市内のある駅前の喫茶店の入口付近において、女店主がたこ焼き屋台器具を搭載した車を夜間日常的に違法駐車して営業していたことに端を発し、付近 住民が再三にわたって警察に通報し、市役所にも相談したところ、警察が同たこ焼き屋台の移動をさせたり、市当局がバリケードを設置して駐車できないようにした。市当局から通報者を聞き出した女店主がこれに憤慨して喫茶店に乗り込んで大声で脅迫めいた抗議をし、また度重なる嫌がらせをした結果、喫茶店の常連客は怖がって寄りつかなくなり、売り上げがガタ落ち、喫茶店営業者は閉店に追い込まれたのに、市は責任をとることなく、当のたこ焼き店は今も営業している」という趣旨のナレーションのもとに、毎日放送は、喫茶店営業者がサラリーマン時代に貯めた資金で苦労して喫茶店を開業した状況、たこ焼き屋台車を違法駐車して営業している状況を隠し撮りして放送した。
さらに、客を装って同店主が喫茶店の悪口をしゃべるのを密かに録音し、また、喫茶店に乗り込んで客の前で大声で抗議している状況を密かに録音したテープを入手して、これらのテープの音声を流し、喫茶店は閉店に追い込まれたのに当のたこ焼き店主は依然営業を続けると言っている状況を隠し撮りにより放送した。
目次
- Ⅰ. 申立てに至る経緯
- Ⅱ. 申立ての趣旨及び理由の要旨
- Ⅲ. 被申立人の答弁の要旨
- IV. 委員会の判断
2006年1月16日 【委員会決定を受けての毎日放送の対応】
2005年度 第25号
産婦人科医院・行政指導報道
委員会決定 第25号 – 2005年7月28日 放送局:NHK名古屋局
勧告:重大な放送倫理違反
産婦人科医院の院長が2005年1月にNHK名古屋放送局が放送したニュースにおいて、「行政指導を受けたことを実名で報道され、しかも指導を受けた時期を明示せず現在も違法行為を行っているかのように伝えられたことにより、名誉と信用を毀損され人権を侵害された」と申し立てた事案。
2005年7月28日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第25号
- 申立人
- 愛知県在住の産婦人科医院院長
- 被申立人
- NHK名古屋放送局
- 苦情の対象となった番組
- NHK名古屋放送局制作のニュース番組
- 放送日時
- 2007年(平成17年)1月25日
総合テレビ 午後5時10分~6時59分『ほっとイブニング』(愛知・岐阜・三重の3県向け地域情報番組)
ラジオ第1 午後6時50分~7時00分(愛知・岐阜・三重の3県)、午後11時10分~11時20分(中部ブロック)
申立てに至る経緯
放送内容
愛知県○○市の産婦人科医院が、助産師の資格を持たない看護師や准看護師に妊婦への内診などの助産行為をさせていたとして、愛知県と保健所が改善を指導していたことがわかったというニュース。
この放送に対して、申立人は「平成17年1月25日、NHK名古屋放送局(以下「NHK」又は「被申立人」という)の記者から『助産師不足で、産婦人科医療現場は大変困っているとのことなので、実情を調べ、少しでも現状を改善するのに役立つ番組を企画したい』との取材依頼があり、それに応じたが、取材の趣旨と違って、助産師の資格がない看護師、准看護師に内診等の助産行為をさせていたとして、行政指導を受けたことを実名で報道され、しかも指導を受けた時期(平成15年10月)を明示せず、現在も違法行為を行っているかのように報道されたことにより、名誉と信用を毀損され、人権を侵害された」としてNHKに抗議し、訂正放送と謝罪を求めた。
これに対し、NHKは、「無資格者による助産行為は重大な社会的問題と認識し、愛知県内でも行政指導の事例があった事を啓発することが重要だと判断して報道したのであり、特定の医療機関を貶める意図をもって報道したものではない。記者は最初から『行政指導の事実について確認したい』と告げて取材した。また翌1月26日に申立人から抗議を受けた『行政指導を受けた時期の明示』と『コメント内容の間違い』については、1月26日に修正放送を行い、その後の話し合いでも新たな要求は無く、放送上の対応については理解を得られたと認識している」としている。
放送後、3回の話し合いが行われたが、双方の主張に隔たりがあり、申立人からBRCに審理要請がなされ、2月の委員会で審理入りを決定した。審理入り決定後、申立人から手直しした「申立書(改訂版)」及び「権利侵害補充書」が提出された。
目次
- Ⅰ. 申立てに至る経緯
- Ⅱ. 申立人の申立ての要旨
- Ⅲ. 被申立人の答弁の要旨
- IV. 委員会の判断
2005年10月18日 【委員会決定を受けてのNHK名古屋放送局の対応】
2004年度 第24号
警察官ストーカー被害者報道
委員会決定 第24号 – 2004年12月10日 放送局:名古屋テレビ
見解:問題なし
警察官からストーカー行為の被害を受けた女性が、警察に被害届を出した際に名古屋テレビからインタビュー取材を受けたが、意に反してニュース等において顔を出して放送され、肖像権やプライバシーの権利侵害を受けたと訴えた事案。
2004年12月10日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第24号
- 申立人
- 愛知県在住の女性
- 被申立人
- 名古屋テレビ
- 苦情の対象となった番組
- 名古屋テレビ放送制作の番組
- 放送日時
- 2004年 3月 9日 17時台『スーパーJチャンネル』、22時台『ニュースステーション』
3月10日 5時台『朝いち!やじうま』、7時台『やじうまプラス』
申立てに至る経緯
放送内容
警察官にストーカー行為を受けたとする愛知県在住の女性が、傷害、暴行の被害届を出したというニュース。女性の、警察官に対する憤りのインタビューを含む。
この放送に対して、申立人は、「名古屋テレビ放送(以下「名古屋テレビ」または「被申立人」という)のインタビューに応じた際、顔出しの放送はしないとの約束がなされていたにもかかわらず顔出しで放送されたため、世間から興味本位で見られるなど、肖像権を侵害されたのをはじめ、プライバシーなど人権を侵された」として、放送後名古屋テレビに抗議し、謝罪を求めた。
これに対し、名古屋テレビは、「取材の際、顔出しで放送することの了承を得ており、申立人の勇気ある告発の意志を尊重して顔出し放送に踏み切ったものであり、訴えは心外」と主張した。
放送直後に、申立人からBRCに対し苦情が寄せられたが、名古屋テレビが話し合いによる解決の意向を示し、断続的に話し合いが行われた。しかし、双方の事実認識に大きな隔たりがあり、6月、申立人から「申立書」が提出され、その後の話し合いも不調に終わったことから、BRCでは話し合いによる解決が困難と判断し、8月の委員会で審理入りを決定した。審理入り決定後、申立人から手直しした「申立書(改訂版)」が提出された。
目次
- Ⅰ. 申立てに至る経緯
- Ⅱ. 申立人の申立ての要旨
- Ⅲ. 被申立人の答弁の要旨
- IV. 委員会の判断
【委員会決定を受けての名古屋テレビの対応】
2004年度 第23号
国会・不規則発言編集問題
委員会決定 第23号 – 2004年6月4日 放送局:テレビ朝日
勧告:人権侵害
2003年9月のテレビ朝日の情報トーク番組『ビートたけしのTVタックル』で、自民党の衆議院議員が予算委員会でヤジを飛ばしている映像が使われ、同議員が「全く関係ない映像を切り貼り編集した捏造で、名誉を毀損された」などと訴えた事案。テレビ朝日は別番組で同議員に意見表明の機会を提供し、当該番組内でもお詫びをしたが、同議員は救済措置を求めて申し立てた。
2004年6月4日 委員会決定
- 申立人
- 藤井孝男
- 被申立人
- テレビ朝日
- 苦情の対象となった番組
- テレビ朝日 「ビートたけしのTVタックル」
- 放送日時
- 2003年9月15日(月)午後9時から9時54分まで
申立てに至る経緯
株式会社テレビ朝日(以下「テレビ朝日」又は「被申立人」という)は、2003年9月15日(月)午後9時から9時54分まで、「ビートたけしのTVタックル」第627回「あれから1年…日本の決断」を放送した。
テレビ朝日は、同番組中の「自民党総裁選と北朝鮮問題」において、自民党総裁選挙に立候補した4人の候補者がこれまで北朝鮮問題へどのように対応してきたかについての発言を紹介する放送をしたが、自由民主党所属の衆議院議員であって同党総裁選挙に立候補している申立人(以下「藤井議員」又は、「申立人」という)については、同年9月9日の候補者所信発表演説会の北朝鮮に関する発言の紹介に引き続き、1997年2月3日の衆議院予算委員会において西村真悟議員(当時新進党)が「横田めぐみという一人の13歳の少女が拉致されたというむごい事件に関して」との質問を開始した直後に藤井議員が「発言に気を付けろ」、「しっかり責任をもって発言しろよ」との不規則発言をしたと視聴者に認識される放送(以下「本件番組部分」という)をした。
藤井議員は、上記不規則発言は、全く関係のない映像を切り貼り編集した「やらせ」映像であり、藤井議員が北朝鮮に対する拉致問題では極めて消極的な態度をとっているとの印象を一般視聴者に与えるものであり、藤井議員の名誉を著しく毀損するとともに、総裁選挙(2003年9月8日告示、同月20日開票)の悪質な選挙妨害であるとして、テレビ朝日に対し厳重抗議した。
テレビ朝日は、同年9月19日放送の「ニュースステーション」において他の総裁候補者と共に出演した藤井議員に特別に意見表明の機会を提供し、藤井議員は、「全くの事実無根であり、捏造といっていい」との発言をした。さらに、テレビ朝日は、同年10月6日の「ビートたけしのTVタックル」で「二つの場面が拉致問題に関する一連の議論であるとの認識で、直接繋げる編集を行ったため、藤井議員が横田めぐみさん拉致問題に対して不規則発言を行ったかのような誤った印象を視聴者に与える結果となったことについて心よりお詫び申し上げる」旨のお詫び放送をした。
その後テレビ朝日と藤井議員あるいは自民党との間で数回にわたり本件に関する話し合いないし電話連絡がもたれたが、同年12月11日藤井議員からテレビ朝日を相手方として当委員会に対し、本件申立てがなされた。
目次
- Ⅰ. 申立てに至る経緯
- Ⅱ. 申立人の申立ての要旨
- Ⅲ. 被申立人の答弁要旨
- IV. 委員会の判断
2004年8月11日 【委員会決定を受けてのテレビ朝日の対応】
2004年度 第22号
中学校教諭・懲戒処分修正裁決報道
委員会決定 第22号 – 2004年5月14日 放送局:北海道文化放送
勧告:人権侵害(少数意見付記)
北海道文化放送は2003年10月の『スーパーニュース』で教育界におけるセクハラ急増問題を取り上げた。この中で、問題教師として取り上げられた中学教諭が「人事委員会が刑罰法規に触れる行為でない等の理由で教育委員会の懲戒処分を軽減したにもかかわらず、放送はこの修正採決を曲解してセクハラ教師と印象付け、名誉を傷つけ教壇復帰を妨げようとした」と訴えた事案。
2004年5月14日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第22号
- 申立人
- 北海道在住中学校教諭
- 被申立人
- 北海道文化放送放送
- 苦情の対象となった番組
- 北海道文化放送(UHB)<スーパーニュース>内「今日の特集」
- 放送日時
- 2003年10月14日午後5時50分
申立てに至る経緯
特集の内容
「生徒にキスを迫った教師の信じられない行為に親も激怒・・・処分は妥当?
スクールセクハラの驚くべき実態」(新聞テレビ欄タイトル)
申立人は、「5回にわたって自校の女子生徒の頬にキスをしたほか、同生徒と二人だけでドライブや食事に行き、また自宅の鍵を渡して生徒を自宅に招くなど、教育公務員としての節度を著しく逸脱した」として、北海道教育委員会から2002年4月12日付で懲戒免職処分に付された。
この処分に対して、申立人は、北海道人事委員会に対して懲戒権の濫用があるとして、処分の取消ないし修正を求める不服申立てを行った。
この申立てに対し、北海道人事委員会は、2003年7月10日、申立ての一部を認め、「申立人の行為は、教育公務員としてふさわしくない非違行為に該当するが、いわゆるセクシュアル・ハラスメントと評価されるものでなく、刑罰法規に触れるものではない」として、「処分は重きに失し、処分者の裁量権を逸脱した違法がある」(要旨)との理由で、停職6か月の処分に修正する裁決を下した。
これに対して北海道教育委員会は、同年9月18日、再審を請求したが、同年12月17日、再審事由に当たらないとして却下した。
以上の事実経過の中で、北海道教育委員会の再審請求後、その却下決定がなされるまでの間である10月14日に行われたのが本件放送であり、申立人は、本件放送内容が申立人の名誉を毀損し、申立人の職場復帰を妨げるものであるとして、10月17日以降12月22日まで、申立人代理人を通じ苦情を申し入れ、再三にわたり交渉の機会を持ったが、了解に達せず、2004年1月7日、当委員会に対して本申立てを行うに至ったものである。
目次
- Ⅰ. 申立てに至る経緯
- Ⅱ. 申立人の申立ての要旨
- Ⅲ. 被申立人の答弁要旨
- IV. 委員会の判断
2004年6月21日 【委員会決定を受けての北海道文化放送の対応】
2003年度 第21号
山口県議選事前報道
委員会決定 第21号 – 2003年12月12日 放送局:テレビ山口
見解:放送倫理上問題あり(少数意見付記)
申立人は2003年4月の県議会議員選挙に立候補した男性。テレビ山口が選挙前の3月のニュース番組で放送した統一地方選挙の企画「県議選・なんでも一番」において、申立人が最多立候補者として実名・顔写真付きで「合わせて12回出馬していますが、いずれも当選に至っていません」と紹介されたとして、選挙妨害であり人権を侵害されたと訴えた事案。
2003年12月12日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第21号
- 申立人
- A
- 被申立人
- テレビ山口
- 苦情の対象となった番組
- テレビ山口 「TYS夕やけニュース21」
- 放送日時
- 2003年3月25日午後6時19分から6時51分まで
申立てに至る経緯
2003年4月の統一地方選挙を前にした3月25日、テレビ山口株式会社(以下、「テレビ山口」または「被申立人」という)は、午後6時19分から6時51分までの「TYS夕やけニュース21」の中で「統一地方選ミニ知識」として企画した14本シリーズのうちの1本「県議選・なんでも一番」を放送した。
内容は、最年少当選者、最多得票者など過去の県議選データから拾い上げた「一番」を紹介するもので、最後に「また補欠選挙も含めて県議選への立候補の回数が最も多いのはAさんで、71年から合わせて12回出馬していますがいずれも当選に至っていません」というコメントとともにA氏の上半身写真を出し、一行目に「立候補回数最多12回」、二行目に「A氏(下関市区)」、三行目に「⇒いずれも落選」のスーパーを付けた。
この放送に対して、申立人である下関市在住のA氏(以下、「A氏」または「申立人」という)は、放送当日テレビ山口に対して「選挙妨害である。改めて放送で名誉を回復してほしい」旨の抗議と救済措置を電話で要請した。
テレビ山口では、社内協議の上「事実関係は間違っていないので訂正放送は出来ない」と電話で回答した。
しかし、申立人はこの説明に納得せず、3月26日テレビ山口に対して「選挙違反行為である」との文書をFAX送信するとともに、山口地方法務局人権擁護課に対しても人権侵害・名誉毀損で訴えた。また、5月16日に「選挙の自由と公正・平等が阻害され人権が侵害された」とする文書をテレビ山口に送り回答を求めた。
テレビ山口は6月11日、報道制作局長名で「山口地方法務局人権擁護課から人権侵害・名誉毀損には該当しない旨の判断をもらっており、当社には法的責任はないと考えている」旨の文書を申立人に郵送した。
この後、8月1日付けで申立人は、BRCに対し「告示前の大切な時に、真実を曲げ嘘の番組を作り報道されたことで名誉を毀損され、人権を侵害された。また、意に反した悪いイメージの写真を無断で使われ肖像権を侵害された」などと申立てたものである。
目次
- Ⅰ. 申立てに至る経緯
- Ⅱ. 申立人の申立て要旨
- Ⅲ. 被申立人の答弁要旨
- IV. 委員会の判断
2004年2月12日 【委員会決定を受けてのテレビ山口の対応】
2002年度 第20号
女性国際戦犯法廷・番組出演者の申立て
委員会決定 第20号 – 2003年3月31日 放送局:NHK
見解:放送倫理違反(少数意見・補足意見付記)
NHKは2001年1月末から4日連続でETV2001シリーズ「戦争をどう裁くか」を放送した。この2回目「問われる戦時性暴力」に出演した女性が、「何の連絡もなく発言を改変し放送した。この結果、発言が視聴者に不正確に伝わり、研究者としての立場や思想に対する著しい誤解を生み、名誉権および著作者人格権を侵害した」などと申し立てた。
2003年3月31日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第20号
- 申立人
- A・カリフォルニア大学準教授
- 被申立人
- NHK
- 対象番組
- NHK 「戦争をどう裁くか」第2回「問われる戦時性暴力」
- 放送日時
- 2001年1月30日
申立てに至る経緯
2000年12月、東京で民間法廷「日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷」(以下「女性国際戦犯法廷」または「女性法廷」という)が開催された。日本放送協会(以下「被申立人」または「NHK」という)は、この「女性国際戦犯法廷」を取材し、2001年1月29日から2月1日までの4日間連続で、ETV2001シリーズ「戦争をどう裁くか」を放送した。
申立人のカリフォルニア大学準教授、A氏(以下「申立人」または「A氏」という)は、上記シリーズの第2回「問われる戦時性暴力」および第3回「いまも続く戦時性暴力」の放送に、コメンテーターとして出演したが、このうち、第2回「問われる戦時性暴力」(2001年1月30日午後10時~10時40分放送)に対し、「スタジオ収録後、NHKの制作意図の変更に伴い、申立人に対して何の連絡もなく、申立人の発言を改変し放送した。この結果、申立人の発言が視聴者に不正確に伝わり、申立人の研究者としての立場や思想に対する著しい誤解を生み、名誉権及び著作者人格権を侵害した」として、2002年1月10日、BRCに権利侵害救済の申立てを行いたい旨、連絡があった。
BRCでは、NHKに相容れない状況にあるのか確認したところ、「A氏とは、個人の人権侵害について直接には一度も話し合いがなされていない」との説明があり、BRCとしては、双方に当事者間での交渉を継続するよう要請した。
この交渉の中で、同年7月8日、一時帰国したA氏とNHKとの直接面談が実現したが、双方の主張、認識の差が大きく、これ以上、話し合いの余地がないことを双方で確認して、交渉は物別れに終わった。このため、申立人が8月2日、BRCに権利侵害救済の申立てを行ったものである。
他方、NHKは、「女性国際戦犯法廷」の主催団体の一つとその代表者が、現在、NHK及び制作委託プロダクションを相手に損害賠償を求めている裁判と「対象番組が同一」「当事者が実質的に同一」であり、「問題とされている事実も同一」との判断から「裁判係争中の事案」に当たり、BRCの審理対象にならないと主張した。
しかし、BRCは本件申立てと裁判係争中の事案とでは当事者が別人格であること、申立て事由が、申立人自らの発言部分に関する指摘である、ことなどを総合的に判断した結果、2002年9月17日の委員会で審理することを決定した。
目次
- Ⅰ. 申立てに至る経緯
- Ⅱ. 申立人の申立て要旨
- Ⅲ. 被申立人の答弁要旨
- IV. 委員会の判断
2002年度 第19号
福井・産廃業者行政処分報道
委員会決定 第19号 – 2002年12月10日 放送局:NHK福井放送局
見解:問題なし
福井県は2002年5月、申立人である産廃の収集運搬業者の事業許可を取り消す行政処分を行なった。NHK福井放送局は同日のニュースでこれを伝えたが、申立人は「処分が発効する前の一方的な放送で、名誉・信用を著しく損ねた」と訴えた。
2002年12月10日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第19号
- 申立人
- 福井県内の産業廃棄物収集運搬業者
- 被申立人
- NHK福井放送局
- 対象番組
- NHK福井放送局 ローカルニュース
- 放送日時
- 2002年5月24日 午後6時10分からと午後8時45分から
申立てに至る経緯
2002年5月24日、福井県廃棄物対策課は、県内の産業廃棄物収集運搬業者である申立人が、契約のない処理業者に産業廃棄物を運び込んだ上、廃棄物の受け渡しを管理するための書類に虚偽の記載をしていたとして、この収集運搬業者の事業許可を取り消す行政処分を行った。
NHK福井放送局(以下「被申立人」または「福井局」という)は、県が公表したこの処分内容を同日午後6時10分からと午後8時45分からのローカルニュース枠で放送した。
この放送に対して、処分を受けた収集運搬業者である申立人は、6月6日「NHKのニュースは誤った内容である上、不適正な画像放映が為されたことにより、申立人の会社や役職員らの人権と名誉を著しく損ねた」と文書で福井局へ抗議し、謝罪報道等の救済措置を講ずるよう要求した。
福井局では、福井県に問い合わせるなど報道内容について再調査したところ事実関係に間違いがないことが確認できたとして、6月8日申立人側に電話で「県の発表に基づき事実を伝えたもので、映像についても県の発表後に撮影取材したもの」と説明した。
しかし申立人側はこの説明に納得せず、6月10日にBRO事務局に「放送局側は非を認めず、決裂状態になった」と伝え、申立ての意向を示した。
その後申立人は6月14日福井県と県知事を相手取って「処分の取り消しと損害賠償を求める訴え」を福井地裁に起こした。
この一か月余り後の7月24日付けで申立人は「被申立人は当方への取材・確認をしないまま、県の一方的な言い分を報道して、当方の名誉・信用を毀損した」などとして、BRCに申立てたものである。
目次
- Ⅰ. 申立てに至る経緯
- Ⅱ. 申立人の申立て要旨
- Ⅲ. 被申立人の答弁要旨
- IV. 委員会の判断
2002年度 第18号
出演者比喩発言問題
委員会決定 第18号 – 2002年9月30日 放送局:テレビ朝日
見解:番組内・放送後の対応に問題あり(少数意見付記)
2001年9月のテレビ朝日の情報番組『サンデープロジェクト』の討論において、ゲスト出演者が「戸塚ヨットスクール」を比喩に用いて発言し、同スクールの校長が重大な名誉毀損だと訴えた事案。
2002年9月30日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第18号
- 申立人
- A
戸塚ヨットスクール校長 - 被申立人
- テレビ朝日
- 対象番組
- テレビ朝日 報道番組『サンデープロジェクト』
- 放送日時
- 2001年9月9日午前10時
申立てに至る経緯
申立ての対象になった番組は、2001年9月9日(日)午前10時の全国朝日放送株式会社(以下「テレビ朝日」という)の報道番組『サンデープロジェクト』であるが、その中で、「緊急・救国経済大討論」のタイトルの下、当面する日本の経済危機をどう乗り切るかをテーマに、司会者と3人のゲスト出演者による討論が、約23分間、放送された。
上記放送の中で、ゲスト出演者の経済アナリスト・森永卓郎氏(以下「当該ゲスト」という)が、IMFの対日審査をめぐって、「IMFなんか受け入れたら、あれは戸塚ヨットスクールですからね」「しごきの理論しかないんですよ。もう、どれだけのアジアの国を駄目にしたか分かっているんですか。あれはひどいところなんですよ」と発言した(以下「当該発言」という)。
戸塚ヨットスクール(以下「ヨットスクール」ともいう)側は、次週放送の前日である9月15日(土)午後10時30分頃、テレビ朝日に電話し、「当該発言は戸塚ヨットスクールがしごきで子供を駄目にしたという意味になり、同スクールと同校校長のAに対する重大な名誉毀損にあたる。謝罪と訂正をしてほしい」と抗議した。これに対して、テレビ朝日側は、「名誉毀損には当たらない」などと答えた。
その後、申立人、被申立人とも弁護士を通じ、それぞれ3回の文書の交換を行ったが、解決に至らず、A氏は、2002年2月21日、放送と人権等権利に関する 委員会(以下「委員会」という)に申立てを行ったものである。
申立人が校長を務めるヨットスクールは、同人により、1977年、愛知県美浜町に開設されたもので、厳しいスパルタ式のヨット訓練などを標榜し、情緒障害などの子供を中心に、全国から訓練生を集めていた。
しかし、1980年以降に訓練生の死亡事件が発生し申立人らが起訴され、2002年2月25日に、最高裁判所は上告を棄却する決定を下したため、申立人に対して傷害致死による懲役6年の刑が確定した。申立人は、同年3月29日に収監されたことにより、申立人側は同人妻である戸塚幸子氏を申立人代理人とした。
2002年3月19日開催の委員会は、「直接話し合いによる解決の機会を持つべきである」と判断し、双方に話し合いを求めた。
同年6月14日、申立人側から、「テレビ朝日は『話し合いは弁護士同士で行いたい』と言っているが、これまでも弁護士同士で行ってきて、それでも解決しなかったのだから進展は期待できない。委員会で審理してほしい」との連絡があった。
これを受けて、同年6月18日開催の委員会は、「話し合いによる解決は難しい」と判断し、本件を審理事案とすることを決定した。
目次
- Ⅰ. 申立てに至る経緯
- Ⅱ. 申立人の申立て要旨
- Ⅲ. 被申立人の答弁要旨
- IV. 委員会の判断
2001年度 第17号
熊本・病院関係者死亡事故報道
委員会決定 第17号 – 2002年3月26日 放送局:テレビ朝日
勧告:人権侵害(少数意見付記)
熊本で車に乗っていた病院関係者4人全員が死亡する転落事故があり、テレビ朝日は2000年8月の情報番組で”熊本・謎の自動車事故”のタイトルで取り上げた。この放送に対して、医療法人と理事長が「事故は保険金目的の殺人事件の可能性が高いと報道し、名誉・信用を毀損された」と抗議した。テレビ朝日は翌年7月に地検の「事故は運転ミス」とする最終処分を放送したが、医療法人側は名誉・信用の甚大な被害の回復に足りないとして申し立てた。
2002年3月26日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第17号
- 申立人
- 医療法人A
B(同理事長) - 被申立人
- テレビ朝日
- 対象番組
- テレビ朝日 情報番組『週刊ワイドコロシアム』
- 放送日時
- 2000年8月6日午後6時56分~
申立てに至る経緯
2000年5月28日、熊本県天草町で乗用車が崖下に転落し、乗っていた熊本市内のC病院の副理事長や看護部長ら4名全員が死亡するという事故が起きた。同年8月6日、全国朝日放送株式会社(以下、テレビ朝日又は被申立人という)は、午後6時56分からの情報番組『週刊ワイドコロシアム』でこの事故を”熊本・謎の自動車事故”というタイトルで取上げ、約40分間にわたって放送した。(注 当該情報番組は同年9月10日で終了)
この放送に対して、当病院を経営している医療法人Aと同会を代表するB理事長(以下、申立人という)は、「本件番組は、当該事故を保険金目的の殺人事件の可能性が高いと報道し、申立人の名誉・信用を毀損している」と抗議し訂正放送と謝罪を要求した。
一方、テレビ朝日は、「番組は、警察の杜撰な対応を検証するのが狙いで、保険金目的の事故と捉える意図はない」と主張、話し合いは進展しないまま年を越えた。
2001年2月2日、テレビ朝日は、「検察庁の処分がなされた時点で、情報系の番組で取上げる。その際警察が送致に当たって発表した保険金殺人疑惑がないとの意見を付記する」旨申し入れた。
2001年7月27日、熊本地方検察庁は「事故は、運転ミスによるもので、保険契約と事故は無関係」との最終処分及びコメントを発表した。テレビ朝日は7月30日午前8時からの『スーパーモーニング』の中で、この地検の最終処分内容を放送したが、申立人は、「極めて不十分な放送内容で、当方の名誉・信用に対する甚大な被害を回復するに足りない」として、8月2日、BRCに申立てたものである。
目次
- Ⅰ. 申立てに至る経緯
- Ⅱ. 申立人の申立て要旨
- Ⅲ. 被申立人の答弁要旨
- IV. 委員会の判断
2001年度 第16号
インターネットスクール報道
委員会決定 第16号 – 2002年1月17日 放送局:日本テレビ
見解:放送倫理上問題あり(少数意見付記)
日本テレビは2000年10月『NNNきょうの出来事』で、インターネットを活用して教育を行うフリースクールを取り上げた。学園側は、取材段階でアポなしの強引な取材だと抗議し、報道内容についても事実を歪曲した一方的な内容で、関係者や学園の名誉を著しく毀損したと申し立てた。
2002年1月17日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第16号
- 申立人
- A
B学園高等部理事・事務局長 - 被申立人
- 日本テレビ
- 対象番組
- 日本テレビ ニュース番組『NNNきょうの出来事』
- 放送日時
- 2000年10月20日午後11時30分
申立てに至る経緯
申立ての対象になった番組は、2000年10月20日午後11時30分の日本テレビ放送網株式会社(以下、日本テレビという)のニュース番組『NNNきょうの出来事』で、「インターネットの落とし穴」のタイトルの下、約9分間、放送されたものである。
申立人が事務局長を務める「B学園高等部」(以下、学園という)は、インターネットを活用して教育を行う「フリースクール」で、放送では、入学した生徒たちからは、授業料を払ったのに何の指導もしてくれないと抗議の声があがっており、元生徒と保護者およそ20名からなる「B学園・被害者の会」(以下「被害者の会」という)が結成されているとし、同会会員らへのインタビュー、「生徒の撮影したビデオテープ」や「学園の委託先会社で取締役を解任された旧役員のカセット録音テープ」、申立人への「直接取材」などによって構成されている。
申立人は、この放送に先立つ取材段階において、「アポなし、無通告、かつ嘘を含め強引な」取材について、日本テレビに対し「質問書」などを提出、抗議をするとともに、取材及び放送の取り止めを求めた。放送後においても、「対立している被害者の会なるものの撮影したビデオテープや対立している人物のカセット録音テープ」を放送で使用し、「報道は事実を歪曲し、一方的な内容で関係者や学園の名誉を著しく毀損し、損害を与えた」として、日本テレビに対し、謝罪と被害の回復措置を求める「抗議文」を提出した。
これに対し、日本テレビは、取材は、「通常の報道番組の取材プロセスに沿ったものであること」、放送は、「すべて匿名であり、映像や音声の処理を通じて、プライバシー保護には、十分な注意を図っており」「放送した事実関係に、間違いはないものと確信している」と回答した。
申立人はこれにより、日本テレビとの話し合いはつかないと判断し、2001年7月11日付けで申立てを行ったものである。
目次
- Ⅰ. 申立てに至る経緯
- Ⅱ. 申立人の申立て要旨
- Ⅲ. 被申立人の答弁要旨
- IV. 委員会の判断
2000年度 第12号
自動車ローン詐欺事件報道
委員会決定 第12号 – 2000年10月6日 放送局:伊予テレビ
勧告:人権侵害(少数意見付記)
1999年9月、松山市の元自動車販売仲介業者が架空ローン容疑で逮捕された事件を伝えた伊予テレビのニュースについて、自動車販売業者が「事件と関係ない自分の店の映像が断りもなく撮影され放送された。映像のボカシ処理が不十分で明らかに店名がわかり、事件の共犯かのような印象を多くの視聴者に与えた」などとして、名誉・信用の毀損を訴えた。
2000年10月6日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第12号
- 申立人
- 愛媛県松山市の自動車販売業者
- 被申立人
- 伊予テレビ
- 対象番組
- ニュース番組「キャッチあい」
- 放送日時
- 1999年9月13日
申立てに至る経緯
1999年9月13日、愛媛県松山市で自動車購入の名義貸しを利用し、架空のローン契約を結んで信販会社から現金をだまし取ったとして、元自動車販売仲介業者が詐欺容疑で逮捕された。
伊予テレビではこの事件を、同日夜の県内向けニュース番組「キャッチあい」の中で、映像を使い1分55秒間放送した。
この放送に対し、松山市の自動車販売業者が、「詐欺事件と関係ない自分の店を、断りもなく撮影し放送した。映像のボカシ処理が不十分で、明らかに店名が分かる。放送は、正当な商取引をしただけの当店が、詐欺事件の共犯であるかのような印象を多くの視聴者に与え、多大な迷惑を被っている」と伊予テレビに抗議した。
しかし、放送局側は今回のニュースは、「詐欺容疑で逮捕された元自動車販売仲介業者の逮捕事実を主眼に放送したものであり、申立人の販売店は取引のあった一つの舞台として放送しただけで、映像上もボカシ処理を施し、特定できないよう配慮している。放送原稿でも申立人の販売店名および詐欺事件との関連について一切言及していない」と主張し、双方の話し合いは対立したままに終わった。
このため、自動車販売業者が「放送によって自分や家族の名誉・信用が毀損されただけでなく、経営も追い詰められた」として、今年6月1日、本委員会に「権利侵害」の救済を求める申立てを行った。
目次
- Ⅰ. 申立てに至る経緯
- Ⅱ. 申立人の申立て要旨
- Ⅲ. 被申立人の答弁要旨
- IV. 委員会の判断
1999年度 第11号
隣人トラブル報道
委員会決定 第11号 – 1999年12月22日 放送局:フジテレビジョン
見解:放送倫理上問題あり(少数意見付記)
1998年11月、フジテレビの情報番組『スーパーナイト』は石材業を営む男性とその作業場に隣接する住民の間のトラブルについて放送したが、男性が「放送は隣人の嘘の言い分を信用した一方的なもので、公平・公正を欠き名誉を傷つけられた」と申し立てた。
1999年12月22日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第11号
- 申立人
- 福島県いわき市の石材業者
- 被申立人
- フジテレビジョン
- 対象番組
- 情報番組「スーパーナイト」
- 放送日時
- 1998年11月29日
申立てに至る経緯
1998年11月29日、フジテレビの情報番組「スーパーナイト」で、「激撮ご近所戦争3年間の全記録」(放送時間は24分)のタイトルの下に、福島県いわき市で石材業を営む申立人と、その作業場に隣接する住民(以下「隣人」)との間に生じたトラブルについて放送した。この放送は、トラブルの一方の当事者である隣人から送られてきたビデオテープや録音テープ、及び隣人が3年間にわたって記録した日誌などを基に取材、構成したものである。
この放送に対して申立人は「放送は隣人の嘘の言い分のみを信用した一方的なもので、公正、公平を欠き、終始申立人が悪者として報道され、著しく名誉を傷つけられた」としてフジテレビに抗議した。しかし、「事前の調査と十分な取材に基づいて制作したもので、放送内容に問題はない」とするフジテレビとの間で話し合いがつかず、今年8月、本委員会に申立がなされたものである。
目次
- Ⅰ. 申立てに至る経緯
- Ⅱ. 申立人の申立て要旨
- Ⅲ. 被申立人の答弁要旨
- IV. 委員会の判断
1997年度 第1号~第4号
サンディエゴ事件報道
第1号~第4号 – 1998年3月19日
1996年5月、アメリカで日本人教授と娘が射殺される事件が起きた。この事件の報道について、教授の夫人が、自分が事件に関与していたのではないかという予断に基く誤報、犯人視報道が繰り広げられたとして、NHK、TBS、テレビ朝日、テレビ東京を相手に名誉やプライバシーの侵害等を訴えた事案。
第4号 – 放送局:テレビ東京 見解:放送倫理上問題あり
第3号 – 放送局:テレビ朝日 見解:放送倫理上問題あり
第2号 – 放送局:TBS 見解:放送倫理上問題あり
第1号 -放送局:NHK 見解:問題無し
第4号 – 放送局:テレビ東京
- 申立人
- A教授夫人
- 被申立人
- テレビ東京
- 対象番組
- 「NEWS THIS EVENING」(平成8年年5月10日)
- 目次
- 申立てに至る経緯
申立人の申立て要旨
被申立人の答弁の要旨
委員会の判断
第3号 – 放送局:テレビ朝日
- 申立人
- A教授夫人
- 被申立人
- テレビ朝日
- 対象番組
- 「やじうまワイド」(平成8年5月10日・22日)
「ANNニュース」(平成8年5月10日等)
「スーパーモーニング」(平成8年5月10日等)
「ワイドスクランブル」(平成8年5月16日) - 目次
- 申立てに至る経緯
申立人の申立て要旨
被申立人の答弁の要旨
委員会の判断
第2号 – 放送局:TBS
- 申立人
- A教授夫人
- 被申立人
- TBS
- 対象番組
- 「ニュースの森」(平成8年5月10日)
「関口宏のサンデーモーニング」(平成8年5月19日) - 目次
- 申立てに至る経緯
申立人の申立て要旨
被申立人の答弁の要旨
委員会の判断
第1号 – 放送局:NHK
- 申立人
- A教授夫人
- 被申立人
- NHK
- 目次
- 申立てに至る経緯
申立人の申立て要旨
被申立人の答弁の要旨
委員会の判断
第1号~第4号 審理経過
当該局の対応
委員長談話
2006年5月25日
2006年5月25日
放送と人権等権利に関する委員会委員長 竹田 稔
「秋田県能代地区における連続児童遺体発見事件」取材についての要望
4月9日に行方不明となり翌10日に遺体で発見された小学校4年の畠山彩香さんの母親から、昨24日、BPO[放送倫理・番組向上機構]に「テレビ、新聞、雑誌等メディア各社の猛烈な取材攻勢に見舞われ、生活を脅かされている。何とかして欲しい」という訴えが寄せられました。
母親は、「取材攻勢が激しくなったのは小学校1年の米山豪憲君の遺体が発見された5月18日以降で、自宅とその周辺は各社取材陣の数十台と思われる車に取り囲まれ自宅には住めず、避難先の実家も取材攻勢にあって外出もままならない。窓は開けられず、職場にも取材陣が付きまとう現状だ。27日(土)に娘の納骨を予定しているが、現状では出来そうにもない。何とか納骨だけは無事に済ませたい」と訴えています。
BRC[放送と人権等権利に関する委員会]は、放送による表現の自由を確保しつつ、放送による人権侵害の被害を救済するため人権侵害に関連する苦情申し入れに対しては、第三者機関として迅速、的確に対応し、正確な放送と放送倫理の高揚に寄与することを目的としています。
当委員会は、1999年12月に「桶川女子大生殺害事件」に関して各社に取材の自粛を求める委員長談話を出していますが、今回のケースについても、放送各社に対し真相の究明を急ぐあまり過剰取材に陥り、本件事案の取材対象者のプライバシーを侵害することのないよう、節度をもって取材に当たることを強く要望します。
以上
2005年12月27日
2005年12月27日
放送倫理・番組向上機構
放送と人権等権利に関する委員会(BRC)委員長 飽戸 弘
「犯罪被害者等基本計画」に関するBRC声明
急激な社会の変化の中で、人々は内外の複雑困難な問題に直面し、とまどいと混迷を深めている。平和で安全な日々の暮らしを守るためには、生起する事態についてその真実を究明し、原因や問題点を明らかにすることが何よりも必要である。人々はこうした情報の提供を受けて自ら意見を形成し、それを自由に表明することを通じて、自らの生活を守り、社会をよりよい方向へ導くことができる。
そのためには、メディアにより、人々への必要かつ有益な情報が十分に提供されなければならない。メディアはこの点で重要な役割を担っており、人々の知る権利に十分に応えるべき責務がある。
本日、内閣は犯罪被害者等基本計画を閣議決定し、犯罪被害者の氏名を実名で発表するか否かを警察の判断に委ねることとした。
しかし、犯罪被害者の氏名は事実の確認や検証のための取材の出発点であるから、今回の措置は情報の流れを事前に警察当局が封鎖することに等しく、メディアによる情報収集を困難にし、人々がメディアを通じてその情報を受け取る自由を制約する結果を惹起することを否定しがたい。
これまで、メディアの側において犯罪被害者らに対し、無神経な取材や行き過ぎた報道がなされたことは事実であり、真摯な反省が求められているところである。しかし、現在メディアはその反省に立って、取材については平成14年4月、日本新聞協会が「集団的過熱取材対策小委員会」を設置し被害防止を図ってきている。また、行き過ぎた放送による被害については、平成9年5月NHKと民間放送各社において第三者機関としての「放送と人権等権利に関する委員会」を設立し、多くの苦情を受け付け、被害を訴える者と当該放送局との間の斡旋解決を図るとともに、現在までに17事案26件について決定を出して放送被害の救済に努めてきている。今回の措置は、当委員会のこうした努力やその果たしている役割を軽視するものと言わざるを得ない。
犯罪被害者の実名開示の可否の問題は、被害者間でも意見が分かれているところである。これに対する対応は、報道関係者が取材の際に被害者との信頼関係を築きながら、事件の社会的性格への配慮と被害者の希望を尊重・配慮することにより自主的に解決すべきであって、犯罪捜査に直接関わる警察に判断を委ねることで解決すべき問題ではないと考える。
以上のとおり、民主主義社会を根底から支える報道の自由の見地から、警察が情報の流れを事前に抑制することとなる今回の閣議決定は報道の死命を制しかねない重大な問題であることを広く訴えるとともに、内閣に対しては同措置を早急に改めるよう強く要望する。
以上
2001年9月18日
2001年9月18日
放送と人権等権利に関する委員会(BRC)
BRCの審理と裁判との関連についての考え方
【現在の運営原則】
「放送と人権等権利に関する委員会」[以下、「BRC」]の運営は、「放送と人権等権利に関する委員会機構」[以下、「BRO」]の規約およびそれに基づいて制定されたBRC運営規則に従って行われている。そして、BRO規約第4条の第1号に定められているBRCの事業(任務)は『個別の放送番組に関する、放送法令または番組基準にかかわる重大な苦情、特に人権等の権利侵害にかかわる苦情の審理』とされているが、司法に基づき係争中のものは除かれている。この規約を受けてBRC運営規則第5条も、その第1項(4)において、『裁判で係争中の問題は取り扱わない』とするとともに、また『苦情申立人、放送事業者のいずれかが司法の場に解決を委ねた場合は、その段階で審理を中止する』と規定しており、申立ての受理や審理はこの規約および規則に従って行われている。
しかし、裁判を受ける権利は当然、当事者に存在するのであるから、BRCの審理が終了し、苦情申立人、放送事業者のいずれかまたは双方がBRCの決定を不満として裁判に訴えることは何ら妨げないし、現に過去の審理案件においても、審理終了後改めて訴訟になった事例がある(「大学ラグビー部員暴行容疑事件報道」「隣人トラブル報道」)。さらにまた、同様の報道を行った放送局のうち、2放送局に対しては民事提訴するとともに、他方で4放送局に対してはBRCに申し立てた事例(「サンディエゴ事件報道」)や、訴訟にするかBRCに申し立てするか慎重に検討した結果、民事提訴を選んだ事例(「所沢ダイオキシン報道」)もある。
【BRCが「裁判で係争中の問題は取り扱わない」ことの意味】
- では、BRCが裁判で係争中の問題は取り扱わないこととする理由は、どこにあるか。その第一は、法的判断の齟齬を防ぐことにある。BRCの任務は主に人権等の権利侵害にかかわる苦情の審理であり、当然、法的判断が重要となる。そのため、現在、BRCを構成する8人の委員のうち、4人は最高裁裁判官経験者を含む法律家となっている。他方、裁判所はもちろん法的判断の場であって、もしBRCに申し立てている事案が同時に裁判所で審理されるならば、場合によって裁判所とBRCの判断に齟齬が起きる可能性が生じよう。もちろん、一方は国家機関であり他方は民間の自主機関であるから、その間に判断の食い違いが生じること自体には否定的ではない。しかし、問題はBRCの判断は単に法的視点にとどまらず、広く放送倫理の視点を踏まえて行われているし、また行われなければならないということである。したがって、法的判断と放送倫理的判断が切り離せないような事案は、裁判所よりもBRCがよりふさわしいものと思われる。
- また、第二の理由として、機能上の相違が挙げられる。自主的苦情処理機関であるBRCには法に基づいた強制的調査権がないので、真実発見・確定する能力に欠けるところがある。したがって、同一事案について、申立てと提訴が並行した場合または提訴が確定している場合には、裁判という強制的調査権により担保された直截的で最終的紛争解決に委ねるのが妥当である。また、裁判所にも調停・仲裁の機能があるが、BRCは連絡や斡旋で解決する事例が多いことからも明らかなように、主として謝罪や訂正を求める場合は裁判所に比べ手続きが簡単で迅速な処理が行われやすいBRCへの申立てが望ましいと考えられる。
- BRCが裁判で係争中の問題は取り扱わないこととする第三の理由は、BRCが主として救済しようとしている報道被害者は、社会的にも経済的にも比較的弱い立場にある個人が念頭に置かれている。本来、名誉毀損等権利侵害に対する回復は訴訟手続きによるべきものであるが、訴訟は裁判費用や日数の点で一般人には利用しにくい難点がある。無料で、しかも迅速に解決できるというのがBRCの特徴であるが、裁判に訴えるだけの力のある報道被害者は、あえてBRC救済を必要としない立場にあるものと判断される。また、裁判所に比較するまでもなく、組織的にも人員的にも弱体なBRCとしては、種々の理由で訴訟を起こし得ない報道被害者を主な対象とすべきなのである。
【外国の状況について】
- では、外国の状況はどうであろうか。非公的機関としての日本のBRCは、放送の苦情処理機関としては世界で稀な存在であるが、それに近いものとして英国のBSC[Broadcasting Standards Commission、放送基準委員会]がある。BSCは、1966年放送法によって設立された公的機関であるが、BSCが扱う苦情は、番組における、①不当もしくは不公平、②プライバシーの不当な侵害、および、③性・暴力表現、④差別と品位、の4分野である。これらのうちBRCと共通するのは、②のプライバシー侵害であるが、名誉毀損をはじめ放送による権利侵害一般を対象としている点では、BRCのほうがBSCよりも範囲は広い。裁判との競合について放送法の規定はないが、一般法と特別法の原則から、プライバシー侵害については放送法による解決が優先するものと思われる。この点に関し、1998年11月にBROを訪問したBSCのハウ委員長は、「BCC(96年放送法で現BSCに統合)時代に、コミッションの裁定に不満で放送局が裁判所に訴えたケースが6件あり、そのうち1件は私たちの裁定が覆された」と述べている。
また、BSCでは、苦情の受理に関する規定として、『委員会の権限が及ばない事柄に関する苦情、もしくは申立期限を経過した事柄』とともに、『英国内の裁判所で係争中の事柄についての苦情、および、当該の放送に関して英国内の裁判所に訴えるに足る法的根拠のある事柄についての苦情は、受理されない』と掲げており、BRO設立に当たり参考にした経緯もある。
- 米国にはBSCないしBRCのような全国的組織は存在しないが、1980年に放送メディアをも対象としたミネソタ・ニュース・カウンシル[Minnesota News Council。以下、「MNC」]が誕生した。この組織の前身は、英国の報道評議会[Press Council]を参考に1978年に設立されたミネソタ・プレス・カウンシル[Minnesota Press Council]であるが、放送界にも参加の希望があり、現在のMNCに改組された。つまり、MNCも英国の報道評議会を参考にしているわけであるが、それに倣った重要な点の一つとして、裁判との関係がある。この問題について、浅倉拓也氏はその著『アメリカの報道評議会とマスコミ倫理――米国ジャーナリズムの選択』(1999年・現代人文社)のなかで、次のように解説している。
「MNCに苦情を申し立てる場合、名誉毀損などの訴訟を起こさないという誓約が要求される……。もちろん裁判で係争中の問題も受け付けない。MNCが苦情を審議する際に提供された情報や、MNCの報告、裁定文などの中で公表された事実に関しても、苦情申立人はこれらを名誉毀損や誹謗などのかどで裁判に訴えることはできない。」
訴訟の権利を放棄しなければ苦情の申立てはできないという条件は、BRCのそれよりもはるかに厳しいが、その理由について浅倉氏は、MNCのギルソン事務局長の次の説明を紹介している。
「もし訴訟する権利を放棄する必要がなく、しかもMNCが苦情申立人の主張を認める判断を示せば申立人はその結果を裁判所に持ち込んで訴訟を起こすだろう。そうなればメディアは二度とMNCの審理に参加しなくなるだろう。」
- 苦情申立人からすれば、MNCの訴訟放棄の条件はいささか厳しすぎるようにも思われるが、裁判所のほかに、MNCやBRCのような苦情処理機関があることは、ある意味でメディアは”二重の危険”にさらされるわけである。また、苦情処理機関での証拠や証言が裁判で一方的に利用される危険性があり、そのため、第三者機関の存在を支えている”善意の合意”が崩れるおそれもある。米国で全国レベルの第三者的報道評議会が存在せず、また地方でもMNCを除いて成功していないのは、そのへんに大きな理由があるものと考えられる。BRCと裁判との関係も、さらに検討される必要があるが、その場合にも慎重な態度が望まれる。
なお、英国では1990年に入って報道評議会が廃止され、91年からプレス業界の苦情処理機構として新たにプレス苦情委員会[PCC=Press Complaints Commission]が機能を開始したが、PCCの苦情申立手続規定は、従来の「提訴権の放棄制度」を廃止する一方、『委員会は、法的手続きに訴える可能性のある事案については、苦情処理を拒絶したり、延期したりする裁量権を持つ』との条項を定めた。
以上
2001年2月20日
2001年2月20日
放送と人権等権利に関する委員会(BRC)
放送番組の録画・録音の視聴請求について
BRCの審理を公正・迅速に行う上で、放送内容確認に関する東京高裁判決(平成8年6月27日)及び平成7年11月11日に施行された改正放送法(第4条、第5条)の趣旨にも鑑み、権利の侵害を受けたことが客観的に明らかな者だけでなく、その可能性を有する者でその主張に一応の合理性がある者に対しては、できるだけ視聴させることが望ましい。
以上
1999年12月22日
1999年12月22日
放送と人権等権利に関する委員会(BRC)委員長談話
「桶川女子大生殺害事件」取材についての要望
今年10月26日に発生した「桶川女子大生殺害事件」に関して、被害者の母親及び親族から、本日、テレビ局の執拗な取材に自粛を求める電話がBRCに寄せられた。母親及び家族からの訴えは以下の通りである。
「家の前に大勢の取材陣が群がり、家族の姿が映し出され外出も出来ない状況で、生活に支障をきたしている。殺害された娘の写真が度々放送され、家族の写真は映さないでほしいと頼んでも聞き入れてくれない。わが家の写せるところは全てさらけ出し、家族には小学生や大学受験を控えた子供もいるのに、話を聞かせてほしいと執拗に迫る。近所にも迷惑をかけ、このままではここに住んでいられなくなってしまう。被害者であるにもかかわらず、何でこれほどいじめられなくてはならないのか。被害者に自殺でもしろというに等しい」
BRCは、事件報道の際に度々指摘されることではあるが、今回も犯罪被害者の立場に十分な配慮をせず、被害者家族に二次的な報道被害が及んでいる事態が生じていることを憂慮せざるをえない。事件の真相を解明するための取材が必要であることはいうまでもないが、今後の取材に当たっては、上記の家族の声を真摯に受け止め、被害者及び家族のプライバシーを侵害することのないよう節度をもって当たることを強く要望する。
BRCとしては、本件の報道に対し、今後とも重大な関心を持っていることを明らかにしたい。
以上
2012年度 解決事案
「ストローアート作家からの申立て」事案 審理入り後の和解合意により解決
本事案はフジテレビが1月9日(月・祝)の『情報プレゼンター とくダネ!』で放送した企画『ブーム発掘!エピソード・ゼロ(2) 身近なモノが…知られざる街の芸術家編』について、ストローアートの作家が申し立てたもの。
企画では、ストロー、バナナ、海苔、それに石を素材とした4作品を紹介した。申立人は、数本のストローで作った組作品のヤシを1本ずつに崩し、本来飲むためのものではないにもかかわらず、飲み物に挿して喫茶店の客に出し反応を撮影・放送したこと、出演者に4作品の人気投票をさせた上、キャスターが「石以外は芸術ではなく趣味の域だ」とコメントしたことについて、「過剰で誤った演出とキャスターコメントにより、独自の工夫と創作で育ててきたストローアートと私に対する間違ったイメージを視聴者に与え、私の活動と人権を侵害した」と主張した。
これに対し、フジテレビは「演出方法を明確に説明せず、申立人に不快な思いをさせたことは真摯に反省し申し訳ないと考えている」として、放送でのお詫び案を示しメールで交渉を重ねてきたが、決着しなかった。
5月の委員会で審理入りが決まり、6月の委員会で書面審理、7月の委員会では申立人とフジテレビにヒアリングを行い、詳しい話を聞いた。ヒアリングを受けて委員会は、フジテレビがお詫びの意思を表明し、申立人に対し数度にわたり謝罪案を提示してきた経緯等もあることから、双方に対して和解による解決を打診した。
これに対し双方とも和解に応じる意向を示したため、委員会が作業を進めた結果、フジテレビは放送で演出についてお詫びし、ホームページでは演出のお詫びとキャスター発言等について見解を表明する一方、申立人はこれを受け入れ委員会への申立てを取り下げるとした合意に至り、8月21日に和解合意書を取り交わした。
その後、フジテレビは、8月23日放送の当該番組内、及び、同日から7日間ホームページにおいて合意内容を履行した。
審理入り後の和解解決は3件目となる。
【委員会コメント】
本事案において、委員会が双方の主張を十分に聞いたうえで和解を斡旋し、申立人も納得する形で早期に解決できたことは、放送による被害者の救済という委員会の使命にもかなうものと考える。
局側は、自ら反省している点は今後の番組作りにおいてぜひ活かしていただきたい。
(放送2012年1月9日 解決8月21日)