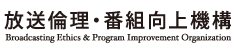意見交換会を大阪で開催
放送人権委員会は、近畿地区の放送事業者との意見交換会を10月29日に大阪で開催した。毎年1回地区単位で意見交換会を開いており、近畿地区での開催は2006年以来7年ぶりで、10社77人が出席した。委員会側からは三宅弘委員長ら9人の委員全員が出席し、前半では曽我部真裕委員が判例や放送番組をもとに報告を行い、休憩後の後半では最近の「委員会決定」をめぐって人権や放送倫理について意見をかわした。予定を上回る3時間20分にわたって議論をした。
概要は以下のとおりである。
◆三宅弘委員長 冒頭あいさつ◆
ご承知のとおり、特定秘密保護法案が国会に提案をされようとしています。サツ回りを日ごろされている報道機関の方々にとっても、テロとかスパイということで行政機関の長が認定した情報が特定秘密になるということで、これは都道府県の警察本部長まで含みますので、霞ヶ関以外の取材・報道関係者にとっても、非常に危険なものだと考えています。法案の中身を見ると、戦前の国防保安法(1937年)、軍機保護法(1941年)に似た条文があります。それはまさに戦前の治安維持法をベースにさまざまな戦時立法の中で作られた法律です。普通の戦争のできる国に舵が切られようとしている状況だと私は考えています。
ことし6月に亡くなったBPOの初代理事長の清水英夫さんが30年以上前に情報公開権利宣言というのを自ら起案されて、情報公開を求める市民運動の宣言としました。その一節に、「国民の目と耳が覆われ、基本的な国政情報から隔離されるとき、いかなる惨禍に見舞われるかは、過去の戦争を通して私たちが痛切に体験したところである」とあります。清水さんは学徒動員で出陣した経験の持ち主だから、このひと言でおわかりになったと思いますが、私どもは過去の歴史を読み解きながら追体験しなければなりません。報道機関には国家秘密のベールを切り裂き、鋭い調査報道がますます求められるのではないかと考えています。放送に求められる社会的な要請というのはこれからもますます強くなると思います。
そういう中で、私たち放送人権委員会がどういう役割を果たすのかということを常日ごろ考えています。報道に対して無用な権力介入を招かないように、取材、報道は放送の対象者の名誉、プライバシーを侵すことなく、放送倫理にもかなう必要があります。そのためのアドバイスをするという役割が、私どもの機関であると認識しています。
清水さんは、かつて放送人権委員会は「必要悪」だと言われました。私の先代の堀野委員長は、「辛口の友人」という言葉で話されました。こちらから友人と言ってもそちらから受け入れていただけるかどうか? きょうの意見交換会などを通じて友情を深めたいと思っています。
◆曽我部真裕委員の報告◆
「報道と人権-最近の事例から改めて確認する」
曽我部委員は、名誉毀損の法律的な枠組みの確認として(1)適示事実の公共性(2)目的の公益性(3)真実・真実相当性といった名誉毀損の正当化自由などの説明に続いて、裁判所の判断の基準について、最近の判例を基に報告した。
何を放送したかがポイント
まず、名誉毀損を判断するときに、何を放送したかがそもそも争いになる場合があります。番組というのは一定の長さがあるし、ニュアンスのある表現も含まれているので、番組が何を提示しているのかということを確定する必要がある場合があります。なぜそういう必要があるのかというと、1つは、そもそもこれが名誉毀損にあたるのかどうかという点、もう1つは、免責事由のときに何を証明したら真実証明になるのかという点に関連する場合があるからです。
民放キー局が埼玉県の所沢産の野菜がダイオキシンに汚染されていると報道したことに対し農家が名誉毀損だと訴えた事案で、高裁判決と最高裁判決とで、この番組が何を放送したのかということについての理解が違いました。そこが勝敗に直結したというところに注目したいと思います。
高裁判決は、このダイオキシン報道の中身の要約として、「民間の研究所が所沢産の野菜を調査したところ、1グラムあたり0.64から3.80ピコグラムTEQのダイオキシンが検出されたこと」というのが放送内容だったと理解しました。これを立証できるかという問題になったときに、1グラムあたり3.4ピコグラムTEQの白菜が1つあったので、これは「真実性あり」だと認定しました。
これに対して最高裁は報道の要約を、「ホウレンソウを中心とする所沢産の葉物野菜が全般的にダイオキシンによる高濃度の汚染状態にあり、その測定値が1グラムあたり0.64から3.80ピコグラムTEQもの高い数字があること」としました。そうすると、白菜が1点だけあっただけでは「真実の証明になりません」ということなのです。放送が何を言ったかを判断する基準は、「一般視聴者の普通の注意と見方」です。テレビの場合は、ナレーションとか効果音とかいろいろな演出があるので、それも総合的に加味して一般人の基準で判断します。その結果、最高裁は単にそういう高濃度の汚染されている野菜が少しあるというだけではなくて、全般的にあるという印象を与えたのだという理解をしているということです。
未確認情報の報道に関する異なる判例
次に、未確認情報の報道の場合の裁判所の判断を確認します。うわさであると断わったうえで、社会的評価を低下させるようなことを報道した場合に、何を立証すればいいのでしょうか。1968年の最高裁の決定は、「真実性立証の対象となるのは、風評そのものが存在することではなく、その風評の内容である事実の真否」だと判断しました。これは非常に古い判断ですが、最近になっても同様の判断があります。2005年の東京高裁の判決で、「名誉毀損の違法性の判断においては、真実性の証明の対象は疑惑の対象として指摘される事実」だ、というふうに判断をしています。疑惑報道の場合であっても、疑惑の内容の真実性を立証することが求められるということだとすると、これは報道機関にとってかなり厳しい判断です。
そうでない判断も幸いなことにあります。2002年の東京高裁の判決で、ある夕刊紙がある県の県会議員が多額の脱税をしているという疑惑を報道したことに関するものです。判決では、「立候補者にかかる事柄である場合は、民主的政治の土台としての表現の自由・報道の自由が最大限に尊重されるべき」だ、というスタンスをまず述べているのが注目されますが、それをふまえて「真実であること、真実であると信ずるについて相当の理由があることの完全な証明がなくても、疑念、疑惑として合理的な根拠があり、国民、政党、議会等あるいは司直の手によって今後の更なる真実究明をする必要があることを社会的に訴えるために、これを意見ないし論評として表明することは民主的政治の維持のために許容されるべきであり、これを報道することは違法性を欠く」というふうに示しています。
未確認情報をどう報道するか
要は裁判例は分かれているということですが、では、どのように考えるべきかというと、佃克彦著の「名誉毀損の法律実務(第2版)」には、次のように書かれています。風評形式の記事の場合は、先ほどの1968年の最高裁判決の判断方法が妥当すると解すべきではないとしています。佃氏は「その記事がいかなる事実を適示していると読者が受け止めるかの問題であって、記事の形式によって判断方法が自動的に決まるわけでない」と、「メディアとしては事実として書ける部分と、推測にとどまる部分を明確に分け、表現の仕方に注意して報じることが必要」だということです。そういう形で真摯にやっていれば、メディアが救済されることになると思われます。
これらの判決や見解をふまえると、さしあたり次のようなことが言えるのではないでしょうか。まず、最低限、「疑惑報道」であることが視聴者に理解されなければなりません。この問題は、何を放送したかということと同じで、一般の視聴者の基準で判断します。つまり視聴者がその放送を見て、これは断定的に言っていると判断するのか、疑惑報道だと理解するのか、それにかかるということと思われます。
そのうえで、疑惑報道だと理解されるようなものであったとしても、疑惑であると言えば何でも報道していいというわけでは当然なくて、次の2点が必要になります。つまり、(1)取材は可能な限りしたうえで、疑惑として合理的な根拠があること、さらに、(2)さらなる真実究明が必要であることを訴える必要があることです。これは疑惑段階であえて報じる価値があるというような趣旨です。
つまり、疑惑としての合理的な根拠が必要であり、疑惑段階で報じる価値があることというのが少なくとも必要だと思われます。現在のところ、裁判所の判断は分かれていますが、少なくとも今述べたことは満たす必要があると思われます。こうした点を後ほどの議論の参考にしていただきたく思います。
曽我部委員は、続いて裁判員制度と報道という論点から事件報道で配慮すべき点などについて説明し報告を終えた。
◆決定50号「大津いじめ事件報道に対する申立て」について◆
まず、起草担当の委員が決定のポイント等を説明してから、意見交換に入った。
奥武則委員長代行:今回の決定のポイントは、一つはインターネット上に少年の実名が判読できる画像が掲載され、その画像を放送したテレビ局の責任をどこまで問えるかということですが、名誉毀損とかプライバシー侵害といった人権上の問題を考えた時に、実際に放送されたテレビの画像では分からないわけですですから、そこでは人権侵害の問題は生じないと、そういう判断をまず前段でしているわけです。
しかし、放送が静止画として切り取られてインターネットに流れる、そういう新しいメディア状況をどういうふうに判断するかという問題が2番目の焦点になるわけです。放送された画面を勝手に切り取って、それをインターネットにアップするという第三者の故意行為は、著作権法に違反する行為であり、そういう第三者の違反行為が介在しているから責任ありませんよ、と局側は言うわけですね。それは、そのとおりだと考えざるを得ないところがある。しかし、問題はその先で、ニュースなり番組を作る人が、新しいメディア状況をどこまでしっかり考えて作らなければいけないのかという点です。この場合、特にいじめ事件という世の中にずいぶん喧伝されて話題になった事件で、少年が関わっているわけですから、その実名に関わる情報、画像の扱いは極めて慎重にしなければいけないと、その点でミスがありましたと、決定ではそういう判断をしたわけです。
それから、なぜこういうミスが起こったのかという問題ですが、実際ヒアリングで聞いても、どうしてこういうことが起こったのか、実はよく分からないところがあるんです。「そこをもっとしっかり究明しろ」とおっしゃる方もいますが、それは放送人権委員会の仕事からちょっと逸脱するだろうと思っています。決定では、全員が見過ごしたというか、考えが及ばなかったという意味で、報道現場全体の人権感覚の欠如ということを指摘したわけです。
私がテレビ局の現場の方々に求めたいのは、やっぱり一人一人が仕事をしていく中でのある種の感覚ですね、「ここは、やっぱりちょっと気を付けなきゃいけない」とか「ここまではやっちゃいけない」とか、そういう感覚を一人一人が身に付けて、判断していくしかないんであって、決定文の表現になると、「人権感覚の涵養」とか、「高度に研ぎ澄ました人権感覚」とか、そういう堅苦しい言葉にならざるを得ないのですが、結局どんなにしっかりシステムを整えて管理する仕組みを作っても、そこで働いている人間がしっかりしてなきゃダメなんですよね。結局、最後は人間だという気がしていまして、こういう決定文になったわけです。
大石芳野委員:アンケートの回答を拝読しますと、「大津いじめ事件の問題は他山の石」と答えてらっしゃる方が何人かいらっしゃって、審理をしていても新しい大きな問題だなというふうに思いました。「ビデオテープの時代でも、止めれば判読できた」というご意見もありましたけれども、結局、今の新しい時代に入っての問題だったと思います。
それで、どうして起こったかというと、やはり奥代行がおっしゃいましたけれども、機械の問題ではなく人間の問題だったかなと。なぜこの映像素材を3種類(モザイク処理したもの、モザイク処理のないもの、黒塗りをしたもの)作ったのか、局にヒアリングで聞きましたが、明確な答えがありませんでした。アンケートでは、「現場が忙し過ぎた」、「流れ作業だった」とか、「意思の疎通が不足だった」とお書きになった方もいらっしゃいますけれども、やはり、そういうことだったんだろうなと思います。というのは、局はずっと長い間この3種類を使ってきたわけですから、今回だけというわけではなく、長い間使っていた、それが今回は誰も気付かなかったというのがヒアリングでの答えで、担当の人のミスということになっていますが、一人のせいにしてしまうのは、どうなのかなと私は考えたりしています。
記者だけではなく、派遣の人も、子会社の人も、いろんな人たちが集まって放送、ニュースを作っているようですので、そういう中で一番大事なのはジャーナリスト感覚だと思うんです。これはバラエティでもドラマでも、放送に関わる人はみなジャーナリストでなければならないと私は強く思っています。落としたら割れると分かっていた器を落としてしまった原因は何だったのか、しっかり握っていなかったのか、あるいはよそ見していたのか、そういう人間の意識に関わってきますので、これは皆さんだけでなく、私にとっても大事なジャーナリストとしての自覚というか、認識というか、そういうものに関わってくるかなということを、つくづく感じております。
【謝罪放送について】
(以下、会場からの発言)
奥委員長代行:ご質問の点は委員会でもかなり議論がありました。確かに謝罪放送が一つのきっかけになった部分はあるだろうと思いますが、じゃあ、謝罪放送がなければ、ああいう形のバッシングが加速・過熱しなかったかというと、それは全く検証できないということが一つありますね。
それから皆さん、テレビ局の現場にいらっしゃる方ですから、ぜひ自分の問題として考えていただきたいんですけれども、今回のケースで言えば、テレビ局は当初は全然認識がなかったわけです。翌日の午前中、新聞社から電話が入って、「お宅のテレビの画像がインターネットに流れて大問題になっているよ」と取材を受けたんですね。その段階で、テレビ局の現場の方がどういう判断をするか。これは個人情報に関わる問題だから、テレビで謝罪しないで当事者にだけ「ごめんなさい」と謝って済ませるか。今質問された方は、そういう選択もあるのではないかとおっしゃったわけですけども、どうでしょうかね?
やっぱり自分のテレビニュースの映像が素材になって大きな問題になっている、人権問題が生じていると分かった時に、それはテレビ放送の問題としてあるわけですから、それをテレビの放送で何か口を拭っておくことは、やっぱりまずいのではないかというのが委員会の判断です。人権に関わるので、謝罪の仕方にも配慮して謝罪放送をした選択は正しかっただろうと、委員会は判断しました。
三宅委員長:ちょっと補足ですけど、局が謝罪しているということをふまえ、決定を出す前に、委員長として、委員会の総意でしたから、双方に和解で解決しませんかという話もしました。委員会の決定文が流れることによって、もう一度視聴者にこの放送の記憶を喚起させて、少年と母親がまたメディアやツイッター等でたたかれるようなことがあってはならないと思ったので、そういう配慮もいたしました。最終的には、申立人側は多少そういうことがあったとしても、きっちりした決定をもらいたいという判断をされて、和解には応じられませんでしたけども、それなりの働きかけをするという意味合いでも、謝罪放送は重要なポイントだったかなとは考えています。
- 今回の場合、相手方に謝罪放送をするというコンタクトはとったんでしょうか? 当社では間違った情報を流した場合は、まず最初に先方と連絡を取ってご意見をお聞きして、最終的にどうするか判断しています。
奥委員長代行:局は、問題を把握した段階で、もちろんその当事者に連絡する段取りを取ったようなんですけれども、つかまらず、ちょっと経ってから代理人の弁護士と話し合いができたということでした。少し待ってから、謝罪放送をするかどうか考えることができた可能性はあるんですけれど、ただ、既に新聞社の取材が入っていて、記事に書かれる可能性がすごくあるわけです。そういう時に局として何も対応を取っていないというのは、選択としてはまずかろうと判断し、速やかに人権に配慮しつつ責任を認めたということだと思います。単純な誤りについて「ごめんなさい」と言うのとは相当違う問題があり、確かにいろんなケースがあるだろうなとは思っています。
【放送自体の問題性】
三宅委員長:曽我部委員の報告にありましたが、「一般人の通常の見方」が最高裁の判断の基準です。ネット上でなくても、静止画像にしたら判読できるからプライバシー侵害に当たるのではないかという議論があることは十分承知していますが、私も何回その映像を見ても分からないんです。もう1.1秒ぐらいですから。しかも、テレビは真ん中を見ますが、ちょうど上の端なので、何回見ても分からないという状況ですので、「一般人の通常の見方」からすると、プライバシー侵害はちょっと酷じゃないかなと、それよりも放送倫理上の問題としてはっきり判断したほうが納得いただけるんじゃないかということも考えました。
明らかな名誉毀損とかプライバシー侵害の事例は、もう長年積み重ねられてきていますから、多分即座に放送局でも対応されて、委員会に来るまでに解決されているようなケースもあるのではないかと、私どもも推測しています。確かに非常に微妙なケースの申立てが多くなってきております。
そういう観点からすると、無理やり名誉毀損かプライバシー侵害かどうかを判断をするよりは、放送倫理上の問題としてこれからの放送に生かしていただくような見解を述べるということが委員会に求められているのではないかと。静止画像にできるからプライバシー侵害とするかどうかいう点について、最終的にそこは問わないという結論を委員会が出しているということを読んでいただけると、読み方として参考になるのではないかなと思います。
◆決定51号「大阪市長選関連報道への申立て」について◆
朝日放送の当該ニュースの同録DVDを視聴したあと、まず委員長と起草担当の委員が決定のポイントを説明した。
三宅委員長:短いストレートニュースですが、一番印象に残るのは、「スクープです」と言い切られたところと、内部告発者が「やくざと言ってもいいくらいの団体だと思っています」、そこのところが、やはり大きな問題点ではなかったかと考えております。
曽我部委員の報告にありましたが、噂を報道する時は、その真実証明の対象が実際の噂があるということではなくて事実証明だという判例のグループと、疑いは疑いとして合理的な疑いとして報道をすればいいという判例の2つに分かれておりますが、今回の決定はどちらの立場かというと、疑いは疑いとして合理的に判断されるべきだというところに一応立っているわけです。そういう意味では、放送局側にかなり理解を示す立場という前提条件があります。それは決定の結論でも一文入れて、「また、疑惑を報道するのであれば、取材努力を尽くしたうえで、あくまでも疑惑の段階であることが明確になるようにすべきである」という、この一文が今言った判例の立場をベースに考えているということです。ただ、冒頭の「スクープです」がかなり強烈で、どうも「疑い」という感じがしないというころが、やはりこの委員会決定になった部分だと思います。
それから「やくざ」という強い表現の論評の部分ですね,あそこでどうしても使わないといけない映像なのか、非常に気になりました。短い報道であればあるほど、脇が甘くならないようにきっちり固めていただく必要があるのではないかということを、今回警告させていただいたと考えています。
小山剛委員:今回の決定の最初のポイントは、この放送が何を報道したのかということです。放送をご覧になって分かりますように、「疑惑」という言葉が2か所用いられていますが、回収リストについては、「疑惑」ではなく、当然に本物であるという扱いになっているという印象を受けました。それから内部告発者の「やくざと言ってもいいくらいの団体」というコメントですが、非常に視聴者に与えるインパクトが強く、かつまた「スクープ」という表現も含めて考えますと、組合がこのようなことをやったということを断定している、もしかすると交通局ぐるみかもしれない、もうちょっと大きな疑惑に広がる可能性があるということを伝えたのではないかと思います。単にこのような疑惑があったとか、市議会議員が調査活動をしたと報じたという受け止め方は、多分一般的な視聴者はしないのではないかと判断しました。
それから2番目ですが、仮に名誉毀損の場合でも、免責事由が満たされれば責任は問われません。この放送自体には確実に公共性はあっただろうし、別に組合たたきというわけではなくて、公益性もあっただろうと思います。しかし、最後の「真実相当性」が、委員会に提出された資料やヒアリングでお聞きした限りでは十分なご説明が得られなかったということです。特に、相手方に対する取材をせず、あのような報道をしたところが一番問題ではないかと感じております。
曽我部委員:2点だけ申し上げたいと思います。一つはアンケートの感想を拝見してということですが、「疑惑は疑惑として報じるべきだ」とか、「裏取りが重要である」というような回答が多くて、当該局も、もちろん一般論としてはそのことは当然ご承知と思うのですが、なぜ、そういうことになってしまったかというと、やはりアンケートの中に出てくるように、一つは「スクープということで、勇み足だったのではないか」というご意見がありますし、もう一つは、今回特有の問題に関することで、大阪では現市長就任以降いろいろな出来事があり、私も近所におりまして、非常に関心を呼んで多々報道されているというのは承知しております。そういう中で、やはりある種予断のようなものが生じてと言いますか、チェックが緩やかになってしまっていた部分も、おそらくあるのかなとは思っております。放送は旬を切り取るものだともいわれますので、こういうことを要求するのはなかなか難しいとは思うわけですけれども、やはり、一歩流れから距離を置いた立場で冷静に眺める目というものが必要ないかと感じたところでございます。
もう1点、この決定は名誉毀損の問題と放送倫理の問題を大きく2つ取り上げておりますが、最終的な結論は放送倫理上の問題とさせていただいております。今回の当事者は社会的関心の高い団体で、例のリストがねつ造だったことは大阪市も正式に調査され結果を発表されていて、それが報道されていることからすれば、リストがねつ造だったこと自体は、大阪市民というか関西一円の視聴者は、事後的であれ、理解され周知徹底されているだろうと思うわけです。そういうことからすると、名誉毀損自体はいったんは成立しているけれども、結果的に相当程度というか一定程度というか、それなりには回復されているとも考えられます。
むしろ、今回の事案で今後に生かしていただくべきは、報道における裏取りの問題ですとか、やくざ発言のあの段階での使い方、あるいは続報の在り方など、決定の「5.放送倫理上の問題」で4点ほど指摘しておりますけれども、そういった点を委員会の問題意識としてお伝えするほうが、今後のためになるのではないかという立場で、名誉毀損の問題よりはこちらを取り上げたとご理解いただければと思います。
【各局の対応】
「回収リスト」に関する在阪テレビ各局の放送対応を尋ねた。
-
ABCの昼ニュースで放送され、私どももリストは入手していたので、これは業界ではありがちですが、うちも夕方からやろうかということで、基本的にはニュースの構図としては同じものを全国ネットで1回、ローカルで1回やりました。ただ、私どもがリストを入手して大阪交通労組に取材したときに、強く否定されて直ちに放送することを逡巡したという経緯がありました。現場の判断を尊重して、グッと我慢を貫けば、良かったんですけれども、それ以上我慢できずに放送したと。ABCさんとの違いは本当にわずかで、労組のインタビューを放送したということと、「スクープです」と言わなかったという、この2点ぐらいなのかなと。
ですので、記者全員に決定文の概要をメールで送って、これは他人事ではないと。特に独自ダネあるいはスクープになると、ネタを取ってきた記者やデスクは舞い上がりがちなので、そういう時こそより慎重にやらねばならないということと、やはり当事者に当たるということ、対立する側の意見を聞くという取材の基礎を改めて徹底するようにしました。
-
うちの場合は、取材による信憑性とかではなく、物理的な問題でその日のニュースに入らなかったというか、入る余裕がなかったので放送しなかったのですが、うちでも起こりうる話かなということで、決定文については報道のほうでも要約を全員にメールで配信しました。
-
結果的に2月6日は放送を見送りました。ABCさんのお昼のニュースを見まして、これはやられたなと。とりあえず、記者に対して裏が取れたら夕方のニュースで放送しようと指示を出しました。放送直前になって、現場から「組合が完全にあれはねつ造だ」という言い方をしていると、記者も心証からガセだと思うという報告が上がって来ました。組合側の声を放送してバランスが取れるか検討した結果、かえって疑惑がクロだという雰囲気に伝わってしまうだろうなという判断で、とりあえず放送を見送ろうと、そういう形になりました。
うちが最初に放送したのは、翌日橋下市長が調査を指示したというニュースで、その日の夕方の番組では、民主党のあの偽メール事件と同じようなことが起きていますと、そっちの方の目線で放送しました。
-
基本的にはあまりこのあたりを深くは取材出来てないと思いますので、おそらく放送しなかったのではないかと思っております。
-
報道の担当者がいませんので、現場でどういう判断をしたかは、申し上げられないんですが、私の知る限りでは、これについては裏を取らなければやはり放送はしないだろうと、こういうことはなかなかあり得ないかな、という部分はあります。
【当該局の発言】
【「スクープ」など放送での表現について】
小山委員: 別に「スクープです」と言ったから断定的とは言っていない。決定文6ページの(b)の最後のところで、「このことに加えて、本件放送の冒頭で『朝日放送のスクープです』と強調され、本件報道の真実性が強く印象付けられることもあわせ考えると」と論じております。「スクープです」だから断定的なのではなく、その印象がより強まったということです。
結局、この回収リストについては、「回収リストらしきもの」とか、あるいは「その疑い」といった表現はなくて、断定的な言及です。それから内部告発者についても、断定して「内部告発者」と放送されていました。そういったものがあって、「疑惑」は頭と最後の2か所だけで、サンドイッチされた中間の部分は全て断定的に放送されたと判断しました。
三宅委員長:ニュースの中で、紹介カードの問題で橋下市長に謝罪している映像がありましたね、「ああいう過去の労組のやってきた内容からすると、今回もそうらしい」という、そういう「らしさ」をある程度出せば、違う内容の放送になったんじゃないかなと実は思っています。
真実相当性の立証というのは、仮に事後にねつ造だと分かっても救済される余地がありうるところですので、やっぱり「疑い」を放送する時には、注意していただいて、決め付けない構成にするやり方があったのではないかなと。私もかつて、無罪になった被告人について報道機関が有罪を前提に放送したと訴えられ、最終的に真実相当性が認められて勝ったケースの代理人をしたことがありましたから、今回のような1分そこそこニュースでも、そういう構成で作れたのではないかという感じが体験的にしました。
坂井眞委員長代行:「スクープです」と言っておきながら、「いやいや、スクープと言っても疑いですから、間違っているかもしれません」というのでは、「スクープ」というほどの迫力はないんじゃないかという気がします。本件放送で「スクープ」と言ってもいいのですが、その場合例えば、「組合に真否を問い合わせたけれど、逃げ回っているので裏は取れておりません」ということを同時に言って、でもこういう疑いがありますと言えば、だいぶ印象は違うと思います。でも、そんな報道ではおそらく「スクープ」とは言いづらいかなと思いますし、だったらそもそも「スクープ」と言うのは止めたほうが良いという話になるのではないかという気がしています。
今の話を前提に聞いていただくと、奇妙さが分かるんですが「朝日放送のスクープです」と始まって、その後「疑いが独自の取材で明らかになりました」ではまったく迫力がないんですよ。結局、まだ「疑い」ならば、スクープとは言わないで欲しいなと。
その後、以前知人紹介カードを集めていたことが発覚して謝ったことがあると報じた上で、さらに今度は回収リストが独自に入手出来ました、そこにはこんなことが書いてありましたと。これでは、印象としては「まだ裏は取れていません」という話にはなっていないわけですよ。回収リストを入手したら、こういうことが書いてありましたと報じて、さらにその後「やくざ」という話ですから、そうすると、これは最初に「疑い」という言葉があって、最後に「組織ぐるみの疑い」とあっても、やっぱり「疑い」の報道とは受け取れないだろうと私は思います。
しかも、最後のところで、リストには政治活動が制限されている管理職が入っている、非組合員のコード番号も記されていると。だとしたら、この回収リストは組合には作れないじゃないかという疑問が当然浮かびますね。それを合理的に説明しようとしたのか、最後に「組織ぐるみ」と指摘をする。しかしこれだと、組合じゃなくて交通局の「組織ぐるみ」ということになって、もともとの「労組がリストを作成した」というニュースではなくなっちゃう。どうも奇妙な、詰めが甘い報道に思えてしょうがないんです。
田中里沙委員:「スクープ」とは業界用語であって、一般の人はあまり敏感にかつ深く反応するものではないと感じています。新聞の「号外」は社会共通の話題になる内容ですが、テレビの「スクープ」はその意味合いがわかりづらい。もちろん大切で価値のあるものですし、記者であれば一度はスクープを取りたいと思うのが普通ですが、この受け手との「温度差」をふまえて使用してもらってはいかがかと考えています。
私は日常の仕事で企業の広報の方と接することがよくありますが、皆さんマスコミが呈する「疑惑」自体に非常にナーバスになっています。「疑惑」とマスコミが報道すれば、世間一般の方はそのことをクロあるいはグレーだと受け止めがちです。報道されたことはその時点における事実となりますので、やはり慎重に発信していただかなければいけないだろうと思っています。一方で、視聴者は速報性を求める面もありますので、疑惑を報じる際には、締めくくりのところで、「現在このような疑惑があります。取材先はノーコメントで取材にも応じない段階なので、追及していきます、あるいは調べています」などと、そのような状況を示していただければ、多分視聴者は「疑い」はこの後どうなるだろう、という見方をするのではないかと思います。
林香里委員:決定に対する朝日放送の放送を見て、反省していらっしゃらないのではないかと、かなりショックを受けていたんですが、今日だいぶ印象が変わりまして、私自身納得しております。
そしてもう一つ、朝日放送の皆さんにお礼申し上げたいのは、今日実際のニュース映像を見せていただいたことです。映像を見ることで議論も活性化するし、皆さんもいろいろ考えることが出来ます。多分作られた方はもう1回見るのも嫌だろうと思いますので、映像を許可していただいたことを、私はありがたく思っています。
【続報について】
小山委員:手元にある原稿(3月26日の朝日放送のニュース)を見てみますと、まず前説として、「去年の大阪市長選挙の際、大阪市交通局の労働組合の名義で、当時の市長の支援リストが作成されていた問題で、大阪市はこのリストが交通局の非常勤職員によるねつ造だったと発表しました」。本文に入って、「この問題は去年の大阪市長選に絡み、交通局労組の名義で作成された平松前市長の支援カードの回収リストを、内部告発者が維新の会の市議会議員に持ち込み、市議会で追及されたものです。リストには、交通局職員1800人分の職員コードや氏名があり、『協力しないと不利益がある』などと書かれていました。これに対して組合側は『労組が知り得ない情報も含まれていて、文書作成には一切関与していない』と全面的に否定、被疑者不詳のまま刑事告発しています。その後交通局は調査を進めて・・・」ずっとこんな感じの、要するに事実関係の羅列なんですね。
あれだけ強い、インパクトの強い報道を行った当事者という感じが全然しないわけでして、これによって内容的には最初の当該報道は事実上、修正されていることになると思うんですけれども、やはり報道が報道だけに、何月何日にこういう形で報道したものの、その回収リストがねつ造であることが明らかになったといった形で、やっぱり当該ニュースを引用して伝えるべきではなかったかというのが委員会の判断です。
【団体からの申立てについて】
三宅委員長:団体からの申立てを審理したケースは過去にもございまして、資料に「委員会決定事案と判断内容」というのがありますが、決定43号の「拉致被害者家族からの訴え」、これは拉致被害者家族会からの申立てで、団体からの申立てを審理したケースの最近のものとしてはそれがございます。
それから、さらにさかのぼりますと、「幼稚園報道」という決定2号の申立人は、幼稚園と理事長、保護者。それから決定17号の「熊本・病院関係者死亡事故報道」は病院を運営する医療法人と理事長が申立人になっていたということで、今回が初めてのケースではないということを、まずご理解いただければと思います。
で、今回の場合は団体としてかなり規模が大きかったので、そのところをどう判断するか、申立てがあった段階で考えました。決定の5ページの「委員会の判断」の「1.本件申立てについて」のところに書いているつもりでございます。その後ろの方ですかね、「また、本件放送は、本組合による重大な不正行為の告発の主旨を含み、本組合及び組合員個人らの信用、名誉、名誉感情等の」というのがありますね。ここのところが、どうもやっぱり腑に落ちなかった。「やくざと言ってもいいくらいの団体」というところは、結局組合員が皆やくざだというようなニュアンスの、侮辱的な表現をここに含んでいると判断すると、この辺については、非常に「深刻な影響を及ぼすおそれがある内容を含むものだった」という判断をして、規模は大きいけれども、「救済を検討する必要性が高く」と。次の段落の「委員会の過去の判断をふまえ」は今言った事例もありますよということをふまえ、「以上の事実関係を総合的に考慮したとき、本件申立てについては、救済を検討する必要性が高く」ということで、「本組合の団体の規模、組織、社会的性格等をあわせ考えてもなお、委員会において権利侵害や放送倫理上の問題の有無について審理することが相当である」と判断をしたということです。
書記の個人としての申立てについては、別件の申立てということは確かにそうですが、その後ろに書いてあるように、本組合の書記の立場として被害を受けているということだったので、審理する必要はないということで、仲介、斡旋まではする必要もないという判断が同時にされているということです。
なかなか詳しくも書きにくいので、決定ではこういう具合にお答えしていると、ご理解いただければと思います。
◆その他の委員会決定について◆
【決定47号「無許可スナック摘発報道への申立て」】
奥委員長代行:どこかに線引きがあるということではないんですね。略式命令で50万円の罰金を払っているじゃないか、これが軽微な犯罪と言えるのか、とアンケートに書いていらっしゃる方がいますけれども、略式命令で50万だから軽微だとか、あるいは懲役5年だから軽微じゃないとか、どこかに線引きが出来るという話ではなくて、これはスナックのママさんが、ちょっと勘違いをしていたのか、風俗営業法の許可を取っていなかったっていう事案ですね。
それを、もう執拗に彼女の全身からアップから、捜査員と受け応えする場面とか、捜査車両に乗り込む場面とか、1分何秒ぐらいのニュースのうちで、申立人の映像が37秒だったか、ほとんど登場するという、つまり風俗営業法違反の無許可営業についてのニュースとして、これだけ顔をさらすというのはやり過ぎじゃないか、という話なんですね。じゃあ何が軽微で、何が軽微じゃないか、それは個々の報道にあたっている人間が判断出来る問題であって、判断しなければいけないだろうと私は思います。
小山委員:ちょっと補足ですけども、この風俗営業法の無許可、無届けの件数は、この事案の神奈川県でも多数発生しております。また、別に近年増加しているわけではなく、横ばいか、もしくは減少している、その意味でもあちこちにたくさんある事件の一つに過ぎないんですね。風営法関係の摘発というのは相当の件数がある。本件は性風俗というわけでもない。それなのに、ここまで放送でやるのかと。
あと、罰金50万という金額は大きいように見えるかもしれませんけど、専門家の話を聞きますと、それはその間に得た収益を没収するという趣旨も含んでいるとのことで、そのようなことも少し考慮したということだったと思います。
【決定48号「肺がん治療薬イレッサ報道への申立て」】
市川正司委員:民間放送連盟の報道指針の中に「視聴者・聴取者および取材対象者に対し、常に誠実な姿勢を保つ」という1項目があり、取材対象者との関係という問題も、一応視野に入っているということが、まず一つあります。
この番組では、2002年当時イレッサの被害者であった娘の父親の申立人と、2007年頃にイレッサの副作用情報を充分認識して服用していたという別の患者さんを、5年以上経っているにもかかわらず同列に置いて、申立人はどうしてそんな損害賠償訴訟をやっているのか、という捉え方をされかねないような報道の仕方をしたということで、委員会は構成上の問題を指摘しています。しかし、若干今までの案件と違いまして、誤った報道、明確な誤認であるとか、あるいはプライバシー侵害、名誉毀損と明確に言えるという部分はなく、そういう意味で非常に判断が難しいところでした。
委員会の多数意見としては、問題はあるものの、やはり構成上の問題で人権侵害や放送倫理違反には踏み込めないだろうという理解です。それに対して少数意見は、先程の信頼関係の問題をより深く重く捉えて、申立人にとっては自らの思いを誤って伝えられた、あるいはそういう可能性があったという点で、放送倫理上問題があったと考えたということであります。そういう意味で、多数意見も少数意見も取材の過程だけではなくて放送内容との関係も含めて、取材対象者との信頼関係を喪失したと、ここの部分は申し上げていると、こういうふうに理解いただければと思います。
【決定49号「国家試験の元試験委員からの申立て」】
◆人権や放送倫理をめぐる質疑応答◆
事前アンケートで寄せられた質問について、委員に回答してもらった。
【桜宮高校の体罰事件の実名の扱いについて】
坂井委員長代行:これは、おそらく基準は明示できないというのが共通意見だと思います。刑事事件の報道なので、実名がだめだということは法律的には言われてない。だけれど、例えば日弁連は原則匿名にするべきだと、完全にとまでは言ってないですけど、原則匿名にしろと言っています。
それは、刑事手続き的には無罪推定があるからですが、原則無罪推定と言っても、犯罪の重さだとか、被疑者の立場で、全然利益状況が違うわけです。少年だったら少年法で保護されるわけですし、これがまた汚職事件か何かだったらまた違って、地方自治体の普通の公務員だったのか、それとも中央官庁のいわゆる官僚と言われる人なのかで変わってくる。おそらく犯罪報道をする時に公益目的が否定されるということはないので、公共性の重さということが、ケースごとにそれぞれ違って来るということですね。
では、桜宮高校の事件はどうかというと、一教員だということは確かです。だけれども、内容はすごく重いものがあるということで、現場の皆さんが悩まれるのはすごく良く分かります。教師が生徒に暴力をふるうということは、あってはならないので、一教員の行為であってもそれは書くべきだと。だけど、こいつは悪い奴だという方向で報道が過熱した状況で、要するに水に落ちた犬をたたけ、みたいな話になると、大きな副作用が出ることがあるんですね。報道してもいいけれど、そこで実名を大々的に報道することによって、どういうマイナスがあるかということも含めて考えて、そこから先は、それぞれが比較考量して、判断して行くことになるんじゃないのかなと、こういうふうに思っています。
【事件・事故報道の際の建物の撮影】
三宅委員長:『判断ガイド2010』をお持ちの方は、314ページにかつての事務所等の撮影についての委員会の判断が示されています(決定35号「"グリーンピア南紀"再生事業の報道」)。建物の外観や肖像が映ったんですけれども、「事務所等の撮影が無断で行われたとしても、放送された映像によって何らかの権利侵害が生じるなど、特段の事情が存在しない限り非難に値するとは考えられない」と。「当委員会決定においても、肖像権の侵害となる行為があった場合でも、報道・取材の自由が民主主義社会において国民の知る権利に奉仕するという重要な意義を有することから、当該取材・報道行為が公共の利害に関する云々」ということで、肖像権の侵害の違法性はないというような判断とかも並べ立てて、建物の外側から撮ったことについては、まったく問題ないというようなケースもございます、という紹介をまずしておきましょう。この時は、確かビルの映像とその窓から中がちょっと見えたんじゃなかったかと思いますが、その映像自体について、このケースの時は問題ないとしました。だいぶ前のケースですが、一概に建物の外観映像が撮れないかというと、そういうわけではないと、まず言っておきましょう。
三宅委員長:先ほどの、実名報道を書類送検のときからするのか、在宅起訴のときからするのかと一緒で、容疑者のプライバシーがどの程度保護されるものか、犯罪者として明らかになった事実との関係上、公共目的と公益性があるということで、名前を明らかに出来るなり、プライバシーの侵害も制約されて致し方なしと言えるのかどうかという、微妙なケースだと思いますね。