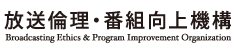中部地区「意見交換会」を名古屋で開催
放送人権委員会は、10月7日に中部地区の放送業者との意見交換会を名古屋市で開催した。中部地区での開催は6年ぶりで、御嶽山の噴火、前日の台風と慌ただしい取材・報道と重なったが、31局から88人が出席し、意見交換会の出席者としてはこれまでで最も多くなった。委員会からは、三宅弘委員長ら委員8人とBPOの飽戸弘理事長らが出席した(委員1名は台風による交通への影響で欠席)。委員、役員の紹介に続いて、三好晴海専務理事がBPOと委員会の役割や意義をビデオを交えて説明し、刊行した『放送人権委員会 判断ガイド2014』の紹介をしてから意見交換に入った。前半は今年6月に「委員長談話」として公表した「顏なしインタビュー等についての要望」、後半は「大阪市長選関連報道への申立て」と「宗教団体会員からの申立て」の「委員会決定」を取り上げ、予定を超える3時間20分にわたって意見を交わした。主な内容は以下のとおり。
◆三宅委員長 基調報告◆
『判断ガイド』に少し触れながら、お話をさせていただきたいと思います。私が9年前に委員になって最初に判断をしたのは、2ページの「若手政治家志望者からの訴え」です。
それ以降の「委員会決定」を見ますと、「放送倫理違反」、「重大な放送倫理違反」、「放送倫理上問題あり」とありますが、「人権侵害」と判断した決定は私が委員になる前の「バラエティー番組における人格権侵害の訴え」のあとはありません。先ほどのBPOの紹介ビデオで「委員会は人権侵害を判断する」と言っていますけれども、実際にはほとんど放送倫理の問題を取り上げてきたということがお分かりいただけると思います。
ただ、「放送倫理違反」と言ったり「放送倫理上問題あり」と言ったりして、各局から分かりにくいというご意見がありましたので、「放送倫理上問題あり」に統一し、4ページにあるようなグラデーションを定めました。「人権侵害」と「放送倫理上重大な問題あり」が「勧告」、一番下の「問題なし」と表現や放送後の対応等について局に「要望」するというのは「見解」です。「勧告」はいわばクロ、「問題なし」と「要望」はシロといいますか、セーフの範ちゅうに入るわけですが、その間に「放送倫理上問題あり」の「見解」というのがあります。「放送倫理上問題あり」は灰色、グレーですね、最近の申立てはグレーというのが多い、このグレーをどう判断するのか、非常に悩ましい問題が多々あるわけです。
『判断ガイド』の104ページに、「放送倫理違反」、「放送倫理上問題あり」というのは、何をもって判断しているかというポイントとして、「事実の正確性」、「客観性、公平・公正」、「真実に迫る努力」、「表現の適切さ」、「誠実な姿勢と対応」の5つを挙げております。これはどこから来るかというと、「放送倫理基本綱領」や民放連の「報道指針」、NHKの「放送ガイドライン2011」に書かれている倫理規範を参考にしながら判断しているということです。委員会はあくまで局側で作っていただいたものによって判断をしているというところを、ご考慮いただきたいと思っております。
お手元の資料にございますように、「大津いじめ事件報道に対する申立て」は2012年7月5日と6日のフジテレビの『スーパーニュース』内で各1回、大津市の中学生いじめ事件の報道に際して加害者として民事訴訟を起こされている少年の氏名を含む映像を放送したという事案です。民事訴訟の準備書面が放送され、少年の氏名が瞬間的に画面に出るのです。テレビは大体真ん中を見ますから、瞬間的に1秒、2秒弱見るだけでは分からないんですね。どこに出ているか、ちょうど画面左上の端っこですね、静止画像にして見ると少年の名前が出ていて、そこだけ消す処理を誤った。それがインターネットにアップされて少年の名前が広まったということで、ヒートアップする現象の中でどう判断するか迫られたわけです。
ここでは、新しいメディア状況の中で放送倫理上の問題が出てくる。最近は重要なニュースは各社のホームページに映像が出ます。わたしどもの判断は放送番組、放送された番組が対象ですが、これまでの審理を通じてホームページにアップされた期間は同じように審理対象になるという判断が大体固まっていますので、ニュースをホームページに載せると申立ての可能性が広がるという認識を持って対応していただくことが必要かなと考えています。
◆「顔なしインタビュー等についての要望」について◆
三宅委員長
「顔なしインタビュー等についての要望」について、作成の経緯とわたしどもとして何を言いたいのか、ご説明をしてまいりたいと思います。
「大阪市長選関連報道への申立て」は「まずは朝日放送のスクープです」から始まって、ポイントになるのは、ちょうど真ん中あたりの内部告発者のインタビュー「正直恐怖を覚えますね。やくざと言ってもいいくらいの団体だと思っています」の部分です。このインタビューは右肩後ろ側から撮っているいわゆる顔なし映像ですね。この事案を判断するにあたって、今指摘したスクープという強い表現と、「やくざと言ってもいいくらいの団体」というコメント、論評ですね。そして、申立人の大阪市交通局の労働組合は非常に人数も多いし、どうしたものかと。後ほど説明があると思いますが、これを判断しました。
もう一つ「宗教団体会員からの申立て」、きょうのアンケートの中で、大体どこの場所のどの高校に通ってA市内の国立大学に進学する人間の特定はあまり難しいことではないと、ドキッとしたという回答があったんですけれども、ボカシのかけ方が弱いですから、卒業式の時に4人の友人と写真を撮っている映像が出てくるんですが、脇の2人の女性の着物の柄が大体分かりますから、あの時誰それと撮った自分があの着物を着ていたということで特定されてしまう可能性がある。我々の判断は可能性の判断でいきますので、そういう問題が出てくる。なおかつ、アレフ脱会のカウンセリングを受け思春期の悩み等から信仰に至ったことを話す状況を、カウンセラーのみの了承のもとで隠し録音し音声を変えたうえで放送した。プライバシー侵害との兼ね合いが一つ問題になりました。
意見交換会では、ここ数年毎回顔なしインタビューについてどう考えるかということで、意見交換をさせていただいて、だいぶ機も熟してきたと考え、今回委員長談話を出させていただいたということです。
I.情報の自由な伝達と名誉・プライバシーの保護など
内容に入りますが、「I」は、取材・放送の自由のなかで、特にプライバシー、名誉、肖像など他人に知られたくない個人の法益、権利利益を保護していくということとの調整、そういう原則的な部分を書いています。
冒頭の文章は、私がかつて法廷でメモが取れないと訴えたアメリカ人弁護士の裁判の代理人を務め、最高裁の判決でもらった一文を引用しました。「個人として自己の思想及び人格を形成、発展させ、社会生活の中にこれを反映させていく」と、自己実現と呼ばれていますが、表現の自由の非常に重要な趣旨の一つです。後半部分は「民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保を実効あるものとするため」、これは自己統治といわれる表現の自由のもう一つの重要な要素、趣旨の部分が、まさに放送関係者が担っている役割のバックボーンとしてあるということを、まずはっきりさせていただくことがよいだろうと考えたわけです。
ちょうど2003年にBPOが発足するころ、個人情報保護法が「治安維持法以来の悪法である」とメディア全体が反対した中で制定された経過があります。その個人情報保護法の1条には高度情報通信社会におけるというような一文があり、「大津いじめ事件報道に対する申立て」の決定では「新しいメディア状況」と書きましたが、そういう社会状況の変化の中で、とりわけ「他人に知られたくない個人のプライバシー、名誉、肖像などみだりに侵害されることのないよう保護すること」の必要性と自由な情報の伝達との適正な調整を図るという点が、日々放送や取材にあたっていただく基本的な考え方のベースにあるのではないかということを明らかにしたわけです。
II.安易な顏なしインタビューが行われていないか
そのような基本的な考え方をふまえて問題提起をした部分です。「知る権利に奉仕する取材・報道の自由の観点」、これは冒頭の「I」のところの第1文を受けているところですが、「取材・放送にあたり、放送倫理における事実の正確性、客観性、真実に迫る努力などを順守するために、顔出しインタビューを原則」とする。この事実の正確性、客観性、真実に迫る努力というのは、先ほどの『判断ガイド』の中に整理して書いた放送倫理の基本的な部分だということをふまえていただければと思います。
この委員長談話を出すにあたって、在京のキー局の報道マニュアルの中で顔出しインタビューと顔なしインタビューをどういうふうに使い分けているのか、わたしどもは見させていただきました。各局では顔出しインタビューを原則とし、例外として顔なしを認める場合についてルールを定めていることを確認したわけです。さらに、海外のデータを集めたわけですが、ドキュメンタリーとかニュースを見ると、正面から語っている映像が非常に多くボカシはほとんど入っていないということで、ボカシを日本の社会現象として見るべきなのかどうか、少し気になったところです。例外として顔なしインタビューをするにあたって、国際通信社傘下の映像配信会社が理由を付記したうえで配信したりするケースもあり、また法務部と社内複数の関係部局の承諾も義務付けているというようなところもあり、例外の顔なしには非常に制約がかかっているということを見させていただきました。
「とりわけ、地域の出来事について、周辺住民のインタビューをする際に、特に匿名にしなければならない具体的な理由が見当たらないにもかかわらず、安易に、顔なしインタビューが行われてはいないだろうか」という部分ですが、今年1月に1週間、夕方の在京キー局のニュース情報番組を全て録画してチェックをする作業をしました。時間の関係であまり詳しくはご説明できませんが、場合によっては同じ人がある局では顔が出ているけれど、ほかの局では顔なしになっているというようなものもありまして、事案だけではなく、局側の対応によっても様々なケースがあると分かりました。どうしても顔を隠さなきゃいけない理由はないんじゃないかというものがかなり散見されました。犯罪報道の場合ですと、加害者に関わるような証言というものは、もちろんボカシを入れたり顔なしの映像にするということは当然あると思いますが、もう少し事案の内容によって検討すべき要素があるのではないかという問題提起をしました。
III.安易なボカシ、モザイク、顏なし映像はテレビ媒体の信頼低下を追認していないか
バラエティー番組では色を変えてホワーッとした感じでボカシをかけた顔なしがありますが、それに報道情報番組も引きずられているんじゃないかという警告を発したわけです。
IV.取材・放送にあたり委員会が考える留意点
先ほどの放送倫理のあり方をふまえ、一つ目に「真実性担保の努力を」として「安易な顔なしインタビューを避けて、可能な限り発言の真実性を担保するため、検証可能な映像を確保することなどの努力を行うことが大切ではないか」というところを出しました。先ほどの「大阪市長選」の「やくざと言っていいくらいの団体」と言う内部告発者の映像は顔なしで後ろから撮影され、彼が提供した「回収リスト」も自分でねつ造したものだったが、それについて裏付け取材もされていなかった。そういうところから、本人が語っている映像を撮っているときに、もしも「正面からちょっと撮りましょう」と言っていたら、そういうごまかし、ねつ造が防げはしなかっただろうかということも考えなきゃいけないということで、この点を一つ目に考えたわけです。
それから、事件現場の限られた時間内で、どうしても顔なしインタビューになってしまうと現場の方からは言われるわけですね。現にこの談話について「よく言っていただいた」という声と、現場のほうから「それじゃあ、取材、なかなかできないですよ」とか「現場感覚からズレているんじゃないですか」というようなご意見もいただきました。
それはそれとして、できる限り「取材対象者と最大限の意思疎通を」図っていただいて、できる限り顔出しを原則とする基本的なスタンスを考えていただきたい。
もちろん、「放送倫理基本綱領」にありますが、「情報源の秘匿は基本的倫理」も確認もしなきゃいけない。じゃあ、どっちを向いてどう判断すればいいのか、それは現場で考えていただくというのがこの委員長談話ですので、考えるべき筋道と考えるべきポイントを明らかにして、日々の取材の中で、その場その場で考えていただくという趣旨です。
それから放送のあり方ということで、先ほどの「大津いじめ事件」にありますように、「デジタル化時代の放送に対し、インターネットなどを用いた無断での二次的利用等が起こりうる可能性を十分に斟酌したボカシ・モザイク処理の要件を確立すべきである」という点で、新しいメディア状況に対応した留意点を特に考えていただく必要があるでしょうと。
「プライバシー保護は徹底的に」と。「中途半端なボカシ・モザイク処理は憶測を呼ぶなどかえって逆効果になりうることに留意すべき」ではないかと。できる限り真実に迫る取材をしていただきますが、放送に当たってプライバシーを保護するとなったら、もう思い切ってボカシをきっちり入れてもらうということもありうると。さっき言いましたように「宗教団体会員からの申立て」では本人のボカシの入れ方がちょっと弱い、周辺の友だちのボカシも弱いんじゃないかと。「大津いじめ事件」では、例えばいじめのあった学校全体はかなりボカシが入って、ある程度学校というイメージがあって、それから窓や校舎をアップにしたボカシのない映像が出たりする。その辺のボカシの入れ方とか特定されないような工夫は、かなりきっちりされていたんじゃないかというのが私の個人的な感想です。
そういうことをふまえて、場合によっては「放送段階で使わない勇気を」ということもあっていいのでは。いい映像が撮れると、「ぜひ使いたい」という話にもなりますが、プライバシー、名誉、肖像権の保護を考えると、場合によってはその映像を使わないという決断もされてもよろしいのではないかという点です。
それから「映像処理や匿名の説明を」のところは議論もあります。理由を注記すると、かえってボカシを推進することになりはしないかというご意見もあると思いますが、これは私の現場感覚で言うと、長年政府の情報公開の制度化を求めて、その運用の改善を求めてきた立場からすると、やはり「原則公開、例外非公開」。この原則と例外の立場をはっきりしたほうがいいという点からすると、映像処理や匿名の理由の説明を工夫してみるということも、これから各局で考えていただくべきところではないかということです。
今日のアンケートを見ますと、まだ社内ルールのないところもございますが、ぜひ「局内議論の活性化と具体的行動を」と、問題提起型の委員長談話という趣旨で書かせていただきました。
V.行き過ぎた"社会の匿名化"に注意を促す
先ほど言いましたように、個人情報保護法ができてから、警察取材が非常にやりにくくなったとか、顔なしを求める市民が非常に増えた、個人情報保護法はなかったほうがいいんじゃないかというような議論もあります。さらに特定秘密保護法ができて、政府が秘密指定したものはおそらく情報公開でも出ないし、リークを求めると、それ自体で処罰される可能性があり、取材・報道が非常に萎縮する、一方、政府自体はこれから共通番号という鍵を持って情報を全て集約する。政府はきっちり情報を持っているけれども、一般市民は無防備で、なおかつボカシのある社会を望むということになると、冒頭で述べた、社会全体が人と人が互いに知り合って意見を交換する中で人格を高め、民主政治を発展させるという趣旨から遠のいていくのではないかということも考えまして、最後に「行き過ぎた"社会の匿名化"に注意を促す」という点を市民にも向けたメッセージにしたいということで、テレビ局関係者のみならず取材対象となる市民の方々にも信頼関係に基づく十分な意思疎通というものを考えていただきたいという談話にいたしました。
林委員
委員長からご説明がありましたように、私どもで今年の1月の2週目の13日からの週の夕方のニュース情報番組の全てをかなり詳しく精査してみました。委員長談話はこの調査に基づいております。1月13日の週は神奈川県の相模原で小学校5年生の女の子が行方不明になるという事件がありました。このような犯罪報道には、顔なし映像が使われることが多いので、この事件を事例に考えてみました。
お手元に1枚の紙をお配りしました。書かれているのは、女の子がまだ見つからなかった時の12日、13日に放送された近所の方のインタビューのコメントです。「1 早く無事に見つかってほしいです」、「2 無事に見つかってくれればいいなと思ってんだけど」、「3 一日も早く見つけてあげたいと思ってね」、「4 とにかく心配で、一日も早くっていう気持ちです」、「5 親御さんの気持ち、考えると、やっぱり、何て言っていいのか」。このコメントには、実は「顔出し」と「顔なし」があります。答えは、1番と5番が顏なしです。コメントだけ取り出しますと、なぜ顔なしだったのか、理由が分かりません。特に1番と2番のコメントはほとんど同じ意味なのに、1番を顔なしにしているということは、判断としてどうなのかなと思っています。
もう一つ、気づいたのは、顔を出してもいい方は、複数の局で同じようなコメントをして使われているんですね。ですから、顔を出していいという方に取材が集中してしまう、そういう現象も起こるわけです。
さらに、夕方のニュース情報番組全体の調査で明らかになったことは、目玉として、だいたい20分ぐらいの調査報道というんですか、独自取材のニュースがあります。たとえば、リフォーム・トラブルとか結婚詐欺とかが、その週にはありました。こういう話題では、なかなか顔を出してくださる方がいないというのは分かりますが、この類のニュースですと全編、ほぼ全員に最初から最後までボカシがかかっている例が散見されました。顔の部分に赤や黄色の風船がバーッと飛んでいるボカシの画面を見ると(笑)、ちょっと気持ち悪い気がします。好奇心をそそられるテーマでもありますが、報道の責任とのバランスを考えてほしい。
以上、夕方のニュースを素材に、テレビの信頼と報道のあり方について問題提起したいと思いました。
名古屋のテレビ各局の発言
A社 取材を受ける人にとってみると、顔を出して発言していい人もいるし、顔はできれば出してほしくないけれども質問には答えてもいい人、いろんなケースがあるということです。その都度いろんなケースがあるということですから、その辺は記者の力量でもあり、制約された時間の中でどこまで頑張って取材するかということにもなってくるかと思うんですけれども、現場で日々いろいろ悩みながらやっているというのが現状かなと思います。
B社 日本の国民性みたいなところもあって、理由は分からないですけれども、コメントの内容如何に関わらず、顔を出したくないという人は出したくない。それと記者の誘導というか、最初の話の持って行き方ですね。多分、若い記者はかなり控えめに「まあ顔なしでもいいですけど」と言うようなことがあるかもしれません。それは、僕らの教育の行き届かないところだと思うんですけれども、基本的にはそういうのを説得して、顔出しでコメントを取る指導はしているつもりです。ただ、顔は勘弁してと言う人ほど、またいいコメントを言っている場合もあるし(笑)、その辺なかなか難しいかなと私自身は思います。
C社 常々気になっていたことでもありましたので、弊社内でニュース部門の記者とカメラマンがどういう認識でいるのかアンケート調査を行いました。やはり以前に比べて顔出しを嫌がる人が増えている、つまり、10年、20年前に比べると、「顔は出さないでほしい」と言われる可能性が高くなっていると感じている者が多いということが読み取れました。その理由はなかなか難しいんですけれども、やはり、インターネットやSNSの発達によって、自分の画像が思わぬところで拡散するのではないかというようなことへの懸念が一つあるのではないかと。もう一つは、昔に比べるとメディアを見る目が厳しくなっている、冷たいというか理解が少ないというか、漠とした感触ですけれども持っております。そういったことがメディアに自分の顔を晒すことへの抵抗感として表れているのではないかなという気もしております。
今年上半期の弊社のニュース映像2,647本のうち、46本顔なしインタビューがありました。一般の住民の方を顔なしで撮ったものが46本のうち15本ありまして、その15本中12本は明確に顔出しを申し込んだにもかかわらず、拒まれたものでした。また2本はいずれも殺人事件に関する近所の住民のインタビューで、やむなく顔切りにしたということで、安易に顏なしが行われたというケースは感じられませんでした。
D社 御嶽山の噴火で、私たちは遺族の方、周りの方々の取材に入りますが、まず誰も受けてくれない。「遺族の気持ちを考えろ」とか「何を聞きたいんだ」みたいな形でだいたい追い払われる。いろいろ聞いていくと、話していただける方はいるんですが、そういう方はいろんなリスクを負われることになる。顔出しで話した場合に、「あの人は顔を出してどんなふうにしゃべった」とか「こういうことをしゃべった」とか近所で言われる可能性があるかもしれないですし、ネットなどに悪意を持って使われるケースもあるのではないかと。「顔は出せないけれども、お話します」と言われれば、その前提で取材をする。聞けることがあるのであれば、取材しないよりも伝えることのほうに意味があるのではないかと考えるケースが非常に多く、悩みながら、それでも声を拾いたいと努力をしています。
E社 「宗教団体会員からの申立て」は、非常に踏み込んだ内容の番組だと勇気に感嘆したんですね。もちろん安易なボカシは如何なものかというものに関しては、私もそのとおりだと思いますが、委員会の判断はボカシが甘いんじゃないかと逆に出ていますよね、そういうことがあると、特にニュースなどの現場判断においては、「ちょっと危ないから、もうこれはボカシをかけちゃおうぜ」ということになりかねないとも感じるんです。そこは矛盾というのか難しい問題だと感じております。
G社 社内のガイドラインは「取材相手の権利保護が必要と判断される場合を除き、顔出しを基本とする」という形で明記し、徹底してやるよう指導しているつもりですが、実際には本当に吟味しなければいけないケースがかなりあります。
例えば今回の御嶽山の噴火の場合で言いますと、原則として取材相手の権利保護については本来あまり考える必要はないケースだとは思うのですが、でも、放送に出ている部分では顔出しになっていないケースがあります。一つは、自分が生き長らえたことに対する負い目を感じている方がいらっしゃって、親子で御嶽山に行ってお子さんを亡くして自分だけ帰ってきたとか、グループで行って助けることができず自分は生きて戻ってきている、そういう人は、なかなか顔は出せないけれども話せる話はあると。逆に、先週土曜日に御嶽山の噴火を緊急に放送しましたが、同じように仲間と行って助かった人が出てきました。この人は顔出しはOKで、その代わり名前は伏せてほしいと。ネット社会の中で検索されて嫌がらせを受けたりするケースがあるんですけれども、この人のように自分の思いをやっぱりきちんと伝えたいので、顔を出して取材を受けたいという方もいらっしゃったことは、ちょっと付け加えておきたいと思います。
大石委員
皆さんのお話を伺って、本当にいろいろと苦労なさっている、悩んでいらっしゃることがよく伝わってきました。私も写真家として、顔出しの写真を撮らなければならないことがほとんどですけれども、どうしてもダメといわれる時は、やはり話し合いをしたり、何日も通ったりとか、やはりある種の努力はせざるを得ない、相手が分かってくれなければ、こちらは写真を撮れない、写真が撮れなければ、どんなに立派なことを言っても何もならないわけですね、私の仕事は。
テレビも映像が勝負だと思うんです。写真と違って音がありますから、そこはちょっと羨ましい部分でもあるんですけれども、やはり映像が勝負ですから、顔が撮れなければどうするかというところを、もう少し考えてもいいんじゃないかという気がしますね。私もどうしても拒否された時は、真正面の顔がたとえ撮れなくても、その人だということがある程度は伝わるような映像、私の場合は写真を撮るように努力したりします。テレビと写真、初対面の人たちに向き合って報道するということにおいては変わらないわけですから、皆さんの苦労は私の苦労でもあるんですけれども、もう一歩を踏み込んで考えなければならないと思います。被写体の人権を尊重するにしても、外国と日本はどうしてこんなに違うのかと、今もあらためて感じながらご意見を聞いていました。
会場からの発言
私は今視聴者対応をやっております。昔は「何で顔を出さないんだ」みたいな意見が来たんですが、逆に今は「どうして顔を出すんだ」、「あんなふうに晒してしまっていいのか」というような意見が結構来るようになっている。やっぱり空気と言いますか、世の中全体が匿名社会に傾いてしまった上に、それを我々が"受け入れる"というところが変わってきている。世の中の雰囲気、顔なしが普通だとまでは言いませんが、個人情報とかプライバシーとかが取り沙汰されて、意識が変わっているような感じは視聴者対応をしていても感じられるところです。
坂井委員長代行
ここ10年以上ですけれど、インターネット上の誹謗中傷の相談がすごくあります。どんどん拡散してしまいますし、消えて無くならない。例えば「2ちゃんねる」の問題が昔よくありました。相手を実名で特定して自分は匿名で発信する。ある意味で非常に卑怯な、自分の発言には責任を持たないで人を傷つけるという行動なわけですね。
委員長談話にもありますけれども、取材対象者を実名、顔出し放送するということは、その発言内容に責任を持ってもらうという部分が、やっぱり一番大事なわけです。なかなか発言が取れないからと言って顔出しをやめたり実名をやめたりして話をさせてしまった結果の、悪い例が大阪市長選の話だったりするわけです。報道の信頼を得ていく、メディアの信頼を得ていくという意味では、取材を受ける人の発言の信頼性を確保するというのは当たり前の根っこの話で、それを忘れてほしくないですね。
◆「大阪市長選関連報道への申立て」事案について◆
意見交換に先立ち、放送された当該ニュース番組を参加者全員で視聴し、冒頭、決定文の起草を担当した小山委員と曽我部委員から概要と判断のポイント説明があった。
小山委員
今、ご覧いただきましたが、2種類のカードが出て来ました。一つが紹介カードで、これは知人を紹介してほしいというもの。それからもう一つが回収カードで、こちらの方が実は虚偽だったものです。今回のスクープはその回収カードが見つかったということで取り上げた訳ですが、先ほど顔なしでインタビューに応じていた人物がそれをねつ造していた。それが後で明らかになります。
おそらく皆さんもどうして委員会がこういう判断をしたのかということよりも、どうしてこのような放送がされてしまったのかのほうにご関心があるかと思います。いくつか補足しますと、組合側にまったく裏付け取材せずに放送した背景には、一つは市議会議員からの情報提供であったということ。それから、先ほどのカードをねつ造した人物ですが、これまでも局側に情報を提供していたようで、その限りでは信頼できる情報だったと。ですから信頼できる情報提供者だということで、今回も真実だろうと思い込んでいたということです。
それから、そのカードの存在自体はもっと早くから局はキャッチして、局によりますと、要するにギリギリになって組合側に取材を行ったと。そうしたところ、取材することが結果としてできなくなったということを言っておりました。さらに、この放送のあと素直に局側として訂正あるいは謝罪をすればいいのにと思いますが、その後始末という点では不十分だったと委員会は考えました。
あとは皆さん方のご質問を受けて、いろいろご説明できる点があればご説明したいと思います。その前に、一緒に起草を担当した曽我部委員から補足をしていただきます。
曽我部委員
私も基本的に、ご質問等ございましたらその中でお答えするという形にしたいと思いますが、その前にこの事案を委員会が判断するときに、念頭においていた裁判所の判例がありますのでご紹介します。
『判断ガイド』をお持ちと思いますが、一つは74ページに「所沢ダイオキシン報道事件」があります。これは、報道番組によって摘示された事実がどのようなものであるかという点についても、一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準として判断するのが相当であるとあります。これは本件にどう関係するのか。ご覧いただいたように、形式的には疑惑があるという表現ですね。局側は、あくまでも疑惑を報じたのだと主張していました。しかし全体、ご覧いただくと、皆様どう思われたでしょうか。スクープですということが強調され、あるいは回収リストそのものは本物であるという前提で報道しています。さらにやくざとか、議員の発言もあります。あれも疑惑が本当であるという前提であるかのような発言に見えるわけです。こういったところを総合的に見ると、一般の視聴者はあのニュースは何を言っているのか、疑惑を疑惑として伝えているのか、それとも疑惑というよりはもっと断定して報道しているのかについては、大方ご判断いただけるのではないかと思います。
それともう一つ、疑惑を疑惑と報道しているという点についてです。疑惑だから確実でなくてもよいではないのかという話に仮になったとした場合に、これについても『判断ガイド』の80ページに、1968年の最高裁の判断があります。決定とありますが、さしあたり判決と同じ意味であるとご理解いただければと思います。この決定は非常に著名ですが、要するに人の噂であるから真偽は別にしてという表現を用いて名誉を毀損したというときに何を立証するのか、噂があるということを立証すればいいのか、それともその噂の本体が本当であると立証すればいいのかが争点になったわけですが、最高裁は、いや、噂だといったときに、その噂が実際にあるということじゃなくて、噂の中身を立証しなければいけないとしたわけです。今の疑惑の話に置き換えて考えると、疑惑を疑惑として報道したときに、そういう疑惑がありますよということを立証するだけでは実は不十分であって、その疑惑は単なる疑惑ではなくて真実、あるいは真実相当であるということを立証しなければいけないと読める最高裁の判断です。
すると疑惑報道というものは一切できないのかという話になりますが、この点なかなか微妙で、この決定は大変古い判断であるし、この事件の事案そのものは、きちんとした報道機関の一応根拠のある疑惑報道とか、そういう筋のいい事案での判断ではなく、怪文書の類の事案ですので、やはり報道機関がきちんと疑惑報道した場合にこういう判断になるのかは、やや疑問ですが、一般にはこういう噂、あるいは疑惑を伝えた場合に何を立証すべきなのかという点に関しては、その疑惑の存在ではなくて中身の存在だということになっているということです。
今回の決定は疑惑であるならば疑惑として、一般人にもそういう疑惑であるということをはっきりさせるようにと。そして疑惑であったとしても、一定のレベルの裏付けが必要だと判断していますが、それはこのご紹介した2件の最高裁の判断を念頭において判断したものです。
■質疑応答
Q この件は先ほどの顔なしインタビューのことでも触れていましたが、この内部告発者が顔なしになっていること自体に、ここにも一定の問題があるとお考えなのでしょうか。
三宅委員長
先ほどのケース、顔出し、顏なしでいえば、例えば犯罪報道にかかわる周辺住民からの意見、感想を述べてもらう場合とか、内部告発者の放送自体について、この決定の中でそれが悪いという判断は触れていませんので、基本的に内部告発者の保護という観点からは映像自体はあれでよかったと考えて、委員会では議論を進めています。ただ問題は、かなりていねいにコメントをとる機会の設定をされていますが、裏取りがちゃんとされてないということからねつ造ということを見破れなかった点において、取材上の手落ちがあるのではないかと思いますので、放送のレベルと取材のレベルにおける真実性の担保の努力という観点からはもう少し何がしかの工夫とか、裏取りの取材をした上でその辺の経過をよく聞いてみるとか、取材のあり方が本来求められていたのではないかと考えているところです。
曽我部委員
事前にいただいたアンケートで、組合側にコメントをとっていないところに非常に問題があるとお書きいただいたご意見が多かったと思います。その中で、逆にコメントをとっていれば放送して問題なかったのか、というご意見もありましたが、実は委員会決定の通知公表のときに、記者の方とのやりとりがありまして、小山委員が、組合を取材すると回収リストは自分たちが作成したのではないという答えが返ってきただろうと回答されています。実際、他局もリストと称するものを入手して組合に取材したところ、それは本物ではないということを言われたので放送しなかったということがありました。回収リスト自体も不自然な点は結構あったわけですね。例えば組合であるにもかかわらず管理職の名前が載っているとか、不自然な点があったわけで、これは取材をすればおそらくこの回収リストが本物ではないということはおそらくわかっただろうという事案だったということかと思います。
事務局
事前アンケートをご紹介します。「取材の進め方、番組の進行には問題があったと思いますが、ただBPOに提出した当該局の取り組みの報告書の内容についてまで、改めてBPOのホームページに委員会の決定の趣旨を理解していないと公表する必要があったのかどうかについては疑問です」こういう声がありますが。
奥委員長代行
このアンケートに書かれた方の疑問は、おそらく極めて異例だろうということだと思います。私もBPOの委員になって長くはないのですが、こういう形で改めて書いたというのは、たぶんなかったのではないかと思います。簡単に言うと、我々が一生懸命議論して、こういう決定を出したのにもかかわらず、ちゃんと理解されてなかったという思いが残ったんですね。報告書は、番組には公共性、公益性があったけれども、ちょっと言葉遣いがひどかったよ、ごめんなさい、と言っているだけなんですね。そういうことを我々は言ったわけではないので、そこのところを理解していないので、やっぱりこれには一言言っておく必要がありますよということで、あえてああいう形で載せたということであります。
三宅委員長
私の最終判断でホームページにアップされたことになりますので、一言コメントしておきますが、この『判断ガイド』の430ページ、先ほどのグラデーションですと放送倫理上の重大な問題ありです。勧告ですから、灰色じゃなくて黒ということです。人権侵害と同視できるレベルという点です。委員会は特に以下の4点から本件放送に放送倫理上の重大な問題があると判断したということで、申立人に対する取材のあり方ということでは、回収リストが本物かどうかを含め申立人を取材してその言い分を放送することは取材の基本ではなかったかと。その辺について今後のスクープ報道における取材や表現のあり方について考えください、というのが431ページの末尾にあります。
それから断定的報道のレベルのところでも、一般視聴者には申立人が市長選挙への協力を組合員に強要したことが事実であると認識されるという、そこの断定的な表現、これがまさに表現のあり方として改善の余地はあるんではないかという議論を局内でやっていただきたかったという点です。
同じように内部告発者のやくざという発言ということで、回収リストが本物と決めつけられなかった疑惑の段階では引用を控えるべきではなかったのか。
それから、続報のあり方で、これがねつ造だということがわかった後、かなり詳細に続報しているから、申立人の労働組合の社会的評価はかなり回復しているじゃないかという言い方が出て来ますが、これについても、すみやかに取り消し、または訂正して、続報や訂正すべき情報についての放送のあり方について具体的にこうすべきだったというのが、まさに決定の内容です。この4点について考えていただくということが、決定をしかと読んでいただくと出て来るだろうと思ったのですが、いや、スクープとやくざの点だけちょっと問題だったというニュアンスの報告書の冒頭の表現だったものですから。
我々も意見交換会を直にやって、理解をされているということはわかったのですが、わかった以上は報告書もそれなりの形で変えていただくべきではなかったのかと。報告書を読んだ委員全体の意見からすると、意見交換をした委員のようには委員会全体ではならなかった。この報告書の内容について、これでいいかどうかについて、もう1回委員会で議論をして最終的にこちらもコメントを出したいという経過があったということです。
ですから決定文は決定文として、勧告ですからやはり社内でしっかり受け止めていただいて、その対応をしていただきたかった。もし現場に対応されるときは、決定が出て、決定もらって、それで真摯に受け止め、今後改善しますと放送で言うだけじゃなくて、社内でいろいろ議論を尽くしていただいて報告をいただきたい、という点がこちらの感想、対応であったということを付け加えさせていただきます。
◆「宗教団体会員からの申立て」事案について◆
本事案については、1時間番組を10分程度に編集することについて許諾をいただき、事務局で編集したものを参加者全員で視聴してから意見交換に入った。冒頭、起草を担当した市川委員から概要とポイントの解説があった。
市川委員
まず本件全体の判断枠組ということで大きく分けると、プライバシー権、肖像権を侵害するかという権利侵害の問題と、放送倫理上の問題はあったかという2つを検討しています。
本件ではここが一つ大きな論点になるかと思いますが、放送で申立人と特定可能か、あるいは判例等では同定という言葉を使いますが、同定可能かということです。ボカシのかかっている、顏だけから見ると必ずしもわからない。ただ、かなり薄いボカシで、周りの人たちが映っている。一緒にいる友人、しかも卒業式だというのは見るとだいたいわかるのですが、この卒業式で一緒にいる友人の特徴的衣服のわかるボカシ。それからナレーションで今年の春、A市内の国立大学を卒業して市内で就職したと。申立人が卒業した大学の雑観を映すと、大学名は出て来ませんが学部の門柱が出て来ます。すると、どこの大学かという特定が客観的には可能になります。あと、○○地方に住む家族ということ。それから出身地の駅ビルの名前等が入った背景等が出て来る。(「○○」と「A市」部分は当委員会決定では非公開としています。)そういったものを順繰りに追って見ていくと、結局、当人の周囲の人たち、大学の友人であるとか、職場の人であるとか、あるいは将来、彼と出会って、彼の属性を知っていく人からは特定が可能になるということになります。一般の視聴者から見ると、すべての人からは特定ができるわけではないんですが、こういう場合、判例等ではその周囲の方、それから将来、彼とその人と知り合う方が特定できる場合には不特定多数の人が知りうる、特定しうるという状態にあるという認定をしていて、この決定でも同じような枠組で考えています。ということで、本件は諸事情を組み合わせてしまうと特定できるという点の問題を指摘しています。
次に、この特定された方のプライバシーに立ち入ったというプライバシー権侵害の問題になる。それで公共性、公益性の観点からこの放送が許容されるのかということが問題になります。この点は公共性、公益性の程度の問題と、それから侵害の程度、どういう内容であるかとか、どういう対応で放送しているのかとか、そういった比較考量ということになってきます。いずれかが重ければいずれかが軽くなるというか、程度が下がるという、そういう関係になります。
委員会では、本件放送部分が対象としたのは内心の深い部分の人にもっとも知られたくない事柄の一つであるから、こういう特定しうる状況下で承諾なく放送するのは、いかに公共性が認められているとしてもプライバシー侵害に当たるのではないか。これが一つの意見です。もう一つは、カウンセリングの冒頭の部分、15秒程度の本人の発言です。カウンセリング自体は1分程度の発言で。その中で出てきたのはアレフに対する自分の見方を述べる部分だったので、具体的な事実の吐露があったとまでは言えないのではないかと。しかも放送目的に直結するものであった。
つまり若者がなぜアレフに向かうのかっていうのを明らかにするという観点から考えると、公共性、公益性、それに直結する内容で、あまり深い部分のプライバシーまでは立ち入っていないのではないかということで、プライバシー侵害まではいかないというご意見もありました。
他方では、高校時代に友人関係がうまくいってなくて、この信仰が非常に自分の心の中にストンと入って来たという心情というのは、それはそれで彼にとってみれば大事な、かなり内心の深いところにある問題ではないかということでプライバシー権侵害とは言えるのではないかという議論もありました。
結論としてはその点で両者一致した結論を得ることはできなかったので、プライバシー権侵害についての結論は出さなかったし、プライバシー権侵害とまでは本件の決定では言ってはおりません。ただ問題点としては、こういう議論をしたということを触れております。
次に放送倫理上の問題点があるかどうか。特定可能性への配慮ということで、プライバシーにかかわる事実を明らかにするものだったので、ボカシや肉声の変換という配慮だけではなくて、特定しうる情報をどの範囲でどのように明らかにするかについて、より慎重に配慮すべきだったし可能ではなかったかと。こういう意見を述べて、一つの問題点を指摘しています。
次にカウンセリングの隠し録音と信書の撮影朗読の問題点。やはり放送倫理上の問題としては行き過ぎている、踏み込み過ぎているのではないかというところで意見の一致を見たというところであります。
最後に、団体としての取材拒否、両親の承諾との関係について、当該局としてはアレフという団体からは頻繁に取材拒否をされていた。幹部も絶対に取材に応じないというスタンスだったと。そういう中ではこういう手法もやむを得なかったと。それからご両親の承諾を得ていた。しかし、成人のこの申立人についていかに両親が承諾していても、これは別の問題だろうと。そういう理解の下で放送倫理上問題ありという結論になったわけです。
この見解では高い公共性、公益性と言っていますが、委員会としても評価しております。ただ、そうはいってもやはり踏み込んではいけない領域というのはやはりあるだろうと。そこのバランスは絶えず考えていかなければいけない。当該局の方はなかなかそこの点のご理解がいただけてなかったのかなというふうに感じていまして、局全体としてもやはり一度立ち止まってですね。その担当者あるいはその上のチェックする方が別の視点から立ち止まって考えて、はたしてこれはバランスがとれているんだろうかということは考えていただきたかったなと思いました。
■質疑応答
Q 映像表現等のことで専門家の法律の先生もいらっしゃるのでお聴きしたいのですが、もし本人の特定ができないような処理をした上であれば、隠し録音の内容、あるいは両親への手紙を使用したケースはプライバシーの侵害に当たるのかどうか、それから、それは放送倫理上はどうかという点、この辺をお伺いしたい。
三宅委員長
小山さんと曽我部さんにあとで補足してもらいたいと事前に言っておきますが、たぶん特定されないとしてもカウンセリングの核心部分とか、実際の手紙を映像で出すということは、本人が特定されないとしてもやっぱり権利侵害になるという議論はたぶん一つあると思うんです。ただ、この委員会で議論をしていたときは、そうはいってもまさにそこが核心部分で、なぜ若者がそこに入るのかっていうときに、隠し録音の内容とですね、手紙の内容「すべての魂は否定できなくて」って、あの辺のところがやっぱりキーじゃないか、肝じゃないかということで、あれを抜いて放送がはたして成り立つのかという議論も一方にあってですね、非常にこれをプライバシー侵害として一本の意見にまとめることは基本的にできなかったので、おそらくそこは委員の中でも意見が分かれる部分もあると思います。
小山委員
まず、その当人だとまったくわからないようになっていた場合にはプライバシーではないと思うんですね。ただ例えば名誉毀損を考えた場合に、名誉毀損とは別に名誉感情の侵害があります。名誉毀損は社会的評価の低下ですけども、名誉感情は自分が侮辱されたとか、そんな感じの感情です。それに近いような形でプライバシーではないけども、何か自分が大事にしているものが暴露されたということで、それは人格的利益の一つということはできるんではないかなと。
曽我部委員
まず特定できない場合、これはプライバシーと呼ぶかどうかは別として、やっぱり自分の思想・良心の深い部分について公表されたというような場合については法的責任が発生する場合は十分ありうると思います。普通のプライバシーは自分の私的な事柄が人に知られて、それに対して社会的なリアクションがあって精神的苦痛を受けるというような構造ですけど、この場合、自分の思想・信条が外に出たのは誰にもわからない、自分だけの問題になるので、普通のプライバシー侵害とは構造が違います。広い意味でいうと両方プライバシーでしょうが、通常のプライバシーとは少し違うので、ネーミングとしても別なものになる可能性あるとは思いますが、いずれにしても法的な問題にはなるかと思います。普通の私的な事柄であれば、特定できないようにすれば法的責任は生じないと思いますが、例外的にそういう内心の深い内容のようなものであれば、今、申し上げたようなことになると思いますので、それにともなって放送倫理の観点からも、放送するだけの必然性のあることなのかをお考えいただくということだろうと思います。
奥委員長代行
確かに問題は公共性、公益性と権利侵害のつまりバランスですね。比較考量の問題としてこの番組に対する判断があったわけですが、私が委員会の中で強く言ったのは公共性とか公益性っていうものはどっか宙に浮いてあるわけではないということでした。この番組に即して言えばアレフという現に団体規制法の観察対象になっている団体があって、かつてこれはオウム真理教だったわけですけれども、かつてオウム真理教が若者たち、それも、かなり学歴の高い若者たちを集めた状況がある。今また同じような状況が起こっている。一体これはどうしてだろうか。そこに踏み込んで1時間のドキュメンタリー番組を作ったわけですね。私はそこに公共性と公益性があるのであって、そうした意味での公共性、公益性というものと権利侵害をバランスの中で考えざるを得ないだろうと思いました。
さきほど委員長がおっしゃってくれましたけれども、なんで若者がアレフに惹かれちゃうかという内心に迫らないと、この番組における公共性、公益性は達成することはできないわけですよね。そこに踏み込んだという部分があるんであって、それを名誉毀損だとかプライバシーっていうところで切ってしまうと、そもそもこの番組は成立しないだろうと思っているんですね。にもかかわらずこういう形の決定になったのは、ちゃんとモザイクをかけなかったとか、もっとちゃんと本人かどうかわからないようにすればよかったというのが私の考えです。委員会は決して法律論議だけをしているわけではないということを少し補足的にお話ししておきます。
坂井委員長代行
実はこの番組作った方たちは、ちゃんとプライバシー保護、同定ができないようにしたというふうに断言しておられるんですね。ちゃんとモザイクなりボカシなり、それから匿名なり、本人が特定できないようにすべきだという点については局も委員会も一致しているんです。それについて局は十分やりましたというのに対して委員会はこれじゃダメだろうということで、今、奥代行が言ったようにそこはちゃんとやらなきゃダメじゃないのかと、そういう話だということをご理解いただければと思います。
Q 私も非常に目指すべき意義の高い番組だと思うんですが、ヒアリングの中で制作者の方、申立人に対して取材の申入れをしなかった理由はなんだって答えているのでしょうか? なぜ申入れをしなかったのでしょうか?
事務局
番組のプロデューサーからは、本人に取材を申し込めばアレフが必ずつぶしにかかってくる、それは絶対避けたかったという一点。もう一つはご両親から本人には知らせないでほしいということがあって、本人に取材しなかったという説明はプロデューサーからありました。
◆飽戸理事長から締め括りのあいさつ◆
今日の議論を伺っていて一番気になったのはやはり視聴者がここ10年、20年の間に大きく変わってきているということ。視聴者のカルチャーが大きく変化しているという点だと思います。局の方からも取材拒否が多いとか、視聴者の態度が厳しくなっているというお話がありました。これは他の分野でもそうなんですね。プライバシー意識、権利意識が高くなって、世論調査なんかでも拒否が激増しています。そういうこともあって、視聴者の皆さんのテレビに対する態度も大変厳しくなっている。10年、20年前だったらバラエティー番組でもフリーパスだったようなのが最近は苦情が殺到するようなことが起こっているわけです。
そういう意味でも視聴者のカルチャーに常に配慮しながら番組を作っていただきたい。
これだけ各局の皆さん、熱心に真剣に番組を作ってくださっているわけですが、BPOに年間2万件ほどの意見がずっとここ数年寄せられており、そのほとんどは苦情なんですね。なかでも一番困るのは、BPOは放送局の味方だ。だからいくらBPOに苦情を言っても番組は変わらない。
もっとBPOは番組を厳しく監視して、厳しく罰してくれという意見が相変わらず来るんですね。BPOは番組を監視して処罰する、そういう機関ではないんですね。あくまで放送事業者の自主・自律的改革・改善を支援する組織としてのBPOの役割をしっかりと伝えていくということが我々の責務でもありますが、皆さんの側もそういう視聴者が厳しくなっているという状況に対応するような番組作りにぜひ力を入れていただきたいと思います。
我々も先ほどもありました辛口の応援団としてこれからも努力していきたいと思いますので、今後もご支援いただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。