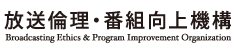在京キー局との意見交換会
放送人権委員会は、7月18日に在京キー局との「意見交換会」を千代田放送会館会議室で開催した。民放5局とNHKから17人が出席、委員会からは坂井委員長ら委員全員が出席した。
今年の2月と3月に通知・公表を行った決定第62号「STAP細胞報道に対する申立て」(NHK 勧告:人権侵害)と決定第63号、64号の「事件報道に対する地方公務員からの申立て」(テレビ熊本、熊本県民テレビ 見解:放送倫理上問題あり)を取り上げ、それぞれ番組を視聴し、坂井眞委員長と起草担当委員による説明、少数意見を付記した委員による説明の後、質疑応答を行い、約3時間にわたって意見を交わした。
質疑応答の概要は、以下のとおり。
◆ 「STAP細胞報道に対する申立て」
(NHK)
決定の説明で、ダイオキシン報道の最高裁判決の話があったが、最高裁判決は、煎茶のダイオキシン類測定値を野菜のそれと誤って報道した部分については、放送が摘示する事実の重要部分の一角を構成するものであり、これを看過することができないとしている。決定文を読んだ職員からは、STAP細胞報道で、ホウレンソウをメインとする所沢の葉っぱものとのコメントに当たるところはどこなのか、それがないのではないか、という声が出ている。
(坂井委員長)
今のご質問は最初にもっとも意見交換すべきところだと思う。まず曽我部委員が言ったように、ダイオキシン報道最高裁判決は、新聞記事に関する最高裁の判例が一般の読者の普通の注意と読み方が基準だとしていることを引用したうえで、テレビ放送でも同様に一般視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準とするとしている。こういう抽象論を言ったあとに、最高裁判決ではさらに具体的にどういう要素によって摘示されている事実を判断するかということを述べている。
まず当該報道番組により摘示された事実がどのようなものであるかということについては、当該報道番組の全体的な構成、これが一つの要素とされている。決定文(7~8ページ)で言っている(1)~(5)までと(6)のつながりも、この要素との関係で出てくるものと言える。この場面がどういう全体の流れの中にあるのかという観点からの判断だ。
それから二つ目が登場した者の発言内容。今おっしゃった久米さん(ダイオキシン報道の番組キャスター)の発言をストレートに挙げている。つまり久米さんの発言はいくつかの要素のうちの一つです。その次に画面に表示されたフリップやテロップ等の文字情報の内容を重視すべきことはもとよりとされている点。これは、最近の例で言うと、人権侵害との判断はしていないが、テレビ朝日の「世田谷一家殺害事件特番への申立て」(決定第61号)で、サイドマークだったり、テロップだったり、いろいろな形式で用いられていた文字情報を含めて摘示されている事実が何かを判断したこととかかわっています。それから、もちろんテレビですから、映像の内容、効果音、ナレーション等の映像及び音声にかかる情報内容という要素、そして放送内容全体から受ける印象等。これらの要素を総合的に考慮して判断すべきであると最高裁判決は述べています。
だから、ダイオキシン報道の最高裁判決というのは、何か具体的な一つの発言を捉えて、それがあることを前提として判断しているわけではなくて、こういうたくさんの要素全体から判断すると言っているのです。ダイオキシン報道で特に象徴的に出てくるのは、さっき申し上げたホウレンソウをメインとする所沢産の葉っぱものと言っていたところだが、実は一番濃度が高かったのはお茶だった。それについて専門家もちゃんと説明していないとか、いろんな事情があったが、そこについては真実性ありとは言えない。重要な部分について真実性がありとは言えない、そういう事例だった。
判断基準としては、発言内容でこれを言ったとかいう、ピンポイントの要素で判断するのではないというのが私の説明になる。本件についても、どれか一つの発言ということではなくて、今、指摘したようなたくさんの要素を総合的に考慮して、我々の摘示事実の認定がなされたということになる。
(曽我部真裕委員)
ちょっと補足をさせていただきたいが、実はこの裁判は東京高裁では真実性ありという判断だった。それは別の研究者が白菜の測定もして、煎茶の3.8ピコグラムに近いような数字が出ていたと。そういう情報を持ってきたので、それをもって高裁は真実性ありと判断した。最高裁は、それはダメだと言った。なぜダメだかというと、摘示事実の認定が高裁と最高裁で違っていた訳です。
最高裁は摘示事実として、所沢産の葉っぱものが全般的に高濃度に汚染されているということを言ったと判断した。だから、要するに白菜1点持ってきたところで、それでは全般的に高濃度に汚染されているということの証明にはならないと言って、真実性・相当性は否定した。これに対して、高裁は全般的にとは言っていない。高濃度の白菜が一つあったので真実性を認めた。
だから、高裁と最高裁で判断が分かれたのは、摘示事実の認定が違っているところにあって、なぜ、最高裁が摘示事実として全般的に高濃度に汚染されていると言ったかというと、これは当該部分全体を見ているから言ったわけです。番組の中で、別に全般的に高濃度に汚染されているという発言は無かったが、全体として、それこそ全体として汚染の深刻さを繰り返し、いろんな手を変え品を変え訴えていたことから、最高裁は摘示事実を全般的に高濃度に汚染されているという認定をした。
要は、全体の作りから一般の視聴者はそう受け止めるであろうと判断したもので、むしろ参考にすべきは、この判断かなと思う。
(NHK)
最高裁判決でいうと、ホウレンソウの値段が暴落しているので、一般視聴者も多分そう見ただろうと思う。ただ、今回のSTAPについては、我々はモニターからリポートを取っていて、この番組が終わった後、視聴者の皆さんからモニターを取ったが、その100件余りの中でも、要するに盗んだという決定と同じように番組を見たという人はいなかったし、そういう抗議も来なかった。申立人が主張してきて初めて、ああ、そういうふうに見られているのだということが分かった。
先ほどの曽我部委員の説明で、摘示事実の認定に関わる部分で、STAP研究が行われた時期と、元留学生のES細胞が小保方研究室の冷凍庫から見つかった時期の間には、2年以上のブランクがあると繰り返し指摘されている。ただ、STAP細胞が最初に成功したとされるのが平成23年11月以降で、その後、研究を継続的に行っているので、2年以上の間隔があるという事実は無い。なぜ、2年以上の間隔があると判断したのか。
(坂井委員長)
2年以上の間隔という意味が、みなさんが捉えていらっしゃるポイントと、我々が言っている趣旨がズレているというか、違っていると思います。
我々が言っているのは、番組を見てわかるように、キメラ実験を成功させたときのSTAP細胞は、実はES細胞のコンタミ(混入)が原因だったんじゃないかという点にかかわることだ。番組では、そのときの話をしているわけだから、それから2年以上経って、ということになる。特にキメラ実験をしている当時は、まだ小保方研なんてないですし、まして小保方研の冷凍庫も無いわけですから、それから2年以上経って小保方研の冷凍庫から見つかりましたということに、どういう意味があるのか。キメラ実験のときのコンタミしたかもしれないES細胞と、どこにあったか分からない留学生の細胞、どこで、いつどうやって、どういう経路でキメラ実験の後に作られた小保方研の冷凍庫に入ったか分からない留学生のES細胞との関係が問題とされているわけで、見つかったときと、キメラ実験をしたときの間が2年もある。そうすると、関係が無いのだったら、ここで見つかったから混入したのではないかという話にはならない。
NHKは、STAP研究は2年以上続いていたという。でも、その話は申立てに係わる、この放送の問題とはあまり関係ない。この放送でどういう事実が摘示されて、それが名誉毀損に当たるかどうかという話をしているときに、放送で問題にしているキメラ実験の後もSTAP研究が続いていたということは意味がなく、我々が言っている2年間とは観点が全然違う。
(曽我部委員)
2年という数字そのものには、特に意味は無い。おそらく、視聴者としてみれば、最初のキメラ実験の辺りから混入していたのであろうと、これは決定文には無いですけれども、おそらく通常、受け止めるだろうと思う。そうすると、その時点から混入していたという話と、だいぶ後になってから、たまたま、たまたまかというかどうか、出て来ましたよと、研究室の冷凍庫にありましたよという指摘とのつながりは、少なくとも、あの放送内容では視聴者はよく理解できないんじゃないかと思う。
審理の過程でも議論はあったが、あの場面はNHKの側からしてみると、要するに、小保方研における細胞の保管状況はあまり厳格ではなかったので、混入する可能性も、客観証拠として、傍証として、間接証拠としてはあるんじゃないかという趣旨で放送したのかなという気もするわけだが、ただ、それは後から見ると、もしかしたらそういう趣旨だったのかもしれないなという程度で、やはり普通に見ると、先ほど来ご説明申し上げているような形で視聴者は受け止めるだろうということだと思う。
(A)
第二次調査報告書の中で結局、2005年に若山研のメンバーが樹立したES細胞が、その後ずっと2010年に若山研が持ち出すまでは研究室にあって、その後なくなったはずのES細胞が、後に小保方研のフリーザーに残っていた資料から見つかって、それが今回のSTAP細胞の中の成分と一致しているという、そして、これは誰が入れたのか、謎のままだという調査結果が出ている。
その大筋においては、それが元留学生のものかどうかは別として、ある程度放送と一致した内容の最終的な調査報告書が出たということが、今回の真実性の判断の中で審理されたのか?
(坂井委員長)
報告書では、若山研にあったES細胞がコンタミしたのではないかと書いてあるから、その限りでは真実性があるのではないかというお話だが、真実性は、番組で摘示された事実を対象に真実性があるかどうかを判断する。
我々の認定した摘示事実では、留学生の作成したES細胞と、冷凍庫で発見されたES細胞というのは、番組で関連があるんじゃないかと言っているわけだから、留学生のES細胞を取っ払って、一般的に若山研のES細胞との関係で真実性を判断するわけにはいかない。報告書で若山研にあったES細胞がコンタミしたのではないかとされているから、その点は真実性があるというが、番組はそういうことは言っていない。前提として、番組の摘示事実は何かというところから真実性の話をしないと、ちょっと論点がズレるのではないか。
市川代行の少数意見は、そこは切り離している。番組として切り離すのだったら、留学生の細胞の話を出さなくたっていいわけですから。私は切り離すのはおかしいと思っているが、それは意見の違いだからしょうがない。
(B)
私は放送を一視聴者として見ていたが、そのときの印象として、出所不明のES細胞が小保方研究室の冷凍庫から出て来たという事実は捉えたが、いわゆるSTAP細胞がそのES細胞に由来する可能性があるとまで摘示しているとは感じなかった。それが即、STAP細胞に使われたというふうには思えなかったというのが正直な感想だった。普通の視聴者の視聴の仕方というが、やっぱり、個々の視聴者が感じることは違うと思うので、私は委員会の判断は相当厳しいなと、すごく感じた。
(坂井委員長)
我々は一般視聴者を全部調査しているわけではない。さっきNHKもおっしゃったように、そうでもないと思う人もいるだろうし、我々もそういう意見もあることは聞いているが、我々は9人の委員がどう認識するかで判断するほかない。つまり、放送を見て、委員会のメンバーが最高裁の基準からしてどう判断するかということで、それは違うと言う人がいたからといって、間違っているということにはならないだろう。委員会として、これを普通に見たらどうなるだろうかと判断をするしかない。これを厳しくしようとか、緩くしようとかは、全然思っていない。
今のお話は、出所不明の留学生の作ったES細胞が、その前の場面のアクロシンGFPが入った若山研にあったES細胞と同じとまでは思わなかったという話ですよね。当時同じだと認識していなかったのであれば、それを明らかにしたうえで、留学生の作ったES細胞が、なぜか後になって小保方研の冷凍庫から見つかったが、なぜそこにあるのか、小保方さんには説明していただけませんでしたというふうにすれば、その前の部分とは区切られて問題にはならないかもしれない。
逆に先ほど説明したように、アクロシンGFPが組み込まれたES細胞が混入したのではないかというSTAP研究当時の混入の可能性を指摘した部分に続けて、それとは別の話であることをはっきりさせないで、元留学生作製のES細胞の保管状況を紹介し、なぜこのES細胞が小保方研の冷凍庫から見つかったのかと疑問を呈するナレーションがある。そうすると、このES細胞が混入したらSTAP細胞ができちゃうね、という流れだと、一般の人にもそう見えると我々は判断した。
NHKは違う話だと主張するが、違う話だったら、どうしてこういう流れで出てくるのか分からないというが委員会の意見で、違う話だと分かるようにすればいいと思う。理研なり小保方研での細胞の管理がいい加減だったという文脈であれば、そういう文脈をはっきり出せばいいと思うし、そうではないと言うのだったら、それまでのアクロシンGFPが組み込まれたES細胞が混入したのではないかというSTAP研究当時の混入の可能性を指摘した部分との関係、そこはまだよく分からないけれども、なぜか無いと言っていたES細胞がありましたと、それは事実で真実性を立証できる、無いと言っていたのに出てきたわけですし、出て来たということは立証できるんだったら、それは全然問題ないし、やりようはあるだろうなと思う。
(B)
この元留学生が作ったES細胞には、アクロシンGFPは組み込まれていないのですね?
(坂井委員長)
結論としては、そうだと思う。
(B)
NHKは放送当時、それを知っていたのか?
(奥武則委員長代行)
今おっしゃった部分について、もし放送するなら、こうやればよかったかなと、一つの提案に過ぎないが、決定文29ページの下から11行目の、「事態が『霧の中』にある状況で」という書き出しの段落の真ん中あたりに、例えばとして書いてある(「アクロシンGFPが組み込まれていないため、現在の時点では遺伝子解析が行われたSTAP細胞とのつながりは明らかではないが、小保方氏の研究室で使われている冷凍庫から、本来あるはずのないES細胞が見つかった」)。こんなふうにすれば、別であるということが分かったのではないか。
アクロシンGFPの話は、後になって、NHKにヒアリングした際にちゃんと聞けばよかったなと思った。アクロシンGFPが入っているか入っていないのかについて、NHKが取材したかどうかは、今もって分からないが、事実としては入っていなかった。
(B)
もしNHKが知っていて表現しなかったなら、放送倫理上問題はあるなと私は思う。ただ、なぜかこういう事実摘示だと認定し、人権侵害のほうに行ってしまうのが、本当によかったのかなと。
(坂井委員長)
そこは何とも言いようがないが、一般視聴者ではなく、やっぱりその道のプロでいらっしゃると、そうお考えになるのかなと思いながら聞いている。ただ、委員会は、一般視聴者が普通に見たらどうだろうかという観点で議論をし、結果、こう判断せざるを得ないと結論した。少数意見も2人もいて、人権侵害とは認めないとしているが、放送倫理上問題ありとはおっしゃっている。
(C)
今の議論を聞いていて、委員会は裁判所なのかなと思ってしまう。例えば、今の状況で行けば、加計の問題とか森友の問題、僕らは一切放送できない。事実性も真実相当性も中途半端な状態でしか分からないので。
今回のケースで行けば、やっぱり、あのSTAP細胞に何かあったのじゃないかという素朴な疑問、メディアの素朴な疑問、当然NHKも持つし、僕らも持った。その疑問について、当然、小保方さんにも当てた、一切回答は返ってこなかった。そういう状況の中で、一所懸命番組を組み立てていった。この問題をメディアがどうやって伝えるべきか、その大義の部分の認識は委員にあったのか? 些末なことが十分な真実性が無いから人権侵害だと断じてしまうのは、ほとんどの調査報道の道を閉ざすことになる。
(坂井委員長)
加計の話とこの話は違うし、調査報道はいくらでもすればいい。ただ、名誉毀損にならないようにすればいいだけの話。それをしない方法はいくらでもある。ここをこうすればという、こんな問題で名誉毀損と言われなくて済むやり方はあると思う。法律家ですから、よく分かっているつもりですけれど、そのようなやり方をするのも報道する側の仕事だと思う。名誉毀損された人間というのは、とんでもない痛みを受けることがある。それを忘れてはいけないと思う。
報道というメディアの重大な役割は委員全員が認識している。それは決定文に書いてあると思うし、こういう問題を起こさないようにすることこそが大切だ。
加計の問題を言われるが、安倍さんは総理大臣だから、公的存在として、STAP研究の1研究員と全然違う。報道されていい範囲が立場によって全然違うのはご存じですね。それを同列で議論できるわけがない。おっしゃるような調査報道はどんどんやるべきでしょう。けれども、そこで名誉毀損だと言われないようにする、細心の注意を払うべきじゃないかと思う。それは、そういう重大な役割を担っている報道のみなさんの役割だし、義務だと思う。
(D)
やっぱり普通に番組を見ると、小保方さんがあの細胞を勝手に盗んできて、個人的にやったのかと見えちゃう。小保方さんが個人的にやったのか、もしくは研究者の誰かが勝手に入れたのか、何らかの手続きで間違って入ったのかもしれませんけれども、これを見る限りでは、個人がなんか意図的にやっているふうに見えちゃう。だとすると、これは個人がやったのか、それとも第三者が勝手に入れたのか、それについてお答え願いたいみたいな表現にすれば、よかったのかなと思う。
それよりも、どちらかというと、声優を使って紹介したメールのやり取りのほうが、かなり問題ではないのかなと。たしかに公的なメールでプライバシーの侵害ではないが、男と女の関係を匂わせるような表現はいかがなものかと、僕はリアルタイムで見ていてびっくりした。
(坂井委員長)
いかがなものかという趣旨の表現は決定文に書いてあると思う。本件のような大事なテーマで、そういうニュアンスを出すのはいかがなものかと、私も個人的に思うが、でも、声優が話している内容自体は大したことじゃないので、問題ありという結論にはならないと思う。
(奥委員長代行)
先ほどご質問があった調査報道のことは、また少数意見で言いにくいが、決定文28ページの「調査報道の意義と限界」というところを読んでいただければ、私が考えていることは分かると思う。委員会は裁判所ではない。
(C)
委員会はより良い放送メディアを作るためのものなので、行き過ぎはもちろん訂正しないといけないが、とにかく押し込めてしまうということがあってはいけないと思う。法廷ではバランスは取れない、絶対に。ただ、委員会はバランスが取れると思っている。たしかに問題があるかもしれないが、伝える意味合いがあるものに対しては、それとのバランスをどういうふうに取るかを、是非お考えいただきたい。法律で言ったら、おっしゃるとおりだということはよく分かる。ただ、委員会はそういう場ではないと思っている。
(城戸真亜子委員)
私は法律の専門家ではない。放送に携わったこともあり、表現する立場でもある。やはり、調査報道は踏み込まないとできないという、おっしゃっていることはとても理解できるし、スレスレの姿勢で入り込んでいく姿勢が必要だと思う。今回のNHKのこの番組は、独自に調べられてタイムリーに作ったと思う。
でも、私はリアルタイムで拝見したが、やはり申立人が何か重大な間違いを犯してしまったんじゃないだろうか、という見方をした。あそこのシーン、留学生の話があり、試験管のようなものが出て来て、私の印象では「杜撰な管理方法でよかったのだろうか」みたいなことでまとめていたら、たぶん人権侵害にはならなかったのではないかと感じた。やはり、ちょっと行き過ぎた言葉によって、傷ついただろうと感じた。申立人のしたことが、それよりも大きかったかどうかはちょっと分からないが、放送によって本人が名誉が毀損されたと感じたならば、やはりそこを考えて判断していくのが、この委員会だと思っている。
(NHK)
今言われたことと、ちょっと関係するが、放送は「小保方さんにこうした疑問に答えてほしいと考えている」で終わっているわけではなくて、その後まで続いていて、新たな疑惑に対して理研は調査を先送りにしてきていて、こういったコンタミを含めた調査をきちんとやらないのかと、指摘する場面を付けている。
(城戸委員)
小保方さんは答えをくれなかったわけで、そして、理研はどうなんだとつながっていくことは大変よく分かるが、そこまでのトーンが、やっぱり、そのコメントに集約して着地しているように私は感じた。
(E)
7月3日付で委員会からNHKに対する意見(NHKの「STAP細胞報道に関する勧告を受けて」に対する意見)というものを出されたが、異例の強い調子で述べられているように私は受け止めている。これはもう、こういう形で平行線で終わりということになるのか。
(坂井委員長)
決定を通知したあと、我々が行って、当該局研修と言いますけれど、研修をしてその報告をいただいて、それで分かりましたと了承するときと、報告の内容に納得いかない部分があるときは、我々はそれに対する意見を出して、それで終わるというのがこれまでの通例です。
大阪市長選事案(決定第51号「大阪市長選関連報道への申立て」)のときも、当該局の報告に対して委員会の意見を出したが、そのときもそれで終わっている。それ以降について、特に何か意見を交換し合う手続きがあるわけではないが、でも、こういう意見交換会のように実態としては局側と話ができている。引き合いがあれば、こういう話ができればと思うが、手続き的には特に定めは無い。
◆ 「事件報道に対する地方公務員からの申立て」(テレビ熊本、熊本県民テレビ)
(A)
こういったケースは、おそらく同じような形で、いろんな場所にあるような気がしている。警察の見立てだと明確化すれば問題ないという結論になるのか、それとも、現時点で見立てに近いものはできるだけ報じないほうがいいというご趣旨なのか。どういった形で正しい原稿、倫理上問題のない原稿を書くかを、ご指導いただきたい。
(坂井委員長)
分かりやすいほうから言うと、警察の見立てに近い部分は報道しないほうがいいとは、全然言っていない。見立ては見立てとして報道してくださいと、委員会決定ではそういう言い方をしていると思う。見立ての部分と、そうではない部分、客観的事実として報道する部分は、ちゃんと区別してくださいということです。
決定文(テレビ熊本)の32ページを見ると、冒頭のところ(リード部分「酒を飲んで意識がもうろうとしていた知人女性を自宅に連れ込みデジカメで女性の裸を撮影したとして、熊本市の職員の男が準強制わいせつの疑いで逮捕されました」)で、逮捕容疑事実、警察発表の文書にないことも含めて言っている感がある、まず、そう言っている。そこはたしかに問題がある。そのあとの真ん中のあたりの「警察によりますと、(容疑者は今年7月、自宅マンションで意識がなく抵抗できない状態の20代の知人の女性の裸の写真をデジタルカメラで)~ 撮影した疑いです」、ここはそのとおり、警察発表のとおりだから、これを書いたからと言って放送倫理上問題ありという判断にはならない。
当該局研修でかなり活発に意見交換してきたが、全体を見てどうなのかということを考えないといけない。原稿はちゃんと書いたが、現場へ行ったアナウンサーやリポーターが話す内容が違うこともあるという話もあった。記者リポートのところに入ると、「事件当日、意識がもうろうとしている女性をタクシーに乗せ、自宅マンションに連れ込んだということです。意識を失い横になっていた女性の服を脱がせ、犯行に及んだということです」と言っている。この記者リポート、先ほど指摘した冒頭部分があり、その流れで放送されているから、このままでいいのかというと、なかなかそうとは言えないだろうなという気がする。
(A)
この記者リポートに近い中身を報じようと思ったら、警察の見立てと言われているところだが、例えば「警察によると、~ということです」と、エクスキューズを付ければ、ありうるのか。つまり前段で被疑事実を言う、被疑事実を認めていると。そのあと、追加、プラスαとして電話して聞いた中身とか逮捕の被疑事実とは離れた肉付け部分を、どういう表現を使えば、「容疑を認めている」から外して、プラスαとして「警察はこう言っているんですよ」という情報として付け加えて、かつ倫理違反に問われないのか?
(坂井委員長)
おっしゃっている部分が、きっとこのケースで一番問題になるところで、冒頭の部分は明らかにオーバーランしている。たしかに副署長が容疑事実を超えたことを言っていて、副署長は最初に、逮捕容疑はこうです、と言いながら、容疑事実にある「抗拒不能とは何ですか?」と聞かれると、全然違う話をバーッとしている。本当は、そこで、「いや、それって、なんか容疑事実と違うのですけれど、いいのですか?」という話があってほしいなと。別に「そう言え」と言うつもりはないが、そういう疑問があってもいいなという感じはする。「いやいや、現場はそんなことはできないよ」という話も、当該局でいろいろ聞いてきましたけれど(笑)。いずれにしても、エクスキューズということではなく、被疑者が認めている容疑事実と、警察の言っていることとは違う部分があるということが分かる表現が必要だと思う。
(市川正司委員長代行)
最初の冒頭のところがちょっと踏み込み過ぎ、「連れ込んで云々」と言ってしまったところが問題の一つ。もう一つは、「容疑を認めている」というあとにも、「何々しているとこのことです」「何々しているとこのことです」となっている。「とのことです」というのは比較的よく使う。警察の疑いを「こうですよ」と示すような意味合いで使うという意味では、それ自体は悪いことではないと思うが、ただ、「容疑を認めてます」という言葉のあとに、また同じような口調で言っているが故に、同じ容疑、同じレベルの容疑というふうに、どうしても受け止めてしまう。それが結局、放送している事実全てを認めている、容疑を全部認めているのだなと、全体としては受け止められてしまうのではないかと思う。
そうだとすれば、「認めています」というあとで、経過に関する事実、聞き取った事実があるのであれば、そこは、警察の疑いとしてはこうですよ、ということがはっきり分かるように、それを書けばいいと。我々が正解を出すわけではないが、そこは区別すべきだったのではないか、もうちょっと区別する工夫があって然るべきじゃないかなと思う。
当該局研修に行ったときに、そこは実は意識はしていらっしゃったという方もいたと感じたところだが、そこがなお不十分だったなというふうには思った。
(坂井委員長)
事案の概要(逮捕容疑)以外のことを聞いたら、余分なことを副署長が言っちゃっている、弁護人の話も何も聞けていないときに、これをそのまま放送に出すべきかどうかという判断が、本当はあるべきだろうと思う。出すなと我々は言っていないが、出すのだったら、そこはちょっと気を遣って、配慮しないといけないのではないかという決定文になっていると思う。出し方の問題はたしかに難しいと思うが、少なくとも彼はこういうことをやったと認めていないし、彼がそこを認めたと見られるような報道の仕方はまずいという気がする。
(E)
おっしゃる区分けというのは、ある意味で分かるが、例えば詐欺事件の場合、おそらく数億円の詐欺の可能性がある、だけれど、直接の容疑というのは、まず一定のところで始まって、最終的に立件されるのも、被害者弁護団が言っているような何億円になるかというと、そうならない事件もある。殺人の場合も、当初の逮捕容疑は死体遺棄がほとんどで、我々としてはそこまで見通してやっているわけだが、どうするのか。連続殺人事件の場合、埼玉の場合でも鳥取の場合でも、不審死とされた人の中で立件されたケースもあると。そのあたりをどう考えていくのか、日々、本当に現場で問われていることだと思うが、おそらく、そこについては、当然、報じていくことになると思う、僕らとしては。その人の周辺で複数の多くの人が亡くなっているという、その疑問が主体ということになると思うが、おそらく全く変わらないと思う、こういう委員会の決定があっても。
ただ、全体として見たら、この人はやっているのじゃないかと。一般の人の一般の視聴の仕方を基準にしたら、全体の印象としてはそういうふうに見られてしまうということがあるのではないか?
(坂井委員長)
例えば、詐欺の数億円の被害、実際、起訴されるのは公判維持できる範囲というケースもあると思う。いろんな経済事件がそうだと思う。そういうときに、まあ抽象的な話ですけれど、例えば被害者弁護団がいて、こういう損害があると主張しているというふうに書けば、メディアの責任は問われないと思う。すべての裏付けが取れない中でやっていらっしゃると思うけれど、工夫してやっていただきたいなということで、やるなということでは、もちろんない。
熊本の2局の当該局研修で、記者の方ではベテランの方から若い方まで、と話してきた。やっぱり経験によって判断の違いはあるし、このケースだといろいろ考えるという方もいるし、そうじゃない方もいるし、そこは、ケースによってだいぶ変わってくるだろうと思う。さっきの連続殺人と言われるようなケースで、絶対ここは負けない、つまり裏付けのある部分、そこは絶対ということもあるでしょう。そこを含めてどこまで何をどう書くかのかは、まさに工夫のしどころだという気はする。
(市川委員長代行)
私も、あまり一般化して、こう書けばいいとか、そもそも書いちゃダメだとか言うつもりは全くない。今回で言えば、容疑を認めているという、その与える印象が非常に強いわけで、そうであるとすれば、どこまで認めているということなのか、きちっと吟味していただきたいし、放送するときには気を遣っていただかないといけないということが、今回のメッセージだと思っている。
(F)
「容疑を認めている」とは、我々としては、要するに逮捕容疑を認めているという趣旨で書いているつもりだったが、そこを指摘されたので、今、いろいろ揉んでいる。実態はケース・バイ・ケースだが、なるべく分けるようにして書く、逮捕容疑と警察の経緯の見立ての部分は分けて書くが、放送時間が短くなると、どうしても経緯の部分とか動機の部分が重要だったりするので、一緒になってしまって、このまま逮捕容疑を認める、一部を認めるにしようかみたいな、いろいろな議論をしているが、ちょっと難しい部分がある。
BPOの意見は承るが、なかなか原稿に書くと難しい部分があるなというのが現実の問題、現場がやっぱり混乱して、ずーっとそういう状態が続いているが、それはちょっとご理解いただきたいと思う。
副署長が言ったからといって、余分なことを書くべきではないと言うと、若干、現場が萎縮する。やっぱり副署長が言ったこと、取材のやり取りで聞いたものを書くのが記者だと思う、特に第一報であれば。
(坂井委員長)
余分なことを書くべきじゃないというような、シンプルな言い方はしていない。そういう考え方もケースによったらありますよね、ということを申し上げた。事案によってはこの段階では書かないという選択肢もあるかもしれない、書くのだったら、誤解されないように書いたほうがいいのではないかと申し上げた。
(G)
両局ともフェイスブックの写真を使っている。フェイスブックの写真を大写しで放送に使われたことが、どれぐらい申立人の不安というか怒りの部分に影響しているとお考えか?
(坂井委員長)
ヒアリングのときの話は正確に思い出せないが、やっぱり写真を大きく出されたことは、かなり彼にとって大きなことだったのじゃないかなという印象は持っている。それで、彼は肖像権侵害と言っているわけだが、それは違いますよと、我々は思っている。
ただ、肖像権の問題は、法律的にはまだきれいに整理されていない。著作権に関する報道引用の問題と肖像権の問題は違うので、これから議論して行かないといけない。フェイスブックの写真について、犯罪報道の時には写真を使っていいよという考え、要するにフェイスブックの写真は公開されるという前提だから、今は使うことが基本的にOKだろうという方向で扱われているが、本件のような見方をする人が増えてくると、配慮が必要な場合もあるかもしれない。別の集まりで、軽井沢のバス事故の被害者の写真について、あのケースはどうだったのだろうかとテレビ局の方と話をしたことがある。フェイスブックから引っ張ってきて写真を載せたテレビ局は多くあったと思うが、被害者のほうでも、載せてOK、むしろ載せてもらいたいという方たちがいる一方、いや、こういうところで、そういう写真を使ってほしくないという遺族の方がいるので、これからきっと議論されていくのかなという気がしている。
(市川委員長代行)
たしかにフェイスブックの全身に近い画像が、しかも複数回出てきているところがあって、ちょっと通常の写真の扱いとは違うところがあるのかなとは思う。それは権利侵害とか問題があるとは我々は考えなかったが、ここまでやるのかと、申立人は思ったのかもしれない。どこが彼の琴線に触れたのか、正直、そこまではヒアリングのときには分からなかったが、その扱いの違いというものがあるかもしれない。そこは少数意見として曽我部委員がちょっと触れているところではあるが、果たしてここまでやる必要があったのかという問題意識は、私も無いわけではない。
(曽我部委員)
ヒアリングのときの若干の記憶がある。申立人はフェイスブックに写真は載せるが、それはまさに知り合いとかと交流するために載せるのであって、たしかに一般公開の設定にしてはいるけれども、そういう本来の目的と違う文脈で使われるのは心外であるというようなことは、たしかおっしゃっていたような気はする。
多分、そういう感情は割りと一般的で、フェイスブックのルール上は一般公開で何に使われてもしょうがないとなっているはずだが、ユーザーの意識はそこまで割り切れてなくて、やっぱり全然違う文脈、とりわけ自分が被疑者扱いで使われることは、当然想定していなくて、非常にわだかまりを感じるということは、ある意味理解できる。
(G)
今回は写真の出どころがフェイスブック、自分が載せたフェイスブックだが、昔は知り合いから顔写真を提供してもらうというパターンだった。そういう写真か何かであれば、こういう問題にはならなかったということか?
(曽我部委員)
昔だったら卒業アルバムとかの写真を使っていたと思うが、あれも、卒業アルバムに載せた本来の目的で放送で使われているわけではないという意味で同じだとは思うが、やっぱり感情的には大きな違いはあるとは思う。
(G)
おそらく熊本の地元にとっては、市役所の職員が逮捕される大きい事件で、おそらく全社が扱っていたのかなと思うが、新聞も含めて同じようなことが書かれているにもかかわらず、なぜ申立て対象がこの2局だけだったのか、問題ありと認定されたのはどうしてなのか?
(坂井委員長)
当時、熊本で公務員不祥事が続いていたということもあって、当然、熊本の民放、NHKも含めてテレビ局はみんな報道している。なぜ、この2局なんだということは、やっぱり当該局も思っていらっしゃるようだ。ただ、我々としては申立人からそこを正確に聞いたわけではないが、おっしゃるような扱い方だとか写真の使い方が影響したのだろうなと私は思っている。彼は報道されているときは逮捕されているから見ていない。出てきてから報道されたものを見て2局を選んだということなので、それは、当然、放送内容で選んだと思う。
(市川代行)
我々もほかの局の放送は見ていないので、ちょっと比較のしようがないというところがある。ただ、印象としては、たしかに写真の問題というのは、彼があえて2局を申し立てたという中にはあったのかもしれない部分と思う。それから、ほかの局や新聞報道はみんな同じ内容だったと言えるかというと、違いはあるだろうし、実際に新聞報道もよく子細に読むと、警察の見立ての部分の書き分け方などでニュアンスは違うなと個人的には感じている。
(H)
全体を通してだが、委員会の中で、少数意見をどういうふうに考えてらっしゃるのか伺いたい。NHKのSTAP事案も、それからこの熊本の事案も少数意見があって、少数意見があるから、当該局というか、各局の中にやっぱり戸惑いが結構ある。必ずしも決定文が十分理解されてない部分があると思う。
放送局にとって、人権侵害とか放送倫理違反は大変重い決定で非常に重く受け止める。特に今回のように複数の少数意見が付くのであれば、人権侵害とか放送倫理違反の認定にあたって、もう少し議論を集約させるまで慎重に審理をしていただくとか、何かそういうことは考えられないものなのか。あるいは、少数意見がある場合に決定まで持ち込む、ある種のコンセンサスというか、どういうルールでやっておられるのか?
(坂井委員長)
運営規則上は全員一致とならない場合は多数決でこれを決する、可否同数の場合は委員長が決するという規定だ。全員一致なら、それは一番分かりやすいけれども、最後は結論を出さないといけないので多数決で決めるしかない。
具体的にどうやっているのかというところは抽象的にしかお話できないが、9人全員に意見を自由に言ってもらう、率直に言って意見が違うときは、かなり激しく議論をする(笑)。それが収れんしていって、意見が全員一致になれば全員一致の意見になるし、そうじゃないときは少数意見を書いていただくようになる。少数意見を書かれる方も、もちろん最初から結論を持っているわけではないから、「うーん・・・」ということで、ある時点で「やっぱり書きます」と、そういうことになる。
少数意見があるということは、私はあまり否定的に考えていない。例えば、普通の裁判所の3人の合議体では少数意見は書かない。実は割れていたかもしれないが、少数意見は書かれない。しかし最高裁ではある。委員会では少数意見が出ることによって、委員会でどういう議論がなされたか、中身が見えてくるので、私は個人的には肯定的に捉えている、ああ、そういう議論をしたんだなと。それは、例えば人権侵害ありと言うときに少数意見があるのか、それとも放送倫理上問題ありと言うときにどういう少数意見がどれだけあったのかで、方向性が全然違ってきて、際どいところで人権侵害にならなかったというケースもあり得るし、逆にギリギリのところで人権侵害があったと判断されるというケースもあり得るわけで、そういうことが少数意見の存在で分かってくる。3人ぐらいの少数意見があったケースは過去に何度かあるが、どういう議論がなされて、判断の違いがどこにあるのかが、むしろ分かったほうがいいのではないか。
STAP事案でも少数意見はあったが、これは人によって判断が変わってくる領域で、数学の計算式みたいに答えが一つしかないという問題ではなく、また、時代が変わったりすれば見方も変わってくる。委員会がどういう議論をしているのかが見えるという意味で、全員一致であれば一番分かりやすくていいが、議論をしても一つにまとまらない場合、少数意見の人はこういうふうに考えたということが分かることを、むしろプラスに考えていただけないかなという気がしている。
(市川委員長代行)、
起草担当者としては、委員の皆さんの意見も聞きながら、最大公約数の部分を取り込みつつ議論・起草をしているつもりだが、やはり、そうは言っても、どうしても多数意見の枠外に出ざるを得ないという意見が出てきてしまうことがある。どうしても一つに全部まとまるというのは難しいなというときもある。最初から少数意見を書くことありき、ということでは決してない。
以上