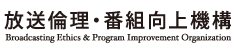第107回 – 2005年12月
「新ビジネス”うなずき屋”報道」事案の審理
審理要請案件「バラエティー番組における人格権侵害の訴え」…など
「新ビジネス”うなずき屋”報道」事案の審理
本事案は、テレビ東京の〈消える高齢者の財産〉というタイトルのドキュメンタリー(2005年6月14日放送)の中で”孤独老人相手の新商売”(うなずくだけで2時間1万円)として紹介された東京在住の男性が、この放送により名誉を毀損されたと苦情を申し立てているもの。
これまで双方から提出された申立書や答弁書等をもとに3回にわたり審理(ヒアリングを含む)を行ってきたが、12月の委員会では、起草委員会でまとめた委員会決定の草案について意見を交わし、「現金の受け渡しシーン」や「番組の趣旨と構成上の問題」等について一部加筆修正を含め、詰めの検討を行なった。
その結果、年末年始をはさんで「委員会決定」を最終的に作成し、次の定例委員会当日の2006年1月17日に申立人・被申立人双方に通知し、その後記者会見を開いて同決定を公表することになった。
審理要請案件「バラエティー番組における人格権侵害の訴え」
有名タレントである妻と2005年8月に離婚した東京在住の男性が「バラエティー番組における元妻の発言等によって、名誉・プライバシー権の侵害を受けた」と放送人権委員会に苦情を申し立てていた事案に対し、協議の結果、2006年1月から「審理入り」することが委員会決定された。
当該番組は、関西テレビ制作の<たかじんの胸いっぱい>で、申立書によれば、2005年6月25日の放送にはタレントである妻本人がゲスト出演し、夫の性格や性癖について赤裸々に語り、また離婚直前の7月9日の同番組では、妻は出演していなかったものの、他の出演者たちが先の妻の発言にもとづいて、夫の性癖等について再びトークを繰り広げた。
これらの発言に対し、申立人は「話されたことは、全くの虚偽であるか、あるいは面白おかしく事実関係を歪曲しており、いずれも自分の社会的評価を低下させ、名誉を著しく毀損・侮辱するものである」と主張、局に対し「取り消して謝罪する旨の放送」を求めた。
これに対し、局側は「放送法4条1項は、権利侵害を受けた本人が事業者に対し、訂正又は取消しの放送を求める私法上の請求権を付与するものではない」とした最高裁判例を引用、「本件内容からして、取消し・謝罪の放送を行う必要はない。また、指摘された発言は、申立人の妻が離婚報道の前に自ら話したものであって、司会者や制作者らの恣意的なリードによってなされたものではないことからしても、申立人の要求には一切応じられない」としている。
「犯罪被害者等基本計画案」について
事件・事故の被害者の報道で、実名か匿名かの発表判断を警察に委ねるという政府の「犯罪被害者等基本計画案」について12月の委員会で意見を交わした。
主な意見は次のとおり。
- 実名か匿名かの判断主体は報道機関で、警察が発表権限を持ってしまうのは危険だ。
- 実名はイヤだという「個人的感情」と知りたいという「公の利益」の対峙だが、後者が優先すべきと思う。
- 放送人権委員会は第3者機関であって、メディア・報道機関ではない。その放送人権委員会にこの問題で何が出来るか。
活発な意見交換を経て、放送人権委員会としてはこの問題について何らかの意思表示が必要ということで一致し、近々に「声明」ないし「要望」を出すことになった。
注記:この「犯罪被害者等基本計画」の閣議決定が12月27日にあった。放送人権委員会では同日この問題について
「声明」を発表した。(「声明」は後掲)
苦情対応状況[11月]
2005年11月の1か月間に寄せられた放送人権委員会関連の苦情の内訳は、次のとおり。
◆人権関連の苦情(27件)
- 斡旋・審理に関連する苦情(関係人からの人権関連の苦情で、氏名・連絡先や番組名などが明らかなもの)・・・13件
- 人権一般の苦情(人権関連だが、関係人ではない視聴者からの苦情、または、氏名・連絡先や番組名などが不明なもの)・・・14件
最後に、次回は「新ビジネス”うなずき屋”報道」事案について2006年1月17日午後2時半からの通知、午後3時半からの記者発表し、その後定例の委員会を午後4時から開くことを決め、閉会した。
以上
放送と人権等権利に関する委員会(放送人権委員会)
委員長 飽戸 弘
急激な社会の変化の中で、人々は内外の複雑困難な問題に直面し、とまどいと混迷を深めている。平和で安全な日々の暮らしを守るためには、生起する事態についてその真実を究明し、原因や問題点を明らかにすることが何よりも必要である。人々はこうした情報の提供を受けて自ら意見を形成し、それを自由に表明することを通じて、自らの生活を守り、社会をよりよい方向へ導くことができる。
そのためには、メディアにより、人々への必要かつ有益な情報が十分に提供されなければならない。メディアはこの点で重要な役割を担っており、人々の知る権利に十分に応えるべき責務がある。
本日、内閣は犯罪被害者等基本計画を閣議決定し、犯罪被害者の氏名を実名で発表するか否かを警察の判断に委ねることとした。
しかし、犯罪被害者の氏名は事実の確認や検証のための取材の出発点であるから、今回の措置は情報の流れを事前に警察当局が封鎖することに等しく、メディアによる情報収集を困難にし、人々がメディアを通じてその情報を受け取る自由を制約する結果を惹起することを否定しがたい。
これまで、メディアの側において犯罪被害者らに対し、無神経な取材や行き過ぎた報道がなされたことは事実であり、真摯な反省が求められているところである。しかし、現在メディアはその反省に立って、取材については平成14年4月、日本新聞協会が「集団的過熱取材対策小委員会」を設置し被害防止を図ってきている。また、行き過ぎた放送による被害については、平成9年5月NHKと民間放送各社において第三者機関としての「放送と人権等権利に関する委員会」を設立し、多くの苦情を受け付け、被害を訴える者と当該放送局との間の斡旋解決を図るとともに、現在までに17事案26件について決定を出して放送被害の救済に努めてきている。今回の措置は、当委員会のこうした努力やその果たしている役割を軽視するものと言わざるを得ない。
犯罪被害者の実名開示の可否の問題は、被害者間でも意見が分かれているところである。これに対する対応は、報道関係者が取材の際に被害者との信頼関係を築きながら、事件の社会的性格への配慮と被害者の希望を尊重・配慮することにより自主的に解決すべきであって、犯罪捜査に直接関わる警察に判断を委ねることで解決すべき問題ではないと考える。
以上のとおり、民主主義社会を根底から支える報道の自由の見地から、警察が情報の流れを事前に抑制することとなる今回の閣議決定は報道の死命を制しかねない重大な問題であることを広く訴えるとともに、内閣に対しては同措置を早急に改めるよう強く要望する。