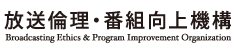青少年委員会は全国各地で様々な形の意見交換会を開催しています。今回は岡山・高松地区の放送局とBPOとの相互理解を深め、番組向上に役立てることを目的に本年(2023年)2月9日午後2時から5時まで、岡山市で初めて意見交換しました。
BPOからは青少年委員会の榊原洋一委員長、緑川由香副委員長、飯田豊委員、佐々木輝美委員、沢井佳子委員、髙橋聡美委員、山縣文治委員、吉永みち子委員の8人の委員全員が参加しました。放送局からはNHK(岡山放送局、高松放送局)、RSK山陽放送、岡山放送、テレビせとうち、西日本放送、瀬戸内海放送、岡山エフエム放送、エフエム香川の各BPO連絡責任者、編成、制作、報道番組担当者など計24人が参加しました。
《【テーマ1】「痛みを伴うことを笑いの対象とするバラエティー」に関する見解について》
まず、「テーマ1」として青少年委員会が昨年(2022年)4月15日に公表した「痛みを伴うことを笑いの対象とするバラエティー」に関する見解について、榊原委員長らが説明し、その後、意見交換しました。
〇榊原委員長
青少年委員会がこの「見解」を出すに至った経緯を説明します。
英語ではエンパシー(empathy)といいますが、共感や共感性というのは、私たちが他人との間で同じ考えを持って、他人が苦しんでいるときにはこちらも苦しみ、他人が喜んでいるときはこちらも喜ぶ、そういう人間の持っている大きな精神的なあるいは心理的な力です。どういうものに共感を得るのか得ないのかは個人差がありますが、これはどんな人にもある感情です。
ではどのようなプロセスを経て、子どもが共感性を身につけていくのか。これは乳幼児の心理学あるいは脳科学の大きな課題でした。自然にそういう共感性が芽生えるのかというと、どうもそうではない。人間の脳の中に経験を重ねることによって共感が生じるような脳の仕組みがあるのだ、心理の仕組みがあるのだということが徐々にわかり、そのトピックスとして挙がってきたのが「ミラーニューロン」です。人間の大脳のうち前頭葉の一部にある、この「ミラーニューロン」と呼ばれる神経の働きだろうと分かってきました。
ミラーニューロンによる共感性の獲得の道筋には、一つのシナリオがあります。私たちが他人の苦痛、表情を見る。そうすると自分のミラーニューロン系が、自分が苦痛を受けたときと同じように活動します。そのときに、その苦痛を受けている人を誰かが助けたり、慰めてあげたりするのを見ると、慰められた人の苦痛が減るだけでなく、それを見ているほうも苦痛の表情が和らぎます。このミラーニューロンを通じて、そういう感情といいますか、それが伝播するような仕組みがあります。このようなことを何度も見ていると、子どもは何か痛い思いや苦しい思いをしている人を助けるという行動によって、自分もそれから解放される経験を得て、自分もそういうのを見たら助けてあげようという気持ちを後押しする、そういう働きをするのだろうと言われています。これが向社会的行動の強化と共感性の発達です。
痛みを伴うことを笑いの対象とするバラエティーについては、若手の芸人が何らかのことで罰ゲームさせられる場合が多いのですが、何かすごく痛くなると。それは痛いわけで、見ているほうも痛そうだと感じます。問題はそこがダブル構造になっていて、スタジオにいる先輩の芸人たちが、若手が痛がっているのを見て皆で笑うわけです。それを私たち視聴者は見ている。特に小さい子どもが見ると、ミラーニューロンが働いて痛いはずなのに、それを笑って見ている大人が一緒に見える、こういう構造になるわけです。
それでなにが起きるかというと、ひとつは、苦痛を感じている人を誰かが嘲笑している、笑っているのを見ると、共感性の獲得の道筋がブロックされてしまい、自分の苦痛の元であるミラーニューロンの活動性が低下しません。さらには向社会的な行動を強化するとか、共感性の発達につながるルートに、必ずしもよくない情報が入ってくることになります。
もうひとつは、大人がそういう痛みを伴うものを見て笑っているのですから、小さい子どもの中には、こういうことは世の中で笑ってもよいのだという気持ちが育まれて、いじめなどにつながる可能性があります。
もちろん1回の番組だけでそうなるわけではないし、多くの経験を経てなるわけですが、テレビはいつでも、みんなよく見ています。回数を重ねることによって、そのような問題が起きるのではないかという懸念があり、それが「痛みを伴うことを笑いの対象とするバラエティー」に関する見解を発表した経緯なのです。
〇緑川副委員長
「痛みを伴うことを笑いの対象とするバラエティー」に関する見解は長文ですが、全部を読んでいただければ、必ずしも「痛みを伴う罰ゲーム、イコールNG」ということではないと、ご理解いただけると思います。
テレビ局は公共の電波の使用をすることができる位置にいて、公共のための放送をする責任や使命を負っています。子どもたちに対して、教養の形成であるとか、いわゆる公共善の実現に向けて考え続けるという観点も大切だと思います。表現や演出については、面白さを追求することの重要さ、そして、そのために限界的な表現に挑戦していくことの重要性を意識して、常にブラッシュアップをしていかなければならないだろうと思います。そして、その時々の社会の状況であるとか社会通念の変化、それから、最新の脳科学などによる知見、例えば子どもの発達心理学的な研究成果などについても謙虚にそのような情報、知見を取り入れて、さらによい番組にしていくという態度が重要なのではないでしょうか。
そういう考え方で、最新の脳科学の見地から、「ミラーニューロン」という知見を番組制作している皆さんと共有することによって、よりよい番組を作っていくことに役立ててほしいという理由で、今回の見解を出したことをご理解いただきたいと思います。
<意見交換>
〇参加者
ローカル局でいうと、このような「痛みを伴う」というのは制作の現場では、それほど機会はありません。ただ、BPOの見解が出て以降は何かしら罰ゲームというのはNGみたいな雰囲気があるように思います。ある場面の痛がるようなところだけを切り取られて延々と流すということになると、これも駄目なのかという感じを持ちます。
またテレビだけではなくて、ネットである部分だけ切り取られてとかSNSで流されるとか、どこまで気をつければいいのかなというのも気になります。
〇佐々木委員
ネットだと、場面を部分的に切り取ってしまうことだと理解したのですが、そうするとテレビの場合は、これこれこういう文脈でこれぐらいのものだったら、最後にみんな仲良くなっているから許容されるし、それほど大きな悪影響はないと思います。ネットの場合は文脈が分からないので、暴力シーンなどの一部分だけを見ていると、やはり結果がどうなったかが分かりません。そうすると、過去の研究で暴力シーンの結果が分からない場合は、まねされることが結構あるという結果が出ています。その暴力行為が最後に罰せられるなどの結果が示されない場合は、ネット上の切り取った画像はちょっと問題だと思います。
〇飯田委員
いわゆる「切り抜き動画」と言われるものかと思います。ネットで流通しているものは、動画を制作したユーチューバー自身が短く切り抜いて拡散しているものもあれば、テレビ番組を録画して、それを第三者が切り抜いてネットで拡散させているものもあります。中にはバラエティー番組の制作者自身が、ネットでバズらせることを意識して作っている動画もあるでしょうし、千差万別です。単に切り抜いただけでなく、第三者によって合成が入ったりコラージュが入ったり、何らかの加工があって拡散するところまでいくと、それはもう制作者がコントロールできない範疇の話です。制作者自身がネットでバズらせることを意識したのであれば、それがもたらす結果に一定の責任を持つのが制作者の倫理だと思います。しかし、意図しないかたちで拡散された切り抜き動画に関しては、これは倫理の問題というよりも、技術の変化に対して放送局と制作者の双方がその状況をどう受け止めていくのかという、ちょっとレイヤー(階層)の異なる課題かなと思います。
〇参加者
さきほどネットと言ったのは、特に我々の場合、ニュースはまず放送ですが、ネットに上げることも当たり前になっている。番組もユーチューブに上げるのが当たり前になっています。ネットのことを考えないとやっていけませんし、やらないといけないのだという認識です。その中で一部切り取られた部分が流れるという心配があると思いました。
笑いに関して僕は、痛みを伴うというよりも非常に良質な笑いというか、考えさせられる笑いというか、落語などのきちんと順序立てて笑うというものが良質な本来の笑いだと思っています。ただ、今のテレビでは一瞬、一瞬で本当に10秒に一回笑わせることを迫られている中で、じっくり10分間聞いて「アハハ」と笑えるようなものはできないと思います。
〇参加者
2021年度に中高生モニターから意見を聞いたときのやり取りには、どのようなものがあったのか、気になりました。
〇榊原委員長
BPOには中高生モニター制度があって、30人ぐらい中高生に異なる形式で2回ほど、「痛みを伴うことを笑いの対象とするバラエティー」に対してどう思うか聞きました。意見は分かれましたね。「面白い」という生徒がいる反面、「見ていてあまりいい感じがしない」という意見があって、どちらかというと、批判的な意見がやや多かった気がします。
あの見解が出たので、「私たち、僕たちにとって、とても面白いんだ」という答えだけが来るかと思ったら、そうではなかった。中学生でもかなり分析的な視点でいろいろ書いてくる生徒がいます。逆に「とても面白いバラエティーが、もしかすると減るのでさびしい」という意見もありました。両方あったということです。
〇髙橋委員
BPOに寄せられる意見は「これはいかがなものか」のようなものが多いため、ネガティブなフィードバックのほうが多いのは仕方がありません。「よかった、よかった」という感想は寄せられなくて、「BPOに通報」という感覚の視聴者意見が多いのではないかと思います。これが本当に大多数の意見なのか、あるいはノイジー・マイノリティー(声高の少数者)なのかは見極めなければならないと感じます。
今の子どもたちはテレビを直接見るのではなく、様々なアプリで見ることがあります。その一方で、私たち(委員会)はテレビとラジオの放送しか対象にしていないため、それはこれからの課題かなと思います。
〇参加者
ひとつすごく厄介な暴力的な問題があって、それは言葉の問題です。人の劣っているところを突っ込んで嘲り笑うような笑いがあって、身体的痛みは伴いませんが、心はすごく傷つきます。笑いの中の毒舌的なものは皆がまねします。人を傷つける言葉の暴力は、どこかでしっかりブレーキをかけさせないといけないと、かなり前から思っています。
〇緑川副委員長
言葉による暴力というのは、おっしゃる通りです。今回の見解は暴力的な肉体的な痛みの演出がきっかけになっていますが、このミラーニューロンの共感性の発達の阻害という視点からは、決して肉体的な痛みだけを対象とするものではないと理解していただければと思います。暴力というのは、肉体的なことだけでなく言葉による暴力、それを嘲笑するのがあまりいい影響を与えないのではないかということを含めて今回の見解を出しました。
私たちは、テレビ局の制作者の表現の自由を制約するという機関ではなく、逆に表現の自由を内側からさらに深めていく、深化させるために、テレビ局の皆さんが「自主自律のために」作った委員会で委員をさせてもらっていると思っています。私たちは第三者ではありますが、自主的に設立運営している機関であるからこそ、このような意見を出すことで、表現の自由の外部からの制約ではなく、中からブラッシュアップしていくためのきっかけを提供できているとすれば、たいへんありがたいと思います。
〇吉永委員
BPOに来る意見で、「問題だ」と指摘される番組は高視聴率なのです。見ていて「これはな」と思うものでも視聴率が高いと、なかなかそこに手を入れるのは難しい。今の民間放送の置かれている現状を考えると、「すごくいい番組をつくりました。けれども視聴率が取れませんでした」とすると、その作り手は結局、何の評価もされずにいい番組を作ったという自己満足だけで終わってしまう。いい番組を作っていこうという気持ちの継続に繋がっていかない気がします。だから、「うけなかったがすばらしかったね」ということを評価する軸を新たに入れることで、流れを変えていくことを考えてなければいけないと思います。
《【テーマ2】「事件や事故などが発生した際の目撃者である青少年、子どもに対する取材、インタビューの可否や妥当な方法」について》
「テーマ2」と「テーマ3」はそれぞれ、地元局の代表社による具体的な問題提起を受けて意見交換しました。
〇代表社の問題提起
これから2つ映像を見てもらいます。最初は36年前の1987年に起こった事件で弊社が放送したものをそのまま流しますが、今ではたぶん放送できません。人通りの多い商店街を自転車に乗ったまま通る人たちが多いことが問題になって、警察が取り締まりをします。その中で、道交法違反で15歳の少年が逮捕されます。<映像上映①>
これは当時そのまま放送されたと聞いています。ぼかしを入れずに少年の顔が出ているのは、おそらくこのぐらいなら(よいだろう)という判断が当時はあって、撮影するカメラが、多少顔が隠れるような形で撮ったもののままでしょう。そういう判断で放送したと聞いています。少年の顔だけでなく、おそらく今では放送できないものがいくつもあります。まず自転車に乗ってはいけないところで乗っている人を普通に撮影しているとか、それから警察が違反切符を切っているところを撮って、住所を書いているところも撮影しているなどです。さらに、手錠を15歳の少年にかけていること、後ろ姿にしていますが連行される状況を、そのままの形で撮影しているところもです。
ただ一方で、見たときに映像の持つ力の大きさというか、逆にそういうものも感じます。これで全部分かってしまうという感じです。翌日に、(視聴者から)電話が殺到したそうです。これを放送したこと自体についての意見ではなく、少年に対して「警察が注意をしたにもかかわらず逃げたのはいかん」という意見だったり、警察が逮捕するのは「やり過ぎである」という意見が出たりということでした。
次に紹介するのは2018年に、児童の列に車が突っ込んでいくという事故がありました。その翌日の放送です。<映像上映②>
このときは、被害に遭った児童の友人や、ご家族とか、そういったところへの取材を控えるという形でした。その結果、亡くなったお子さんのことは市教委が記者会見を開いて、こういう子だったという発表があっただけです。
三十数年前と、5年ほど前の事例ですが、状況がずいぶん変わったなという印象です。どちらが、当時の記録やニュースとして伝えられるものが多くあるのかといえば、もちろん最初のほう(映像①)があるとは思います。ある程度制限をしていくことによって撮影できないというか、できるところがどんどん減っていくのを感じます。情報源が限られる中で、一次情報である家族や子どもたちに取材する、しないというのは本当に悩ましいところだなと思いました。その2つの時代の映像を比べてご意見をうかがいたいと思います。
*****
青少年委員会は2021年10月6日に、映像②と類似の事件である、千葉県八街市で起きた飲酒運転による児童5人死傷事故で被害者の同級生へのインタビューを放送した番組について「通学中に起きた児童の死傷事故についての未成年者への取材のあり方に関する《委員長コメント》」を出しました。「テーマ2」の意見交換の参考になるこの委員長コメントについて、緑川副委員長から説明がありました。
*****
〇緑川副委員長
2021年10月6日に青少年委員会から、通学中に起きた児童の死傷事故についての未成年者への取材の在り方に関する委員長コメントを出しました。事故の状況については、さきほど紹介された2番目の事故(映像②)に酷似しているかなと思います。(八街市内で)通学途中の小学生の列に飲酒運転をしている車が突っ込んで5人が死傷するという痛ましい事故でした。当時のニュース番組で亡くなった子どもの友達、同級生にインタビューをした映像が流されました。これは顔が出ていて、どのように感じたかという亡くなった友達に対する気持ちを聞いているというインタビューでした。
これに視聴者から、「事故によるトラウマを想起させ二次被害につながるのではないか」「こういう場合は専門家であっても慎重な対応が必要とされる場面である」と、それから「この被害者が通っていた学校では事故の翌日には子どもたちの心のケアのために休校にしている。そういう状況だったのに、ほかの子どもや保護者の心は考えなかったのか」などの意見が多く寄せられました。同級生に対するインタビューをニュースで報道したテレビ局に、そのときの状況等について質問をし、回答をもらいました。
そのなかでテレビ局側は、その子どもの保護者から承諾を得た上でインタビューしたということです。一部で亡くなった子どもに対する気持ちを尋ねる中で、誘導とも取られかねない質問をし、それに子どもが「そうです」と答えるシーンがあり、その質問手法について「討論」のときの検討対象になりました。これについて、(局側の説明では)放送ではその場面が放送されたが、その前段階の取材の中で、そういう気持ちが話されていたものの、テレビカメラを回す段階では、子どもなのでうまく言葉が出てこなかったということです。その結果、はっきりと意図が分かる部分を放送する対応になったということでした。
しかし、事故直後に亡くなった子どもについてインタビューをすることは、その報道の必要性、つまり事故の悲惨さを伝えて社会全体で共有して同じことが起こらないように皆で考えるための報道の必要性はもちろん肯定できると考えるものの、そのための手段として事故直後に直接子どもにマイクを向けることには、やはり更なる配慮が大切ではないか。そういう問題意識のもとで、この委員長コメントを出しました。
さきほどの2番目の映像は、そのあたりが配慮された内容になっていたと拝見しながら思いました。亡くなった子どもがどういうお子さんだったのかということを校長先生と、お花を供えにいらした人でしょうか、大人に対するインタビューによって、亡くなったお子さんがどういう状況であったのかということが報道されたので、報道の必要性、報道するという趣旨に沿った報道ができていたのではないかなと感じました。
〇榊原委員長
亡くなった子について「(質問される子の)お友達でなくてよかったね」と、すこし誘導して、本人が「うん」とうなずくような(答えでした)。お友達でなくてよかったね、というのは、これは本人が言い出したことではありません。そう言われれば、直接よく知っているお友達ではなくてよかったと(答えた)。これがなぜ問題かというと、それで事故のことを思い出すということ以外に、その画像が保存されて、この子が大きくなってから、あるいはその後で周りの人が見て、この子は「自分のお友達でなくてよかった」と言った。そこだけ切り取ると「何て子だろう」と思われる。そういうことが二次的に、このインタビューを受けた子どものトラウマになっていくのではないかと思います。
〇髙橋委員
まず、友達の声が、果たして国民にとって本当に必要な情報なのか。本当に必要な情報というのは、おそらく、(事故を)再発させないために有用な情報であって、さまざまな人たちへのインタビューが必要な情報なのかなということを、もう一度考えねばならないと思います。また、インタビューに答える子どもが緊張していると笑ってしまうことがあります。そうなると、「あの子は大変なときに笑っていた」などと、ネットやSNSでバッシングが始まったり、二次的な被害がネット上で起こったりするのが、今の世の中です。
では保護者の許可があればインタビューしてよいのかという話ですが、事故直後にインタビューすることが子どもの心を傷つけるという認識が保護者になかった場合、(保護者が子どもを)守ってやれません。やはりこれは報道のプロである皆さんの常識として、直後にインタビューするのは子どもにとって心理的な影響があることを意識しながら、報道してもらえればありがたいと思います。
<意見交換>
〇参加者
事故直後の現場に子どもがいた場合、時に取材活動の一環として状況を聞かなければいけないのではないかと、取材者がそう思うのもあり得ると思います。そこのバランス、要するに子どもに声をかけること自体が子どもの心を痛めてしまうのか、話の内容によっては聞いてみるという判断があるのかどうか、取材している現場の記者はけっこう悩むポイントになると感じました。
〇榊原委員長
八街の場合は、その報道がいわゆるニュース、報道プロパーではない人がインタビューしています。つまり、それが本当に報道として伝える必要があるのかという問題と、総合的に見て報道番組とは必ずしも言い難いワイドショーや情報バラエティー番組が、話を聞きに行くことがあります。その辺の線引きが難しくなったという意見も私たちの中で出ました。純粋な報道としては髙橋委員の言う通り、それはどこまで伝える必要があるのかを判断すべきです。しかし、話題性になりますと、ちょっと視点が違います。その辺をどう分けるのか、かなり悩ましい課題がありました。
〇参加者
とにかく(取材現場では)何が起こったかを知るのが一番です。それ(取材相手)が子どもしかいないときは、これはもう聞かざるを得ないのかなと思います。ただ、テレビの取材活動として聞くものと、カメラを向けてそれを証言として繰り返し流すことによる子どもへの影響は考えないといけない。それには放送しないという判断もあるかもしれません。しかし、取材活動としては、何が起こったのか、それを誰も知らない場合に、もし友達である子どもしか知らないのなら、聞かざるを得ないという判断になると思います。
映像②の場合は、お子さんはこういう子どもだったと、市の教育委員会が発表しました。そういう取りまとめをどこかの機関が発表するのがいいかどうかも難しいところです。どこも出さないとおそらく、どんな子どもだったかを近辺で聞いて回ることになりますが、「それはやめてほしい。学校がきちんと対応する」と周知すれば、(取材者側は)いったん落ち着くでしょう。ただ、果たして学校側の「こういう子どもだった」というのが本当にそうなのかは、実際の友達に聞かないとわからないところがあります。言い方は悪いのですが、学校は「こういう子どもなんだよ」とある程度統一して発表するでしょうから、一次情報としては近所の人や友達などの声をどうしても聞きたいという気持ちになります。一方で、「子どもに影響があるんです」と、さきほど(委員が)言われました。保護者の同意があったとしても子どもへの影響を理解していない保護者がいるのだから、取材する側がきちんと理解してやらなければならないのだというご意見でした。それも全くそうだなと思いますから、ケース・バイ・ケースで、やはりそれぞれ悩ましいなと受け止めました。
〇参加者
さきほどの岡山県赤磐市で5人の小学生の列に車が突っ込んだ事故(映像②)では、仮に私がその現場に取材記者として行っていて、あの5人の中に1人でも無傷の小学生がいたら、その子のインタビューをトライすると思います。なぜかと言えば、あの事故は突っ込んだ車の女性ドライバーが居眠り運転か何かで、(ブレーキとアクセルの)踏み間違いが原因だったと思いますが、それは結果としてのちに分かったことで、事故の時点ではまだ分かっていません。もしかしたら、無傷の子どもに聞けば、事故が起きたときの状況がくわしく分かるかもしれないと考えます。事故の全容をつかむために、現場にいる子どもにインタビューをトライするのは、記者として当然のことだと思います。後輩からどうするべきかと聞かれたら、「取材しろ」と言うと思います。
ただ、無神経にテレビカメラを回してインタビューを撮るというやり方を選ぶのか、保護者に取材して、それからお子さんの了解を得た上で(カメラを回さず)話だけ聞いて、それを記事として書くのかは、また別問題です。「子どもに取材することはちょっと遠慮してください」という風潮が広がると、全くそういう取材をしなくなることをすごく危惧していて、取材するということを我々がどんどん怠ってしまうのではないかと、思いました。
〇髙橋委員
事故を目撃した子どもに直接取材することは、とても大事だと思いますが、複数の新聞社やテレビ局が同じ子どもに何回も何回も聞くことになると、その子は何回も何回も答えなければなりません。もう一点は、各メディアが同時に聞くと、大人がずらりと並んだ中で答えねばならない恐怖感があります。警察がある程度聴き取りをするはずですから、警察から聞くという方法があるかもしれません。(子どもに)何回も何回も聞くということの害があるかなと思います。私は東日本大震災(2011年3月)のときに宮城県に住んでいましたが、震災遺児に関しても、「あの子は答えてくれるよ」となると、各社がその子にインタビューしに行ってしまうということがありました。子どもが何度も話をしなければならないことを懸念しています。
〇参加者
例えば地元のメディアが代表者1人を決めて、その人間だけで取材をするという方法を取ったらいかがでしょうか。
〇髙橋委員
そういう配慮があればいいとは思いますが、現場に駆けつけた警察や消防の方々は第一発見者である子どもに対しては、かなり配慮をしながら事情を聞いているので、たとえば警察や消防などのノウハウも少し分けてもらいながら聞くというのが大事かなと思います。絶対聞くなという話ではありません。聞き方(の問題)だと思います。
《【テーマ3】「大規模災害時等における避難所での被災家族、特に青少年、子どもへの取材、インタビューの可否や妥当な方法」について》
〇代表社の問題提起
「テーマ2」と似ている話で、大規模災害時にどのように被災者に接するかは現場の課題です。(取材相手の)年齢制限についての考え方や、インタビューしないで表情だけを撮るという行為はどうなのか、その辺のことも現場のスタッフが来ていますので体験を聞きながら進めさせてもらいます。広い意味で、大規模災害時の現場でどういうことに気をつけねばならないのか、そういうところの意見交換、共有ができればいいと思います。まず、いま現場で活躍している我々のスタッフに話を聞いて、現場で気をつけているのはどういうところなのかを話してもらいます。
〇代表社の参加者①
もう30年近くずっとニュースのカメラマンをやっています。若いころは災害の現場に行くと、とにかく安全に気をつけながら映像を撮って早く放送へ結びつけることが使命でした。インターネットが普及し出すと、現場での我々取材陣の立ち居振る舞いが非常に見られていて、その立ち居振る舞いが被災されている人たちを傷つけたり悲しませたりすることになって、そこは「非常に気をつけるように」と言われています。スタッフ同士での話す内容に気を付け、冗談も言わないし、被災された人たちのことを考えて、自分たちの食事をどこでとって取材を続けるかをよく考えます。
大事件とか大災害があった後に、ネット上で「マスゴミ」という言葉が出るのが非常にショックで、たとえ直接自分が言われなくても同業者が「マスゴミ」と言われるのはやはり何か悲しいなと思います。我々は何のためにそこに行って、社会のためにやっているのかと。皆の役に立てばと思ってやっているのがごみと言われるのは、非常に残念です。どうしたらそのようにマスコミ全体が言われなくなるのか、何かいい方法がないかなと思います。
〇代表社の参加者②
私は火事の現場などに取材に行ったりすると、マスコミの姿勢というのも同時に見られているなというのをインターネットやツイッターなどのコメントを見て感じるので、なるべくそのように思われないような取材をしていきたいと思います。
〇代表社の参加者③
まず避難所ということだと、皆さんも避難所を管理している人たちの承諾を得た上で中に入って取材すると思います。その上で、青少年、子どもへのインタビューはどのようにするかということです。大規模災害になると、余計に保護者の了承なりあるいは横にいてもらうことを、十分留意しながらインタビューしているのではないでしょうか。
私が現場で記者をやっていた何年も前と比べると、いま話にも出たようにSNSなどですぐ発信をされ、特にメディアに対する批判的な見方がだいぶ強まっていることはあるでしょう。相当慎重にそのあたりの立ち居振る舞い、態度に気をつけなければならないだろうと思います。それに、一度放送に出した後、当初は本人も保護者にも理解が得られていたけれども、何度も放送で使っているうちに、「もうやめてください」となることもよくあります。そういうことも想定しながら、現場で工夫されていると想像します。
<意見交換>
〇参加者
弊社も、岡山県が放送エリアに入っていて、西日本豪雨(2018年7月)の取材経験があります。避難所取材では、当時実際に取材に当たった記者からのヒアリングしたところ、避難所開設から1週間ぐらい経って取材したケースですが、当初は被災者のプライバシーが守れないという理由で、基本的に取材が全面NGになりました。その記者ら取材班が、当時管理運営していた倉敷市と交渉して、条件付きで取材を許可してもらいました。
管理事務所を訪れて取材内容などを説明した上で、カメラでインタビューする場合は当然、本人の了解を得てから行うとか、居住スペースに配慮をする、プライバシーに配慮するなど当たり前のことばかりでした。阪神・淡路大震災(1995年1月)のときに僕も被災地に入りましたが、どうしても前のめりになってしまう自分がいたのを思い出します。そういうところはカメラクルーなり取材班として、お互い気をつけ合いながら取材しないといけないと思います。
青少年に対してだと、さきほど委員が話されたように、子どものインタビューは、そのときは答えてくれても後で違うなど、いろいろあるのだろうと思います。やはり、保護者の同意は最低限得ないといけないと思いますし、実際あった例では、オンエア後に「使ってほしくない」といわれるケースが最近増えています。ネット時代で速報性がとくに言われるようになって、カメラで撮れたからそのまま、すぐ(放送に)出そうというところがあります。だからこそ、特に事件・事故現場、災害現場などではより慎重にしないといけないと最近感じています。
〇榊原委員長
私たちは経験がありませんが、記者が取材しているときにいろいろお考えになり悩まれると、その視点はとても重要だと思います。特に子どもの場合は難しいのですが、その子どもの個人情報の問題だったり、その子が将来、心理的あるいは周りからいろいろ言われて、トラウマになったりすることがあります。どこまで報道するかという難しさは、私が共感の話をしましたが、例えばあるニュース報道の中で子どもがとてもひもじい思いをしている表情を見ると、共感で「みんなで助けよう」となります。その情報が何なのかというと、大地震の数値や被災者の数などの単なるデジタルなものではないのですから、皆さんが悩んで、どうしたらいいのかと常に反すうしながらやるなかにしかないと思います。さきほど紹介された(1987年の報道事例である)15歳少年の自転車のこと(映像①)については、「今ではこんなのはもう出せません」と言われた。それは、今までの経験の中で培われてきたことだと思います。
直近の例では、(2月6日に起きた)トルコとシリアの地震報道を見ていると、小さな子どもががれきの間に挟まって、妹を36時間ずっと守っていた話がありました。その子の顔が映されてすごくつらそうに頑張っているのを見ると、それは共感を呼び起こして、では助けるために募金ができないかと感じます。たぶん記者のみなさんは単純なデジタルな事実だけでなく、こういうことを伝えたいのでしょう。そこをどう切り取るかという線引きが難しいだろうと思って聞いていました。私も記者だったらきっと悩んだだろうと思います。
〇沢井委員
北海道で臨床心理士をしている友人(女性)から聞いた話ですが、避難所の子どもたちがどういう状態であるかをきちんと調査したのは、奥尻島の大津波災害(北海道南西沖地震。1993年7月)のときでした。あのとき奥尻島から逃げた家族が北海道内の避難所にいました。
子どもたちが避難所内の遊び場で友達と「きゃっきゃっ」と遊んでいます。それをアナウンサー、取材者が「(被災者の)大人は大変だけれども、子どもたちはこんなに生き生きと元気に過ごしております」と感動をもって伝えました。臨床心理士としてそこで子どものケアをした友人に聞くと、まず子どもについて注意しなければならないのは元気過ぎるときで、これは非常に不安の表れであって、それを「すごい、すごい、子どもは元気でたくましいですね」というコメントでよいのだろうかといいます。国民全体に誤解を与えることになるという。表面的なところを見て、記者は事実だと思ったかもしれませんが、災害の後に子どもを含めて被災者がどのように心理状態が変わっていくかということを知らなくてはいけないでしょう。
臨床心理士の彼女は、阪神・淡路大震災のときに奥尻島の知見を基に、「こういうことに気をつけてください。元気そうということで安心してはいけません」と、テレビの報道番組にも出て注意喚起しました。私も「阪神」のときには、心理学スタッフとして加わっていたテレビ局の関係者がアメリカFEMA(連邦緊急事態管理庁)のマニュアルを取り寄せてくれたので、そのマニュアルを読んで、被災した子どもにどういうケアが必要かをきちんと調べました。
それによると、災害の直後は全ての人が、隣近所も一緒に同じような災害を受けているから、非常に連帯感を持って英雄的でとても人格者に見える行動を取るし、そういう発言を皆がします。皆が謙虚で、大変だったよねということで、ある意味高揚感に満ちている。その次のステージは(それぞれの環境に)だんだん格差が出てきて、さまざまないざこざが起きることなどが、研究されています。現在では(マニュアルが)さらに進化していると思いますが、そういうことはもっとマスコミが報道する、あるいは取材をする人たちに共有されていいのではないかと思います。日本はどう防災するかという面が多いのですが、被災者の人たちがどのように心理的な心の変遷をしていくものなのか、一般的にはどうか、もちろん個別にはいろいろ異なる反応もあると思いますが、皆に共通する点は学んでおいたほうがいいと思います。無知ゆえに過剰に解釈したり、過剰に一般化したりという報道があると、歴史的にもいろいろと傷をつけることになるし、誤解を広げることになるでしょう。
フェイクニュースではないけれども、人間観察の浅さによって、それが事実であるかのように報道されてしまうことがあります。これは子どもに対する場合に限らずあると思うので、FEMAのマニュアルなどをチェックしてください。また集団心理あるいは子どもの心理について、子どもの発達段階ごとにその認知がどう変わってきて、目撃者としてどれだけ信頼性があるかということも、子どもの目撃者の研究をしている研究者がいるので、そういうことの知見をぜひ参照していただきたいと思います。
〇吉永委員
大規模災害の現場を取材するというのは本当に怖いものです。言葉が出なくなってしまう。取材する側の人間力というのがもろに試される現場だろうと思います。私は阪神・淡路大震災のときには、声を出すことすらできなくなりました。ところが、私が親しくしていたベテラン・ジャーナリストがいて、あの人は普通そこら辺で私たちと一緒に飲んでいるときと同じような感じでススッと近づいていっては「話し聞かせてんか」と言う。その相手の人も、私だったらとても受け付けないような雰囲気の人が話してくれるのです。巨大な悲しみとか、巨大な怒りが渦巻いている現場に入っていく恐ろしさというのが、私には無理だと当時思った経験があります。
だから、その中で何かを撮ってこなければならなくて行くのがどれだけ厳しいことか、と思います。そこに行くに当たって予備知識なり勉強なりしていく、あるいはそこに体力的にぎりぎりの経験をしている人が聞くほうが本当の答えが出てくると思います。体力の問題とか現場の厳しさとか、体力的に危険なところであるとなると若い人になるのでしょうが、そういうものであることをおそらく感じて帰ってきたでしょう。それを次に生かすために自分の経験を後輩なり皆に共有する場を作っていくこと、それが人間の力をつけることだと思います。
沢井委員が話したように、私も北海道の地震のときに、家族が皆生き埋めになった状況でひとりだけ元気、その子だけ助かった男の子のインタビューがあって、その子がものすごく明るかったのです。テレビの取材と私の活字の取材とは全然違って、活字は映像がないので、この子がいくら目の前で笑っていても、その中の何かを感じ取ったら、それを言葉に変えられます。しかし、映像の持っている力が言葉を超えてしまうと、「この子は何か全然、平気なんだね」というメッセージになってしまって、この子の一生にどれだけつらい思いを残してしまうのかと考えると、もうつくづく大災害の報道というのは難しいと思います。
避難所に入っていくことひとつですら、私たちは公共の建物に入っていくような気持ちですが、あそこは(被災者の)生活の場なのです。(取材者が)そこに入っていくという意識を本当に持てるのか持てないのか、何かそういうことによって中身が変わってきたり、ひとつの映像から、ひとつの言葉から受ける印象が見る側に与える影響も違ってきたりすると思います。
〇山縣委員
「テーマ3」では、私の印象でもあまり子どものインタビューは出てきません。学校が被害に遭った場合には、子どもに聞いていることもありますが、基本的には大人が語れる場合には大人で語らせるという判断になっているのではないかと思います。一方で、子どもが一番の当事者であるとか、真実を語ることができる状況になったときには、おそらくすごく苦しまれているのではないかと思っていて、その部分はきっと正解がない状況で考え続けるしかないのだろうというのが、私の印象です。
〇髙橋委員
東日本大震災のときに私は仙台にいました。テレビや新聞の記者たちがその現場を見て衝撃を受けて、PTSDになる案件が重なりました。その後の研究でも、取材をした記者たちが後々、PTSDのような症状が現れることが分かっています。さきほど「マスゴミと言われて傷つく」ということを話していましたが、これは自衛隊員の調査でも「早くやれ」「もっとやれ」「何やっているんだ」「寝ずにやれ」などと怒られた自衛官に鬱(うつ)の発症率は高くなっています。だから取材する皆さん自身も、現場を見て傷ついていることを認識しておくのはとても大事だと思います。
《【テーマ4】 フリートーク》
「テーマ4」では議題を特定せず、参加者に自由に質問してもらいました。
〇参加者
1月15日に京都で行われた全国都道府県対抗女子駅伝で、岡山県津山市の中学3年の女子選手が17人抜きしたことが全国ニュースで報じられ、話題になりました。2週間後に岡山県内で市町村対抗の駅伝大会がありましたが、多くのカメラ取材が予想され、本人が非常にナーバスになっているという情報があったため、地元の民放テレビ5社とNHKについては当日、共同取材という形式で取材しました。
その5日後、2月3日に地元の記者クラブの加盟社に、女子選手の代理人弁護士から、「環境の変化で練習が以前のように自由にできなくなった」とファクスがありました。「過度な報道で精神的にも疲れることが多かった」、そして「可能な限り普通の生活をしながら陸上競技を続けていくことを希望します」というコメントがありました。
この話題は新聞やテレビでも報道されましたので、委員が感じたことをお聞きしたいと思います。
〇緑川副委員長
私は弁護士をしていまして、以前から報道問題に関わってきました。数十年前のことですが、 (事件の)被害者だったり加害者の近隣住民だったりして、メディアスクラムの被害を受けたという人たちにヒアリングをしたことがあります。被害者救済活動をする弁護士がまだあまりいなかった時代です。そのころ、メディアスクラムの被害に遭った人たちから、「誰に相談していいか分からない、どこに行っていいか分からない」、また「メディアの人たちは親切な人もいるけれども、だまされたような感じで出ていったら写真を撮られてしまった」という話を聞いたことがありました。
今回、中学生でしたが、(選手としての)自分の生活を守りつつメディアにも対応していきたいと考えたときに、代理人の方から連絡が来たという話を聞いて、30年経ってそういう経路ができてきたのかなという感想を持ちました。取材者と被取材者の関係ですから、時代が流れていくことによって必ず動いていくのだと思います。その都度、お互いが工夫しながら、考えながら、よりよい取材ができることを期待しています。
〇榊原委員長
この女子選手は中学生で未成年ですが、未成年の人の意見をどのように取り上げるかは社会全体の問題だと思います。今まで子どもの声を聞くときには親(保護者)が代弁者だというのが前提でしたが、必ずしもそうでない。さきほどの議論で、子どもが(事故直後の)インタビューを受けることのトラウマなどについて親(保護者)が、よく考えない場合には、取材者側が考えてやらなければならないと、ありました。一番の問題になるのは、児童虐待やネグレクトの場合で、このときは親子が対立するわけです。
この中学生の場合、弁護士を通じて(取材者側に)申し入れてもらうというアクションをおこし、この30年の間にそうしたことが取れるようになったという意味で、大したことになったなと思いました。
〇参加者
3年目の記者です。LGBTQをテーマに取材をしたり番組を作ったりしてきました。その中ですごく思うのは、LGBTQという枠があるからこそ救われたという人がいれば、自分はそうした枠にとらわれたくないからそのように描かないでほしいという考えの人もいるので、放送で描くときに表現の仕方に気をつけないといけないということです。
半年間、高校生の当事者の取材をしました。その子は、体が男性で心は男性でも女性でもどちらでもないという子でしたが、学校の男女別の頭髪基準をなくすための活動をすごく頑張っていました。でもその放送に向けて、どういう描き方をされたくないかと聞いたところ、その子は「枠にとらわれたくない」ということでしたから、視聴者に分かりやすくその子の性別を説明するのに、その枠を言わずにいかに理解してもらうかを考えました。また、学校と親(保護者)と三者合わせて話し合う機会を何度か設けて、表現をどうしていくかという話をしたのですが、「こんなに心配されるのは、自分はやっぱり普通じゃないからかな」と、その子自身が思ってきたりして、すごく難しいなと感じた取材の一つでした。当事者の取材だったり、特に未成年だったりする場合に、気をつけることや、描き方がありましたら教えていただきたいです。
〇飯田委員
これまで中高生モニターのリポートの中で、男女二分法を前提にしてつくられている番組に対する違和感のような意見が、たくさん寄せられています。例えば、テロップは男性が青で女性が赤、みたいな区別を無自覚にやっている。そういうものに対して、「今はそういう時代ではないんだ」と、学校でも(ジェンダーの多様性について)学んでいる世代ですから、(学んだことと)テレビの表現のギャップを感じる若者が増えてきていると思います。
それから、最初に話されたLGBTQという概念がなぜ当事者たちにとって必要だったかと考えると、ある種の運動や連帯のための用語だったことがあります。それに対して、レズビアンとバイセクシャルはまったく違うのに「一緒にされたくない」と、性的マイノリティー同士での差別を経験することもあるようです。LGBTQという言葉の持つ功罪といいますか、ある意味では必要だった言葉ですが、それで全てが解決しているわけではないという状況があります。若い当事者の人たちは、このような歴史的な経緯を知らないわけですから、取材をして本人が何を思っているのかを拾っていくことは大事ですが、逆に一緒に勉強して教えてあげることによって解決できる部分も多くあるのかなと思います。そういう意味では少し時間をかけてお互いに理解していくことが大事でしょう。
あと、カミングアウトしている人としていない人がいるわけで、統計的に見ても実は性的マイノリティーはそんなに少ないわけではなくて、一説には8%、数え方によりますけれども、3%から10%ぐらいが何らかの形で性的少数者と言われています。(取材対象者がこうしたことを知ることで)自分が置かれている状況を必ずしもネガティブにばかりとらえなくなっていくことは必ずあると思います。
それからもう一つ。LGBT(Q)という言葉は2000年代後半にNHKの番組で精力的に使われていて、そういうところをきっかけに広まった言葉と思いますが、最近はダイバーシティ(diversity : 多様性)という言葉がよく使われます。LGBTQがダイバーシティに置き換わったことで、人それぞれ、いろいろという理解がより一層広がった面があるかなと思いますので、こういうことは当事者にとっては非常に追い風であり、よい傾向かなと感じています。
〇榊原委員長
ラジオ(エフエム)局の参加者にも、全体の議論を聞いてみてご意見があればお聞きしたいと思います。
〇参加者
ラジオは、1対1というメディアで、車の中で1人で聴いていたり、部屋で1人で聴いていたりという、あくまでも1対1のメディアということを心掛けています。そういう意味ではやはり身近な存在で、あなたのためだけに放送しています、と考えてやっています。ラジオはなかなかテレビと違って、つける習慣がないと聴かないものですが、いったんつけ始めるとそれは温かいものであり、目には見えませんが、心に響くすごく素敵なメディアだと思っています。
〇参加者
きょうはテーマがすごく大きくて、うちも考えねばいけないなと思いました。例えば、僕らも街角で子どもにインタビューすることがありますが、おいそれとしてはいけないのかなと少し怖くもなりました。ただ、どちらかというと僕らは、生活に根差した共感というところを大事にしながら放送しているので、そういう意味では「遊園地って楽しいかい?」などと聞くようなインタビューなわけで、さほど深刻になる部分はないかもしれません。
しかし、常日ごろから、ひとつひとつ気を配って考えていかないと、ふとしたときに何か全然意図しないことを言ってしまうことがあるのかなと、きょうの話を聞いていて思いました。
特に声だけしかないメディアですので、その声の調子であるとか、よく最近は「言い方、言い方」と言われますが、それ一つで随分と印象が変わってしまうこともよくあるので、ラジオだからこそ気をつけなければいけないこともたくさんあるのだなと思ったしだいです。
〇榊原委員長
みなさま、本日はどうもありがとうございました。
事後アンケート 概要
意見交換会の終了後、参加者全員にアンケートの協力を依頼し、約7割に当たる17人から回答を得ました。その概要を紹介します。
- ▼ (テーマ1)「痛みを伴うことを笑いの対象とするバラエティー」に関する見解について
- ローカル局ではあまり、差し迫った事例はないが、制作者としては、頭にとどめておくべき問題だと改めて感じた。また、委員の皆さんが、決して、罰ゲームがダメだとは考えていない、ということが確認できたのはよかった。いじめにつながるだとか、度をこえたものだとかではなく、しっかりとバランスを見ながら番組制作していきたい。
- バラエティー番組において他人の痛みを伴う事を笑いの対象とするものはかなり以前から多くみられる。また、人気芸人などのタレントのみならず、素人相手にそのような手法を用いてバラエティー番組を制作するケースすら見られる。規制すべきか否かの境界線が不明瞭なこのような手法を制作者が用いる時、その判断基準をどこに設定するべきかという困難なテーマは常に付きまとう。ただ、テレビメディアに携わるスタッフはその影響力の大きさを常に自覚しておく必要はある。その思いを一層強くした。
- ニュース制作に携わる中で、あまり意識をしたことがない分野であったが、視聴者への影響を考える上で重要な議題と感じた。医学的知見から放送を考えるということは、これまで行ってこなかったので、今後のニュース制作でも、事実を伝える上で必要な一方、内容に衝撃をうける可能性がある映像を扱う場面など、必要に応じてさまざまな視点を取り入れて考えられるよう努めたい。
- ▼ (テーマ2) 「事件や事故などが発生した際の目撃者である青少年、子どもに対する取材、インタビューの可否や妥当な方法」について
- 子どもの気持ちを思いやり、コンタクトや取材の方法、タイミング(時期)を熟慮する必要がある。常に取材を控えるということではなく、事実を伝えるためには、保護者の理解を得るなどした上で必要な取材はするという姿勢が大切だと思う。また各社で話し合い、代表取材なども取り入れ、メディアスクラムは避ける必要がある。
- テレビだけでなく配信もされるようになり、子どもの発言・映像も半永久的に残ってしまうかもしれない現在では、放送後のことも考えて取材をすることが肝要だと感じました。だからと言って「取材しない」という選択肢はないと思うので、ケース・バイ・ケースでの対応をマスコミ全体が考えていかなくてはいけないと思いました。
- 子どもを守る観点からと、知る権利に奉仕するという点から、いつも悩むこと。BPOが、どのようなスタンスで意見をおっしゃっているかがわかった。親(保護者)に承諾を得ていても、子どもへの影響について理解していない親がいるので取材は慎重になってほしい、という話があったが、難しい課題だと感じた。
- ▼ (テーマ3) 「大規模災害時等における避難所での被災家族、特に青少年、子どもへの取材、インタビューの可否や妥当な方法」について
- 避難所での取材も本人や子どもの場合は保護者の了解を得て行っているが、子どもの場合は、元気過ぎるのは不安の裏返しということもあるので、取材者も子どもの心理などについて学ぶ必要がある。記者は日々の取材に追われがちなので会社でそういう場を設けることも考えないといけないと感じた。
- 大きな衝撃や喪失を感じる被災者への取材方法については、答えが出ているものではないが、避難所取材でも、生活の一部を見せていただくという意識を持った上で、代表撮影や場所を指定した取材の交渉など必要な情報の発信と被災者へ過度な負担をかけない報道を両立できるようにしたい。
- ▼ フリートークやそのほかの意見、BPOや青少年委員会への要望など
- ジェンダー問題や障害者に対する意識は急速に変わってきている気がする。先日も街頭インタビューで「障害者手帳を持っている」というコメントに一瞬ひるんでしまった。最新の意識調査の結果や世の中の潮流には常に気を配っていなくてはならないと感じていたので、非常に参考になった。
- 放送だけでなく、今やデジタル展開は、放送業界では当たり前になっている。BPOも放送だけでなく、放送のネット展開も、考慮に入れないといけない時代になっていると感じた。委員の負担は大きくなるでしょうが。