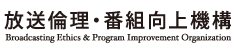近畿地区意見交換会を開催
「SNS時代の選挙報道 局の垣根を越えて議論」
放送人権委員会の近畿地区意見交換会が2025年2月3日に大阪市で開催された。近畿地区での開催は、2019年以来6年ぶりとなる。前年の2024年秋に行われた兵庫県知事選挙で、SNSが有権者の投票行動に大きな影響を与え、また25年も7月に参議院議員選挙が行われることなどから「SNS時代の選挙報道はどうあるべきか!」をテーマに意見交換を行った。近畿地区の20放送局から約100人が参加し、SNSで拡散されるデマや誤情報への対処、選挙報道における「公平性・中立性」の問題などを論点に3時間にわたって活発な議論が展開された。
●曽我部委員長「選挙における放送の役割が問われている」
会議の冒頭あいさつに立った曽我部委員長は「放送界のあり方が深いところで問われる局面がこのところ続いている。放送は民主主義が機能するために不可欠で、選挙は民主主義の根幹の一つであるから、選挙に関してこそ放送はその役割を発揮しなければならないはずなのに、それができていないのではないかと今日改めて問われている。」と述べた。さらに「放送界全体として、放送法や公職選挙法の改正、あるいは法解釈の見直しを国に対して提案することも求められる一方で、個々の放送局としては、今の法律を前提として何ができるのかを考えていただく必要があると思っており、本日の議論をそのための一助としていただきたい。」と語った。
続いて、毎日放送 報道情報局東京報道部部長兼解説委員である大八木友之氏が兵庫県知事選挙を現場取材して浮き彫りになった課題について語った。
<毎日放送 大八木氏>
●エポックメイキングな選挙だった
今回の兵庫県知事選挙の街頭取材では、これまでの知事選挙とは異質な熱気、うねりを感じた。現場ではテレビで伝えてきたこととの乖離が起きており、SNSをきっかけに演説会場に来た聴衆からは「テレビに騙された」などと厳しい言葉が投げかけられた。
なぜテレビが厳しい言葉を浴びたのか、その要因は選挙の前と後で変化した報道量にあると考える。告示前は斎藤知事関連で多くの報道があったが、告示後はニュースや番組での取扱量が明らかに減少した。それは例えば、伝えることで特定候補に有利又は不利になる情報は扱わないなどと判断したためであるが、もう一方では生の情報番組が単純化した構図やキャッチーさにこだわるあまり、複雑なテーマを噛み砕いて伝える難しさを避けてしまうような傾向も手伝ったのかもしれない。その結果、テレビが選挙期間中に報道量や頻度を減らす一方で、ネットやSNSの世界で動画の投稿数や閲覧数がどんどん増えていくという現象が起きていた。
●テレビは選挙という「面倒ごと」を避けてきたのではないか
テレビが選挙期間中に報道量を減らすことは、有権者が投票に際して最も欲しいと思うタイミングで情報を提供しないということにつながっている。それは長年の課題であり葛藤でもあるが、どこかに甘えがあるとも思う。
敢えて本音と建前という言い方をすると、建前としては放送法や公職選挙法を遵守して各候補者や政党を中立・公平・公正に取り上げる必要があるからとしながら、本音としては陣営・政党・視聴者からのクレームを避けたい、面倒を避けたいという理由から、結果的に自らその報道量を減らしているのではないかと感じる。
●テレビは「政治的公平性」に縛られているのか?
BPOの放送倫理検証委員会は、今回の兵庫県知事選挙から7年も遡る2017年の委員会決定で、選挙報道に求められるのは、事実を偏りなく報道し、明確な論拠に基づく評論をする質的公平性だと指摘している。
また、総務省幹部は「放送法に書かれている政治的公平性については、それをどう解釈してどう報道するのかは自主自律の話だ」と見解を述べる。
つまりBPOからも総務省からも各社の判断で選挙報道を行うよう促されているのだが、今後の選挙報道を変えていくにあたって質的公平性をどう担保するかは非常に悩ましい。
●兵庫県知事選挙で何が突きつけられたのか?
今回の兵庫県知事選挙で突きつけられたのは、一つは結果偏重の報道からプロセス重視に移ることだと思う。選挙は結果が大事であり、それこそ与野党の過半数などは意識してしまうが、これまでの放送は選挙結果を伝えることに重きを置きすぎたきらいがある。テレビは人員・予算を大幅にかけて投開票日に特番を放送するが、有権者はやはり実際に投票に行く際に有益な情報を事前に提供してくれる番組や記事を求めており、そこにきっちりとコミットできる報道が求められる。
もう一つはまさに今回欠けていたと反省する点だが、ネットやSNSと対話をしていくことが大事だと思う。例えば選挙期間中に取材したことや街頭で起きていることを発信したり、ネットやSNS上で話題になっていることを情報の正しさ、誤りを含めて伝えたりすることができる。それをやらないことで「テレビは無視している」「私たちの声を取り上げていない」「街で起きていることを伝えていない」と批判されるのであり、普段の番組でやっているのと同じようにネットやSNSとの対話を繰り返し、取り上げていくことが必要ではないかと思う。
●これからの選挙報道は…
これからの選挙報道をどうするかについては、それぞれの選挙に応じてやり方はいろいろあると思う。投開票日だけにこだわらない事前の特番、ネット世論やSNS上の言説のファクトチェックのほかにも、有権者ファーストから入る報道、政策やイシューを重視した報道などができるのではないか。
また、放送局はすでにWEB配信を行っているので、そこを十分に利活用する手があると思う。地上波では時間的な制約があるが、WEB配信でそうした物理的な制限がなくなれば、各種討論会を開催したり、記者や解説者が出演して今起きていることを伝えるなどして有権者に判断材料を提供していくことができる。
答えがない世界ではあるが、頭を悩ませて、結果的に今回の兵庫県知事選挙が選挙報道を変える良いきっかけになるように、ひいては民主主義の最大の手段である選挙をきっちりと伝える役割を担えるようにしていきたい。
- 大八木氏のプレゼンを受けて、メディア論が専門でSNS問題も研究テーマとする松田委員、兵庫県出身の斉藤委員が意見を述べた。
●松田委員「視聴者の感情面での公平性を考えた報道を」
質的公平性について、視聴者が感じる感情面での公平性をどのように考えるのかが非常に気になった。今回の兵庫県知事選挙と似ていると言われるものの一つに「推し活」がある。有権者は自分が応援する候補の選挙戦に参加して、演説会場などいろいろなところに見にいって応援する。かつ、候補者もSNSで活躍するインフルエンサーやYouTuberと同じように、見せ方を工夫し、自己演出する。そんな選挙戦では有権者の感情が非常に動く。
その一方で、放送局が斎藤知事に対して「パワハラ」「おねだり」と繰り返し報道するのは、旧態依然たるメディア側が古くさいレッテルを貼って個人攻撃をしているという感情を持たれてしまっている。推し活には「お互いの『推し』について悪く言わない」という暗黙のルールがあって、お互いに好きなものをそれぞれ応援するといった振る舞いがSNS上でウケる状況の中で、放送局が古くさいレッテルを貼って上から目線で攻撃するというイメージが感情的な反発を引き起こしたのではないかと思う。
このため質的公平性においては、情報の内容としての部分はもちろん重要であるが、一方でSNS時代を考えたときには、視聴者の感情にどう訴えるかについても考える必要があると思う。
●斉藤委員「スピードよりも、信じられる情報を」
BPO委員というよりは個人的な意見になってしまうが、兵庫県知事選挙の後で神戸の友人たちに話を聞くと、反応が重く歯切れが悪かった。みんな何が本当なのかわからない様子で、選挙の話題を振ると気まずい雰囲気になってしまった。
私もパワハラやおねだりの報道があり、県議会から全会一致で不信任決議を受けたあたりまでは、簡単に言うと「斎藤知事ってとんでもない人だな」と思っていたが、その後にSNSなどで「斎藤知事は実はよくやっていた」というような言説を見聞きすると、斎藤氏が知事の時にどういう政策をしていたのかあまり把握していなかったことに気づいた。候補者の人間的な面を伝えることももちろん大事だが、政策や実績、注目される問題についての考え方など、有権者として自分が求めるものに対する立場をきちっと伝えてくれる情報が欲しかったという友人もいた。
質的公平性の判断は難しいし、守りに入って報道を控えてしまうのもわかるが、SNSがこれだけ発達した中で、いま私個人がテレビの選挙報道に求めるのは、スピードではなくて信じられる情報だ。みんなが悩んでいるような問題について有権者と問いかけ合い、一緒に考えるような報道をそれぞれの放送局がいかに一生懸命頑張って発信するかが大事だと思う。
- ここから4つの論点について意見交換が行われた。
論点は、①拡散されるデマ・誤情報への対処、②取材者に対する個人攻撃のリスク、③公平性・中立性の“呪縛”、④SNS時代の選挙報道とは・・・、である。
論点①「拡散されるデマ・誤情報への対処」
●参加者「ファクトチェックが特定候補者を利する場合は?」
選挙中に流布されるSNS情報については、ファクトチェックが難しいだけでなく、そのファクトチェックの指摘が候補者の有利、不利に直結する場合は非常に躊躇してしまう。ファクトチェックを具体的に行ったために特定の候補者の報道量が多くなって、結果としてその候補者を応援しているように受け取られるのではないかと危惧する。
●曽我部委員長「指針を作って公平・公正に適用し、説明できることが重要」
私は日本ファクトチェックセンターの運営委員長でもあり、その観点からもお話ししたい。今後の選挙報道には質的公平が大事であるということだが、現実的にはこれまで量的公平を重視して報道してきたこと、さらには質的公平には基準や答えがないことから、いきなり量的公平から質的公平に移行するのは実際上大変難しいと思う。このため部分的に、できることから始めることを提案したい。
まずできることの一つは、ネットで流通する偽・誤情報に対するファクトチェック的な取り組みを放送番組とWEBの両方で行うこと。放送人権委員会の決定に判断のグラデーションがあるように、日本ファクトチェックセンターの判定基準にもグラデーションがある。ファクトチェックは「正確か誤りか」という二択ではなくて、「正確」「ほぼ正確」「根拠不明」「不正確」「誤り」の五段階があり、言説に対する評価のニュアンスを反映するような仕組みになっている。例えば「根拠不明」とは煮え切らないような感じだが、「この言説は根拠不明なのでよく注意してもらいたい」という視聴者への注意喚起になるので、一定の役割を果たすと思う。
もう一つは、最近は選挙運動期間中に突発的にいろいろなことが起きるので、それを伝えること。起きたことを伝えないと、逆に有権者の判断が歪んでしまう。最近「選挙ハック」的なものが多々行われているが、私が一番衝撃を受けたのは衆院東京15区補欠選挙でつばさの党が非常に妨害的な行為をしたことで、これがリアルタイムには全然放送されないということに極めて大きな違和感を持った。あれはまさに有権者の判断に資する情報であり、放送しないのは逆に公平に反すると思う。
特定の候補者に有利、不利に働いてしまうおそれがあるという点については、私はあまり気にする必要はないと思う。大事なのは、まず各局でファクトチェックの指針をきちんと作るということだ。日本ファクトチェックセンターでも、どういうものを取り上げるのかについて指針を作り、その上で指針を公平・公正に適用している。現状では偽情報を流す陣営が限られているので結果として偏ってしまうのが実情だと思うが、指針がしっかりしていて、その基準に従って取り上げていることをきちんと説明できるのであれば、公平・公正についての問題はない。ただ、理屈としては今申し上げたとおりだが、実際問題としてどうするかは、各社において工夫の余地があるかもしれない。
●参加者「候補者のプライバシー情報の扱いは?」
これまでは政策に関係のないプライバシー情報を地上波で扱うことは避けてきたが、SNSが発達して有権者の投票行動に影響を与えるようになった今、プライバシー情報の扱いについても議論が必要になってきているのではないか。
●松尾委員「プラットフォームに対応を求めるか議論が必要」
今、プライバシー情報の扱いについて問題提起を頂いた。
直接的には、いわゆる告発をされた方のプライバシー情報がSNSで盛んに取り上げられたこと等を念頭にテレビがどうすべきか、という文脈でおっしゃられていると理解している。とはいえ、なかなか個別事案についてはコメントすることができない反面、この問題は私も非常に悩ましい問題だと思っているので、特にインターネットにおいて、選挙にも影響がある形で虚実織り交ぜたプライバシー情報が広まるという問題について、どういうところが特に悩ましいのか説明することでご勘弁頂きたい。
インターネット上の虚偽情報、プライバシー侵害、名誉毀損情報等については、権利侵害や法律違反でプラットフォームに通告して削除を依頼する。やはり内容次第で、プライバシー侵害になりやすいのはいわゆる私人の行為。これに対し、選挙における公人の行為はなかなかプライバシー侵害にならない。
とはいえプライバシー侵害にならなくても、公職選挙法上は虚偽事項の公表罪があるので、違法情報として通告して削除することも一応はできる。これが理論的な帰結ではあるものの、ネット上にそうした情報が大量にある場合にはプラットフォームが迅速にすべてを削除するのは簡単ではない。逆にそうした精査をせずに削除する場合には、問題があることをしたわけでもないのにXのアカウントを凍結されるような事態も起きてしまう。
そのような観点を踏まえると、AIだけで自動的に対応するような雑な対応ではなく、やはりプラットフォームに相当なマンパワーを割いてAIと人間がタッグを組んで対応する必要があると思う。そして、確かに兵庫県知事選挙は大きな選挙なので、これに力を注いでくれといえば、プラットフォームとして力を注いでくれるだろう。しかし、1700以上ある自治体の個々の選挙すべてについてプラットフォームにそうした重い対応を求めるかは、さらに議論が必要なポイントだと思う。
さらに生成AI、特に画像生成AIが発展してしまったために、まるで本当にそういう事実があったかのような画像を簡単に作れるようになってしまった。
生成AIに対しては、電子透かし等とも言われるウオーターマークを埋め込んで、ウオーターマークが入っていたらそれが生成AIで作られたことがわかる、そうした特定の情報があるとプラットフォームは「これは生成AIでつくられた画像です」といった警告表示を出す、などの方向で一応動いてはいる。しかし、結局ウオーターマークはただの情報なので、一定の技術的措置を講じれば抜き取ることができる。
警告表示がなければ本物と認識される状況の中でウオーターマークを取り去って、プライバシーに関わるものを含むフェイクニュースを、選挙に影響を与える目的でアップロードすることも全く不可能ではない。特に選挙期間は2週間程度と短いので、そうした期間の短さを利用して、選挙戦の後半あたりにウオーターマークを取り去った偽画像をアップロードして選挙戦を有利にすることもあり得るのではないかと悩ましく思っている。
●参加者「人手をかけずにファクトチェックを行う方法は?」
今後SNS選挙が展開されるにおいてファクトチェックが非常に重要になるのは一致した意見だと思うが、チェックをしようにも人が足りないというマンパワー的な問題がある。何か具体的な方法を伺いたい。
●國森委員「選挙期間中に限らず、ファクトチェックにこそ労力を」
マンパワーがないという話だが、ファクトチェックにこそ労力を注ぐ時代が来ていると思う。視聴者の立場から言うと、選挙期間中に限らず、ネット上に流通している偽情報をファクトチェックするというテーマの番組があれば、私は是非観てみたいと思う。エンタメに偏りすぎずにジャーナリズムの視点を持って放送すれば、視聴者の希望に沿うような番組になるのではないか。
ネット上では、少数の人たちのネガティブなコメントや悪意、敵意が増幅され拡散していくので人権侵害が起こりやすい。その人権侵害の被害者には取材をする記者も含まれ、放送局は記者を守るという毅然とした対応を取っていく必要がある。ネット上で記者が攻撃に晒された場合には、民事や刑事の法廷にも持ち込んで、今ある法律を積極的に用いながら記者と放送局自身を守っていく。ネット上の人権侵害を絶対に許さないということを広く社会に訴えアピールしていく、こうしたことが放送局として必要だと思う。それは個別の放送局に限らず、放送業界、メディア全体として、公権力による言論規制を招く前にネット上の配信や投稿における人権侵害に対してしっかりと働きかけていくことが大事なのではないかと考える。
●曽我部委員長「午後8時の当落予測が最高のプライオリティか問うべき」
マンパワー不足は現実的には非常に深刻な問題だと思うが、そもそも選挙報道は何のためにやるのか、恐らくそういうところから考えていく必要がある。
放送局は今、経営の問題や働き方改革で人が増やせない、報道は大変な仕事なので人材が採れないなどの制約があり、今まで人海戦術でできていたことがだんだんできなくなっている。このため部分的に効率化しながら何とか今までどおりにやろうとしているのだと思うが、今後もずっとそれで行けるとは限らないし、そもそもそれが唯一の答えかどうかもわからない。そうであれば、選挙報道にはもっと大きな考え方の転換があり得るのではないだろうか。
例えば情勢取材は投開票日の午後8時から始まる選挙特番で出すことが本当に最高のプライオリティなのか、むしろ選挙運動期間中の議論を充実させることが有権者のためになるのではないかなど、本来いろいろな考え方があると思う。今のようなマンパワー不足を一つの契機に、もっと根底的に報道の仕方を考えることも一つのアプローチだと考える。
論点②「取材者に対する個人攻撃のリスク」
●参加者「リアルでもネットでも攻撃に晒される記者を守るには?」
今回の兵庫県知事選挙では、取材に基づいて斎藤知事が不利になるような報道をすると親斎藤派からネット上で批判され、会社のSNSがターゲットにされる事態が起きた。また、街頭で取材をしていた記者が暴言を吐かれたり、YouTube上で事実誤認の情報を発信されたり、写真を撮られてSNS上に晒されるなどして怖い思いをしており、記者を守るための方法を伺いたい。
●廣田委員長代行「誹謗中傷を甘受せず、法的措置など毅然とした対応を」
私は記者活動を法的に支援する団体を作る活動を始めたところだが、記者が人物を特定されて誹謗中傷されるということを最近あちこちで聞くようになった。報道はある意味、批判をするのが仕事なので、批判をされるのはやむを得ないとは思うが、当然ながら記者や報道機関が誹謗中傷を甘受しなければならないということではない。
誹謗中傷されて心が折れそうになったとき、何が支えになるかといえば報道する使命や意義、放送局で報道に携わるプロの記者としての誇りしかないのではないかと思う。今いろいろマスコミ批判がされているが、SNS上の言説との違いは事実の裏取りがされていること、何を報ずべきかをきちんと考えて報じていること、意見の対立があるときには自分の言いたいことだけではなく反対側の言い分も伝えて解説することで、これはプロの記者にしかできないことだ。最近では昭和の精神論は通用しないと言われるが、こと報道においては報道の意義、なぜ自分たちは報じるのかという原点が何より重要であるように思う。抽象的ではあるが今そうしたことが報道機関にとって一番重要になってきているので、何のために報道するのか、自分たちの報道がSNS上で飛び交う言説とどう違うのかを、年長者は若い人たちに常日頃から伝えていただきたい。
しかしながら精神論だけでは対応できないところがあるので、社内に相談窓口を設置して、一人で抱え込まないようにするのが重要だと思う。そして限度を超える誹謗中傷に対しては、マスメディアであろうと発信者情報開示請求などをきちんとして法的措置を取る必要もあると思う。また、産経新聞が自社の記者への誹謗中傷についてコメントを出したように、場合によっては社として対応することも必要になるのではないか。マスメディアが批判を生業にするものだとしても批判と誹謗中傷は違うので、言論のルールを示す意味でも誹謗中傷には毅然とした対応をしていただきたいと思う。
●松尾委員「報道への妨害、取材先からのハラスメントと捉えて対応を」
取材を申し込むと相手からYouTubeでの生配信を条件にされるなど、取材を取り巻く状況がかなり変わってきたと思う。その重要な原因としては、おそらく従前よりも取材や編集に対する信頼感が社会一般において低下していることが考えられる。これは取材を受ける側として、メディアの「編集」を信頼できず、いわば、勝手に「切り取られる」のではないかという不安があるためと思われるが、だからといって取材記者の個人情報を晒したり、虚偽情報を公表したりしていいわけではない。それは記者に対する人格権侵害であることに加えて自由な報道に対する妨害であり、やってはいけないことだ。
現在、東京都カスハラ条例等の形でカスタマーハラスメントが注目されているが、私はそうした度を越した取材対応は記者に対する一種のカスタマーハラスメントではないかと考えている。放送局では従業員がハラスメントを受けた場合の規定や相談窓口をすでに設けているところも多いと思うが、その枠組みの中に取材先からのハラスメントも入れて対応していくことが大事だと思う。
論点③「公平性・中立性の“呪縛”」
●参加者「放送法や公選法への勝手な思い込みがあるか?」
選挙報道に際しては放送法や公職選挙法を常々意識してきたが、その先の潜在意識としては、中身について深く立ち入って考えると相当なエネルギーを使うのではないか、相当なリスクがあるのではないかと勝手に思い込んでいたところがあるかもしれない。長年あまり深く考えずに量的な平等性を保つ選挙報道を続けてきたので、こちらが勝手に“呪縛”と思い込んでいる節は多分にあると思う。これまではトラブルやクレームを避ける意識が先行しがちだったと思うので、改めて選挙報道における放送法の解釈や、放送メディアに対するアドバイスをいただきたい。
●鈴木委員長代行「政治的公平は判定不能。偏りを排す自律的な努力を」
政治的公平について学者の間では、倫理的な規定にすぎない、法的には拘束力がないという考え方が従来から支持を集めている。最近では、放送法第4条の内容規制は刑法のように違反すると制裁を受けるハードローではなくてソフトロー、即ち業界のガイドラインのようなものだと説明する学者もいる。
総務省の解釈は1993年の椿発言事件以来「政治的公平には法的拘束力がある」という立場に変わって、違反をすると電波法第76条を適用して行政指導したり電波を止めることもありうるという解釈になっているが、これまで何回か行われた総務省の内容に関する行政指導は事実を曲げているかどうかとの関係がほとんどで、政治的公平に反したり抵触したための行政指導は本当に数が少ない。
つまり何が政治的に公平かはそもそも判定不能と考えて、放送局が自律的に守っていくしかないのだと思う。偏りがないように自分たちが努力さえしていれば、クレームが来ても、例えばこれは重要なイシューであるから、重要な候補者であるからと毅然とした態度で説明できるので、量で公平を図る必要は全くないと考えている。
とは言え、やはり質的に公平にしようとすると難しい。結局、質的公平を目指そうとすると、一つ一つの扱いについてちゃんと理由がないといけないことになる。それは大変であるし、また少しでも扱いが異なると候補者や政党からクレームが来たり、あるいは今ならSNSで反対派の人に批判されるなどいろいろな厄介ごとが起きるので、それを避けるには量的に公平にしておくのがシンプルであったと思われる。
ちなみに、安倍政権下では政治的公平の解釈について極端な場合は一つの番組でも政治的公平を測るとしていたが、総務省は公式にはこれを撤回していないものの国会答弁で当時の説明をしなくなっており、政治的公平は番組全体で測るものであり、放送局各社が自律的に考えるものだという以前のスタンスに戻っている。
こうして政治状況も変化し、今回の兵庫県知事選挙や東京都知事選挙のこともあるので、この機会に政治的公平を量で測る必要はもうないと考えて、ではどうすればいいのかを是非検討していただければと思う。
●曽我部委員長「質的公平の前提として選挙制度への理解と知識の継承を」
BPOの放送倫理検証委員会は、質的公平に言及した2017年の委員会決定第25号「2016年の選挙をめぐるテレビ放送についての意見」のほかにもいくつか選挙の公平に関して意見を出している。我々放送人権委員会は外部の意見として外から見ているので、真意を捉えているかどうかについてはお断りが必要だが、この中にヒントがあると思うので紹介したい。
2020年の委員会決定第35号「北海道放送『今日ドキッ!』参議院比例代表選挙の報道に関する意見」では選挙報道に関する放送基準を十分理解していないという重要な指摘がなされている。またそれに先立つ2014年の委員会決定第17号「2013年参議院議員選挙にかかわる2番組についての意見」や2010年の委員会決定第9号「参議院議員選挙にかかわる4番組についての意見」でも放送局は選挙制度の正確な理解等を徹底する必要があると指摘している。典型的な例は、参議院比例代表選挙は全国を対象にしているにもかかわらず、地元局がその放送エリア内の候補者だけを取り上げて、結果として不公平になったというもので、これに対し選挙制度の理解が足りないと繰り返し指摘され、そこに起因する放送倫理違反が繰り返し指摘されている。
質的公平を追求することは非常に難しい。量的公平には答えがあるが、質的公平には答えがないので、あとは説明責任でやるしかないが、その前提としてやはり選挙制度に関する理解が必要ということだと思う。また、何か拠りどころがないと質的公平の議論はできないので、制度理解のほかに今までの事例の理解や知識が必要だ。ただ、限られたスタッフで制作していることや選挙に詳しい外部の有識者が限られていることを考えると、質的公平にシフトしていくために理解や知識を深めるのは現実問題としてはなかなか難しいと思う。そうした中であり得る方法としては、社内の誰かが異動にかかわらず継続的に知識を深め、選挙番組のデスクやプロデューサーに助言をしたり相談相手になることから始めてはどうかと思う。
●野村委員「自分たちの考え方を謙虚に丁寧に説明して」
この公平性・中立性の問題については、我々が市民として常識だと思っていたことや、放送局が常識だから最後は視聴者に理解されるだろうと思っていたことが通用しなくなっている。今までは特に説明をしなくても「これはおかしい」と視聴者にわかってもらえるはずだったが、今は放送局が思う常識を謙虚に丁寧に説明することが求められている。
政治的公平の問題について、いま話があった、質的公平という観点を取り入れるとすると、こういう人を選んで、こういうことを取り上げます、ということを、放送の中で根拠を示して自分たちの考え方を謙虚に丁寧に説明することが必要になる。もしかすると、その説明は面白くないかもしれないけれど、放送局として面白く見てもらうことを優先するのか。それとも、少しつまらない部分や回りくどい部分が生じたとしても、放送局が選挙と市民の意見形成に対して蚊帳の外であってはいけないと考えて、有権者が考えるための適切な場としてあろうとするのかどうかが問われる。批判を受けることもあるかもしれないが、テレビが選挙にコミットすることが非常に大切であるので、何故これをこういうふうに取り上げるのか、頑張ってしっかり丁寧に説明していただきたいと思う。
もう一つ別の話になるが、選挙制度についてはこれまで公職選挙法のルールや手続きを悪用したり逆手に取るような話はなかったが、そういう人たちが現れている。我々法律家は、制度を悪用する人に対しては、法律の解釈や制度を変えて対処していくことになるが、それにはどうしても時間がかかってしまう。ルールを破った人を罰したりペナルティを受けさせようとしても、それが実現するまでに時間がかかるので、結果的に破った人が得をしてしまう。特に選挙期間は短いので、ルールを破って当選することを法律家が防ぐことは難しい。
こうした法律家がすぐには対処できないことに対して、ぜひメディアの力でタイムラグを埋めてほしい。質的公平という意味で、ルールを破っている人を同じ候補者として取り扱うのか、ルールを破っていることをうまく伝えることはできないのかといったことも含めて考えいただきたい。
●参加者「有権者の投票に役立つ情報をどう伝えるか?」
記者1、2年目のときに先輩が、いくら選挙の取材をしても選挙が終わらないと伝えられないのは悔しいと言っていたのをよく覚えている。私もいま組織をまとめる立場になるとどうしても、量的公平性を維持してリスクを管理するのが仕事だというマインドになっている。やはり公平性・中立性の担保を優先すると面白みのない報道になってしまうので、その中から役に立つ情報をどう伝えて、どう投票行動につなげていけばいいのか悩んでいる。
●廣田委員長代行「バラエティ・情報番組でも正しい知識の共有を」
選挙制度に対する理解や質的公平と量的公平の問題については、報道の方は先輩記者から教わる機会が多々あり十分わかっていると思うが、ほかのバラエティ・情報番組の方や制作会社の方たちにもきちんとわかってもらうのが大切だと思う。いくら報道で量的にも質的にも公平を意識した番組を作ろうとしても、ほかの番組でただ尺を合わせるだけの放送をしているようでは変わっていくことはできない。報道だけではなく放送局全体として、選挙報道に対する正しい知識をみんなで共有することが重要だ。
論点④「SNS時代の選挙報道とは・・・」
●参加者「“オールドメディア”だからこそ果たせる役割は?」
兵庫県知事選挙をめぐって元県議会議員の竹内英明氏が亡くなったことについて、NHK党の立花孝志氏がSNSで虚偽の情報を発信したが、その後すぐに県警本部長がそれを否定したというニュースを報道したことでSNSが収まった。我々はオールドメディアと言われているが、オールドメディアなりに強い情報網を持っているので、選挙期間中においても自分たちが取材して裏づけを取って放送できるものに関してはきちんと放送することが大事ではないかと思う。
●大谷委員「信頼されるメディアとして、多くの受け手に情報提供を」
今回の兵庫県知事選挙では確かにSNSが大きな影響力を持ったが、その一方でマスメディアが全く機能しなかったわけではない。やはりSNSを利用しない世代の人たちはマスメディアの情報を信用しているし、またSNSの情報に惑わされている人もファクトチェックの機能をマスメディアに求めているところがある。
インターネットの情報は真偽を確かめるのが大変だという弊害があるが、人々は信頼性を疑いつつも便利、速い、簡単というところからSNSで情報を入手している。こうした状況においてマスコミ側は、受け手に多くの情報を提供していくことが引き続き重要ではないかと思う。
またコロナ下で、少数派であっても声が大きい人が主流を形成する傾向が強くなり、その声が大きい人の言っていることが正しいかどうかの判断は後回しにされているところがある。マスメディアには、こうしたSNSでの偏ったメッセージがひとり歩きしないような中立・公平な情報を提供する役割が今後は一層求められるのではないかと思う。
●毎日放送 大八木氏「有権者ファーストの選挙報道を」
基本的にSNSやネットで情報を入手するという波にはもう抗えないと思うが、そこで得られる情報とテレビなどのマスメディアが伝えていることには乖離がある。マスメディアの側がニュースだと思っていたことがだんだんそうではなくなってきて、こういう報道なんだと提示すること自体が間違っているのかもしれない。私は選挙報道は有権者ファースト的であるのが一番大事で、時代的にもそうなりつつあるのではないかと思う。そういう意味で、先ほど松田委員がおっしゃったとおり、感情的公平性をどう取るのかが非常に重要で難しい課題になる。
●松田委員「有権者の都合で検索できる動画やテキストを」
何か知りたいことがあったとき、SNSでは自分の都合で検索をするが、それに対して放送は時間のメディアであって、ニュースの時間が決まっているので、放送局はその時間に向けてニュースを作り、放送している。このため、今はニュース番組を見る側の視点と、ニュース番組を作る側の視点が違ってきているように感じる。放送局はこれまでのように時間のメディアとしてニュース番組を定期的に出す以外に、YouTube上で動画を公開したりテキストとして残したりして、見る側が自分の都合に合わせて検索して見るような、これまでとは違う接触の仕方を念頭にニュース番組制作を考えていかなければならないように思う。特に選挙はSNSでの時間の流れ方が違っていて、候補者は午後8時以降、街頭演説や選挙カーなどでの選挙運動を禁じられているのに、YouTubeを検索すれば夜中でも候補者の動画を見ることができる。以前は選挙という枠組みも選挙報道もほぼ同じ時間の流れにあったものが、SNSが主流になることで時間の流れにズレが生じており、その対応が必要なのではないかと思う。
-
これまでの議論を通じて、委員から放送局に改めてエールが送られた。
●松尾委員「今こそ自信をもって放送の使命の体現を」
インターネットの影響力が高まっている時代だが、そのような時代だからこそ、放送メディアには大きな役割があるのだ、と自信を持ってほしい。先ほどSNS上のデマに対して放送局が県警本部長のコメントを引き出してそれを打ち消したという例が挙げられたが、そうした例を多く実現して放送の使命を体現していただきたい。
●斉藤委員「視聴者も一緒になって考えていける放送局に」
人が少なくなってできることが限られてくる一方で、放送に加えてネットにも対応するため仕事量が増えて、そこで叩かれると萎縮してしまうのは同じ人間としてよく分かる。こういうときこそ、なぜ放送局に入社して報道をやっているのか、原点に帰って考えることが支えになると思う。
選挙報道に関して言えば、各局とも開票速報でスピードを競っているが、そのために労力を使うよりも、もっと大事なテーマを伝えてほしいと思う。例えば今、地球環境が危機にさらされているとき、候補者がそのためにどういう政策を持っているのか知りたい。特に原発問題や環境問題などいろいろな事象が複雑に絡み合った問題については、候補者はなかなか政策を語らないので、有権者が一番知りたいときに情報が得られない。
うわべが良くて人が食いつきそうなものが興味本位で先行してしまうと肝心なものが見えなくなるので、こういうときこそ自分たちが伝えたいことを自信をもって報道していただきたい。また、この時代をどう生きて行けばいいのか、視聴者も一緒になって考えていけるような放送局であってほしいと思う。
今回の兵庫県知事選挙に関しては、例えば検証番組を作って、放送局はどうすればよかったのかもう一度考えることもありうるのではないかと思った。
●國森委員「深く多面的な報道で安心と信頼を」
ある調査によると、今回の兵庫県知事選挙で斎藤知事に投票した人の46%がSNSの影響で投票したが、稲村和美氏についてはSNSの影響が5%、新聞・テレビの影響が66%となっているのは興味深い結果だと思う。
マスメディアとSNSのどちらが真実を伝えているか、多面的な伝え方をしているか、そうしたことを視聴者がわからなくなっているのが今日的な問題だが、それはマスメディアの人たちにはチャンスでもあると思う。みなさんが県警本部長から立花孝志氏の言説を否定するコメントを引き出したのは、まさにプロの矜持だ。
マスメディアは社会の大事なインフラの一つだと思う。またマスメディアが決定的にSNSと違うのは、みなさんのプロとしての力量、相手へのリスペクト、それから倫理も含めた専門的な知の集積をもって事実を追求している点にある。みなさんには現場にいる強さと地道な取材努力があって、それをもとに確かな根拠で報道できる。その資金力や圧倒的な技術力、カメラワークも含めた技術の蓄積も併せて、深く多面的に伝えることで正確さを増している。
放送は圧倒的な取材力と調査分析力を活かして、視聴者との間で一方的ではない双方向、多方向のやりとりをすることが安心や信頼につながり、これから先もサバイブできると思う。みなさんの事実に基づいた報道により視聴者の具体的な投票行動につながり、その投票が私たちの社会を豊かに成熟させていくので、みなさんのプロの矜持をもっと世の中に伝えていただきたいと願っている。
●鈴木委員長代行「ファクトチェックや嘘を打ち消す力を発揮して」
政治的公平に関しては、私が気にするなと言ってもみなさんは気にせざるを得ないのかもしれないが、これからは量ではなく質で考えるということを少しでも意識していただけたら嬉しく思う。
選挙の投票行動にはこれまでも口コミが大きく働く面があり、だからこそSNSで動くこともあるかと思う。SNSでは偽・誤情報がどんどん拡散してしまうので、どうしてもマスメディアはスピードについていけないところはあるが、先ほど具体例として出てきた県警本部長のコメントのように、報道機関のファクトチェックの力や嘘を打ち消す力は大きい。報道機関が何も情報を発信しないと偽・誤情報だけが拡散してしまうので、放送は決まった時間にしかニュースを出さないとは思うものの、スピード感を意識することも大事になっている。これからも民主主義のために放送が果たす役割は非常に重要であり、それが放送法の目的規定に書いてあることでもあるので、みなさんの仕事はますます大変になるけれどぜひ頑張っていただきたい。
●廣田委員長代行「放送にしかできないことを追求して」
SNS時代の選挙報道と言うが、私は放送にしかできないことがあると思う。自分の知りたいことだけを知るのではなく、民主主義のために知らなければならないことを伝えたり、正確な情報を伝えたりすることは放送にしかできないことだと思うので、あまりSNSのことばかりを意識せず、放送だからこそできることを追求していただきたい。
また、自分の当選を目的とせずに立候補するといったことについては、選挙制度の悪用になっていないかなど、選挙の時期だけではなく常日頃から選挙制度をきちんと報じて、民主主義における選挙の意義が情報の中で流通できるようにしていただきたいと心から思う。
- 最後に曽我部委員長が今回のテーマの総括とコメントを述べた。
<曽我部委員長>
●メディアだけでは解決できない課題がある
まず当然の前提ではあるが、選挙にまつわる様々な問題はメディアだけでは解決できない。選挙制度そのものの問題もあるし、選挙制度を逆手に取って物議をかもしている人たちに関しては、もしそれが選挙法令やその他の刑罰法規に触れるのであれば、適正な法執行を通じて責任をとっていただくことも公権力側の課題としてあると思う。
また先ほど國森委員から稲村陣営でSNSを見て投票した人は5%しかいないという話があったが、今のSNS上の選挙運動がある意味非常に不健全に見える背景には、既存陣営側が適切にネットを活用していない状況がある。そういう意味では、既存陣営側の見識不足という部分もあるので、制度の問題や撹乱する人たちだけの問題ではないということも忘れてはならない。
●今回の兵庫県知事選挙の非常な特殊性が弊害を生んだ
今回の兵庫県知事選挙はある意味、非常に特殊性があった。知事選挙は通常あまり有権者の関心が高くなく、有権者の間に候補者に関する知識がほとんどないことが多いが今回は違った。
また在阪局の本拠は大阪にあるので、兵庫県はどうしても取材が手薄になりがちで、兵庫県を本拠地とするサンテレビ以外の局にとってはやや扱いづらいところがあったのではないか。さらに地方選挙はローカル枠で扱うしかないため、そもそも放送尺が短いという問題がある。ただ今回は注目された知事選挙だったので、そうは言っても放送尺は取れたと思うが、その後立花孝志氏が泉大津市長選挙に出たように、あの規模の自治体では放送で取り上げることは極めて困難という中で、何かが起こったときにどう対応するか考えなければならない。
国政選挙に関しては、有権者もそれなりに知識があり、既存の枠組みもあり、メディアもより大きく扱うので、今回のような弊害が出てくる度合いは少ない。このため、メディアのみなさんが対応を考える時間はまだあると思う。
●テレビは感情のメディアから熟慮のメディアへ
松田委員から「SNSの感情に向き合う」という話があったが、私はこれを非常に感慨深くお聞きした。つまり、ネットの時代が来る前は、テレビは感情のメディアであり、お茶の間に侵入して視聴者の感情を直接揺さぶるものだった。それがテレビの魅力である一方で青少年に有害であるなどと言われていたが、今やSNSが出てくると、テレビは感情のメディアではなくて熟慮のメディアとしての役割が期待されるようになった。
●選挙報道はプロセスの重視を
選挙運動がいろいろな形で穴を突かれ、裏をかかれて、アテンションエコノミーの中に取り込まれているが、そうであるならやはり選挙運動期間中に何が起きているのか伝えなければならない。毎日放送・大八木氏から「結果からプロセスへ」という非常に示唆的なご指摘があったが、「プロセス」は選挙運動期間中に何があったのか伝えるという意味でもあると思う。
●専門家と連携したファクトチェックを
ファクトチェックに関しては、関係者の間でも限界が多々あり万能ではないと言われているが、それを克服するための試みも行われている。例えば、偽・誤情報がたくさん出てくるので、後からファクトチェックしてもなかなか追い付かないという構造的な問題に対しては「プレバンキング」という試みが行われている。プレバンキングとは、選挙の際に出てくる偽・誤情報や災害時に出てくるデマ情報など、定型的にわかっているものに対して、予め「こういうデマがありがちなので注意しましょう」と前もって呼びかけることをいう。
放送局が今後ファクトチェックに力を入れていくのであれば、ファクトチェックの団体や専門家がどういう議論をしているのか、どういう手法を取っているのか参照する必要があるし、場合によっては連携することも必要かと思う。ちなみに日本ファクトチェックセンターでは実際に放送局の人員を受け入れて、ファクトチェックをお手伝いいただいた例もある。
なおファクトチェックに関しては、番組で行うのも大事だが、偽・誤情報に影響を受ける人たちはテレビを見ていないので、ちゃんとSNSやネットにも情報を出さねばならないことは言うまでもない。
●業界として記者を守る姿勢を
記者への攻撃はグローバルな動向だ。国境なき記者団でも、記者に対する攻撃や暴力は報道の自由に対する重大な問題だという意識で活動しており、これは日本だけの問題ではない。それに対してはやはり記者を会社として守る、業界として守るという姿勢が重要で、今後はそうしたところをより強く打ち出す必要があると思う。
●メディアがどう考えているか、存在意義とは何か、青臭く発信を
最後に、これはこれまでご発言いただいた委員の方々と同感で、放送やマスメディアにできることは依然として多々あると思っているので是非ご尽力をいただきたい。
事前のアンケートに、自分たちが考える報道倫理について一般の方になかなか理解してもらえないというご指摘があった。先ほど来の記者への攻撃に対して報道界、メディア界、放送界として世間に向き合うことの重要性も併せて、メディアがどう考えているのか、メディアの存在意義が何なのかということを発信しなければならない。日本ではこういう大上段の情報発信は上から目線だと言われがちで非常に躊躇されるが、こういったことを言うのがメディアの存在意義なので、やはり青臭く言っていくことも必要なのではないかと思う。
以上